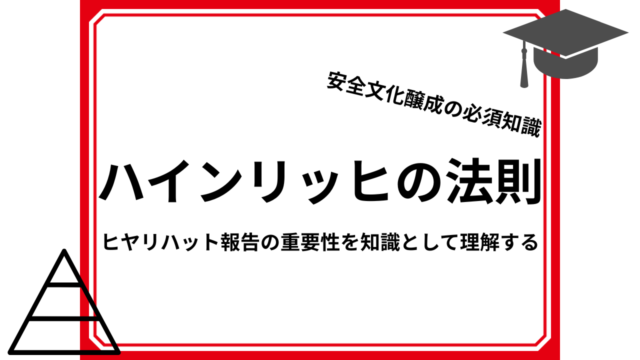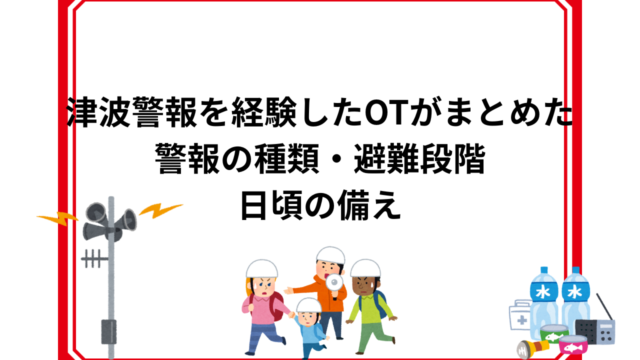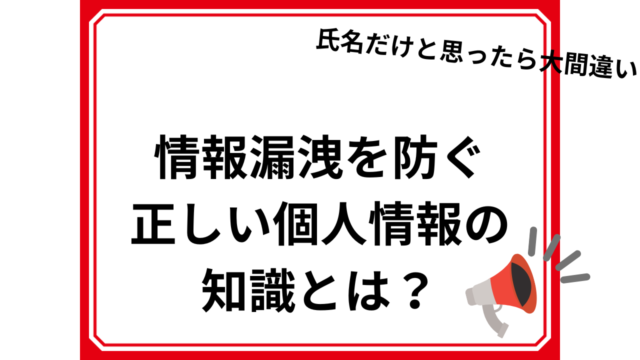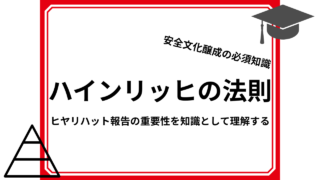🟦 医療現場でこそ必要な「KYT」とは?

医療や福祉業界で働いていると「なんでそんなことになったの?」と思わず感じてしまう事故やヒヤリハットが発生し、何か事故防止対策をしなくてはいけないと感じながら日々の忙しさに埋もれていってしまう…そんなことありますよね。
発生する事故の多くは、特別な状況下だけで起こるものではありません。
「いつもの業務」の中に潜む小さな違和感や、ほんの一瞬の油断が、大きな事故につながることもあります。
そこで大切なのが、KYT(危険予知トレーニング)です。
この記事では、医療・福祉の現場におけるKYTの基本と、現場でどう活かすべきかを医療安全管理者の資格を持つ作業療法士が解説します。
🟦 KYT(危険予知トレーニング)とは?

KYTとは “Kiken Yochi Training” の略で、目の前に潜む危険を予測し、事故を未然に防ぐ訓練のことです。
✅ KYTの基本ステップ(4ラウンド法)
- 現状把握(何が起きているか、何があるかを把握)
- 危険予知(どんな危険が潜んでいるか考える)
- 対策立案(その危険に対してどう防ぐか)
- 目標設定(安全行動の共有・実行)
これはもともと製造業などの現場で用いられてきたものですが、医療の現場にも非常に応用しやすい考え方です。
🟦 医療現場でKYTがなぜ必要なのか?

医療現場は「人の命」を扱うため、一つの判断ミスや確認漏れが深刻な事態につながる可能性があります。
医療でのKYTの対象例:
| KYTの対象 | 具体例 |
| 環境 | 点滴スタンドの位置/配線のひっかかり/床の水濡れなど |
| 手順・操作 | 投薬前の声かけ不足/検査前の本人確認ミス |
| チーム連携 | 引き継ぎの曖昧さ/伝達モレ/ダブルチェック不実施 |
| 感染対策 | PPEの不適切な着脱/手指消毒の不徹底など |
💡 ポイント:
「これは大丈夫だろう」という思い込みが最も危険です。
KYTは、気づく力・問い直す力を育てる訓練でもあります。
🟦 KYTを取り入れると現場がどう変わる?
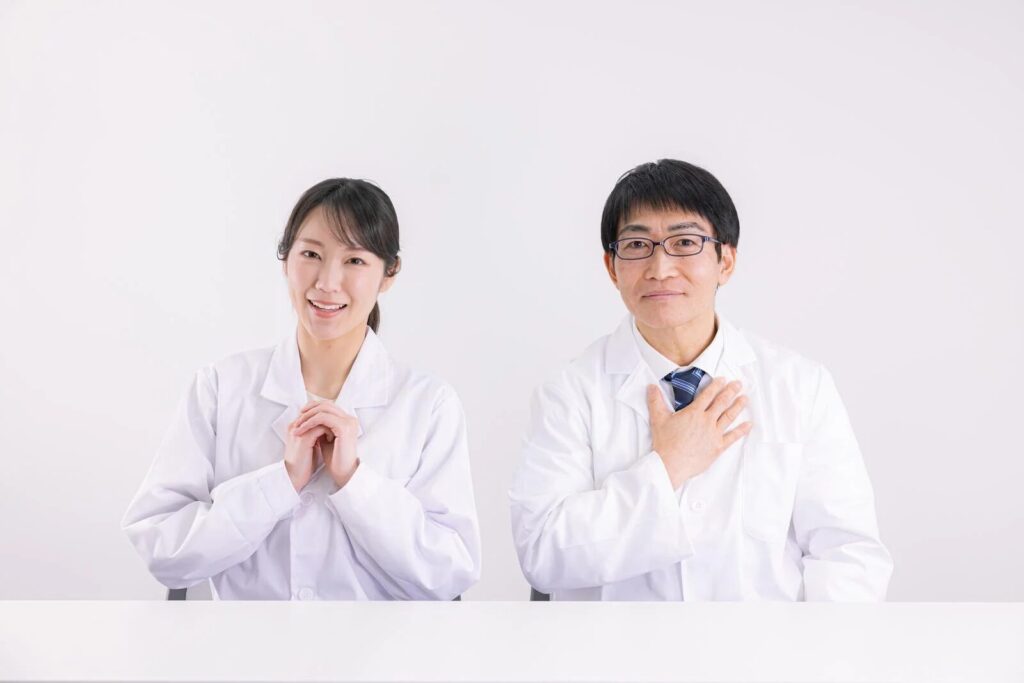
KYTは単なるトレーニングにとどまらず、現場全体の安全意識の底上げにつながります。
✅ KYT導入による効果:
- 現場スタッフ同士の「安全に関する会話」が増える
- 危険の予兆をキャッチする感度が上がる
- インシデント報告の質が高くなる(抽象→具体に)
- 新人教育にも有効(場面ごとの判断力が育つ)
✏️ 例(実施内容):
- 看護カンファレンスでの写真を使ったKYT演習
- 夜勤前の申し送り時に一言KYT
- 実際のインシデント事例をもとにグループ討議
🟦 「慣れ」や「思い込み」に潜むリスク

医療現場では「いつも通りにできている」ことが、安全とは限りません。
- 毎日行っている処置ほど見落としが起きやすい
- 「私は大丈夫」という思い込みが危険
- チームの雰囲気や疲労もリスクを高める
だからこそ、KYTで立ち止まり、意識的に“危険を予知する”習慣を持つことが大切です。
🟦 まとめ:小さな違和感に気づける組織に
KYTは、「ミスを無くす」ためだけでなく、「気づける人材と文化を育てる」ための訓練です。
✅ まとめポイント:
| 項目 | 内容 |
| KYTとは | 危険を予測し、対策を考える訓練 |
| 医療現場での例 | 手順ミス・確認不足・連携エラーなど |
| 効果 | 感度UP・報告精度UP・新人教育への活用 |
| 継続のコツ | チームで話す、振り返る、共有する習慣 |
📣 最後に
医療事故ゼロを目指すには、「危険を予防できる現場づくり」が不可欠です。
KYTを単なるイベントで終わらせず、日常に根付かせる工夫を一緒にしていきましょう。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。