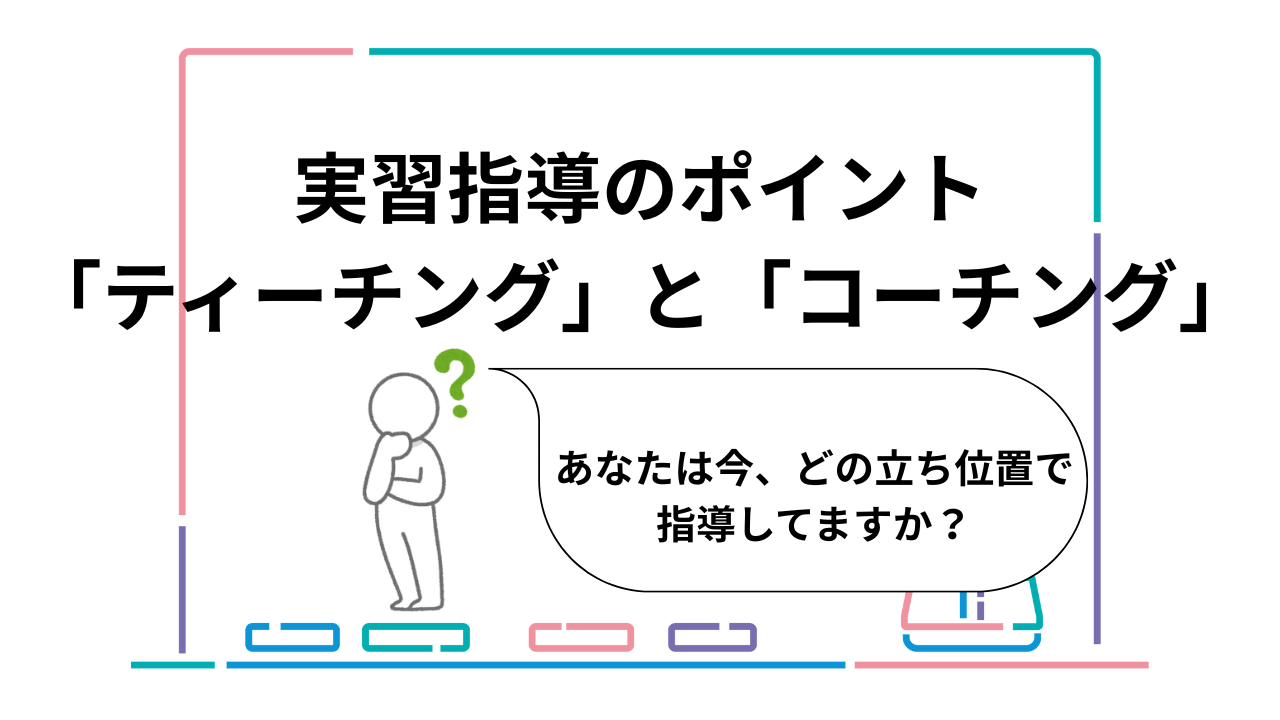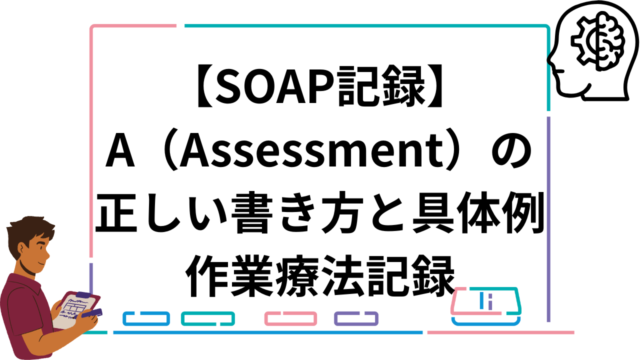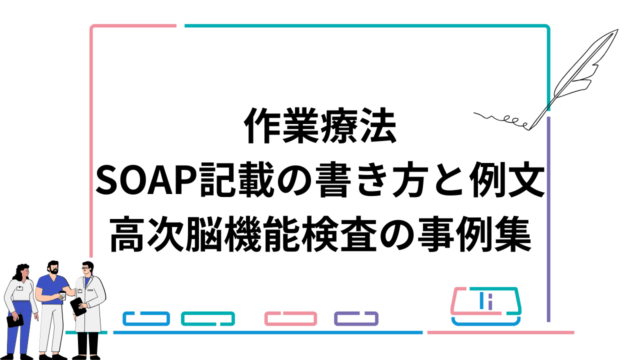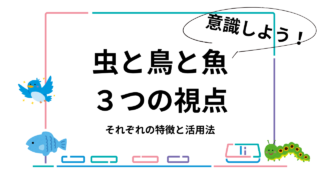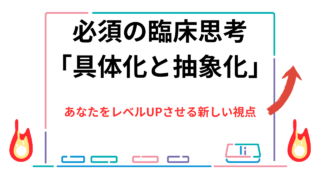― 成長を支える2つのアプローチを状況に応じて使い分けよう ―
🎓 実践型医療教育「CCS」指導におけるティーチングとコーチングの使い分けとは?

クリニカル・クラークシップ(CCS)は、医療系学生が臨床現場に積極的に参加し、患者との直接的な関わりを通じて「自ら考える力」や「臨床的判断力」を養う実践型の教育モデルです。単なる知識や技術の習得にとどまらず、実践的な思考力や主体的な支援力を育てることがCCSの本質です。
このような学びを効果的にサポートするためには、指導者が「教える力(ティーチング)」と「引き出す力(コーチング)」の両方を適切に使い分ける視点が欠かせません。学生の成長段階に応じて、教え導く場面と問いかけて気づきを促す場面を柔軟に切り替えることで、学習効果が飛躍的に高まります。
本記事では、CCSにおける効果的な学生指導法として、ティーチングとコーチングの違いと活用法をわかりやすく解説します。これから指導に関わる医療者・教育者の方は、ぜひご一読ください。
①CCS指導には「ティーチング」と「コーチング」の両立が不可欠

クリニカル・クラークシップ(CCS)は、作業療法士や理学療法士を目指す学生が実際の臨床現場で学びを深める重要なプログラム。CCSの最大の目的は、「未来の療法士を現場でしっかり育てること」にあります。
このため、指導者が果たす役割は非常に大きく、単に知識や技術を教えるだけでなく、学生の主体性や思考力を育むことも求められます。
このCCS指導で特に重要となるのが「ティーチング」と「コーチング」という二つの指導法のバランスです。
ティーチングの役割
ティーチングは、基礎的な知識や技術を確実に学生に伝える指導方法です。
例えば、関節可動域(ROM)測定の正しい方法や、SOAP記録などの評価記録の書き方を丁寧に教えることがこれにあたります。
これらは学生の基礎力となる部分であり、誤った方法や不完全な知識が現場での混乱やミスにつながるため、指導者は正確かつ具体的に指導する必要があります。ティーチングは「成長を与える」指導とも言え、学生が最低限の技術や知識を身につけるために欠かせないアプローチです。
コーチングの重要性
一方で、コーチングは学生の思考力や判断力、内省力を促進する指導方法です。
学生自身が自ら考え、問題を見つけ、解決策を探る力を養うことを目的としています。
例えば、患者の状態を観察して気づいた点を自分で整理し、次にどのような介入が必要かを自発的に考えるよう促すことがコーチングにあたります。こうした指導は、学生の主体的な行動や創造的な思考を引き出すために不可欠であり、「成長を引き出す」役割を担います。
CCS指導に求められる「両立」
つまり、CCSでの指導は「基礎的な技術や知識を確実に伝えるティーチング」と、「学生の自発的な成長を促すコーチング」の両方をバランスよく行うことが重要です。
一方に偏ると、学生はただ指示を待つ受け身の姿勢になったり、逆に基礎知識が不十分で現場に適応できなかったりするリスクがあります。
この両立こそが、CCS指導で未来の優れた療法士を育てるために欠かせないポイントと言えるでしょう。
つまり、 成長を与える(ティーチング) と 成長を引き出す(コーチング) の両方がバランスよく求められるのがCCSです。
②学生の成長ステージに応じて支援方法を切り替える必要性

CCSでは、学生は「病院や地域でのリハビリ場面を自ら体験し実践する機会」を得ますが、実習開始段階では未熟さゆえに判断力や行動力が限られています。
この段階では、明確な指導やモデル提供(ティーチング)が必要です。一方、実習半ば以降では、学生の自主性や内省力を引き出すコーチングにスイッチすることで、「実践的で自律的な学び」が成立します。
| 指導フェーズ | ティーチング(教える) | コーチング(引き出す) |
| 実習初期 | ROM測定、SOAP記録、手順の説明 | 「この記録で何を伝えたい?」「どう感じた?」 |
| 中盤以降 | 評価FIMと介入設計方法の指導 | 「この介入でクライアントにどんな変化が?」 |
| 失敗・戸惑い時 | 基本対応や手技の適切な実施法指示 | 「なぜその選択になった?次はどうしたい?」 |
| 実習終盤 | 文献やモデル例の紹介 | 「自ら気づいた変化と今後の介入目標は?」 |
学生の成長ステージに合わせて、このように両者を柔軟に切り替えることが、自立的な療法士への道を後押しします。
③【具体例】ティーチングとコーチングの使い分けシーン

実習初期:観察導入フェーズ
- ティーチング:
- 「ROMの測定方法をこのように行ってください」
- 「SOAP記録の各欄には、こういう情報を入れます」
- 「ROMの測定方法をこのように行ってください」
- コーチング:
- 「このROM記録から、何を読み取りましたか?」
- 「SOAPの記録を見て、患者の状況はどう理解できますか?」
- 「このROM記録から、何を読み取りましたか?」
中盤:評価・介入設計フェーズ
- ティーチング:
- 「FIMやADL評価の分類・スコアリング方法を教えます」
- 「FIMやADL評価の分類・スコアリング方法を教えます」
- コーチング:
- 「この人にとって『更衣』がどんな意味を持っていると思いますか?」
- 「どうしたら本人の希望に近づく介入になるか、一緒に考えてみましょう」
- 「この人にとって『更衣』がどんな意味を持っていると思いますか?」
失敗や迷いが生じたとき
- ティーチング:
- 「この場面では、基本対応として〇〇を優先する方が安全です」
- 「この場面では、基本対応として〇〇を優先する方が安全です」
- コーチング:
- 「なぜその対応を選んだのか、自分の考えを教えてもらえますか?」
- 「もし別の対応を選べたとしたら、どう考えますか?」
- 「なぜその対応を選んだのか、自分の考えを教えてもらえますか?」
実習終盤:振り返りと統合
- ティーチング:
- 「この文献には、成功例や評価のヒントがあります」
- 「この文献には、成功例や評価のヒントがあります」
- コーチング:
- 「この介入で患者さんにどんな変化がありましたか?」
- 「今後、どのように支援を継続したいですか?」
- 「この介入で患者さんにどんな変化がありましたか?」
④【まとめ・再主張】指導の柔軟さが、学生の自立性を育む

視点ごとの役割を整理すると、以下のようになります:
| 観点 | 内容 |
| ✅ ティーチング | 知識・技術を正しく伝える → 安定した基礎を形成 |
| ✅ コーチング | 学びを自分で発見させる → 自立的な主体性育成 |
| ✅ バランス | 学生のステージに応じて両者を柔軟に併用することが重要 |
ティーチングは“教え”、コーチングは“引き出し”。この2つを適切に使い分けることが、実習指導における「育てる指導」から、「育つ指導」への転換を実現します。
🔚 最後に|「教える」だけではなく「問いかける」ことで育つ学生たちへ
CCSでは、学生がただ情報を受ける受け身の立場では終わりません。
「教えることで導き、問いかけることで自立の芽を育てる」。この二重構造こそが、未来の作業療法士を育てる本質的アプローチです。
学びを与えた後に、「その先」を学生が自ら考え、自ら行動できるよう促すことで、真の成長と臨床推論力の醸成が期待できます。これが、CCS指導における最大の使命ともいえるでしょう。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。