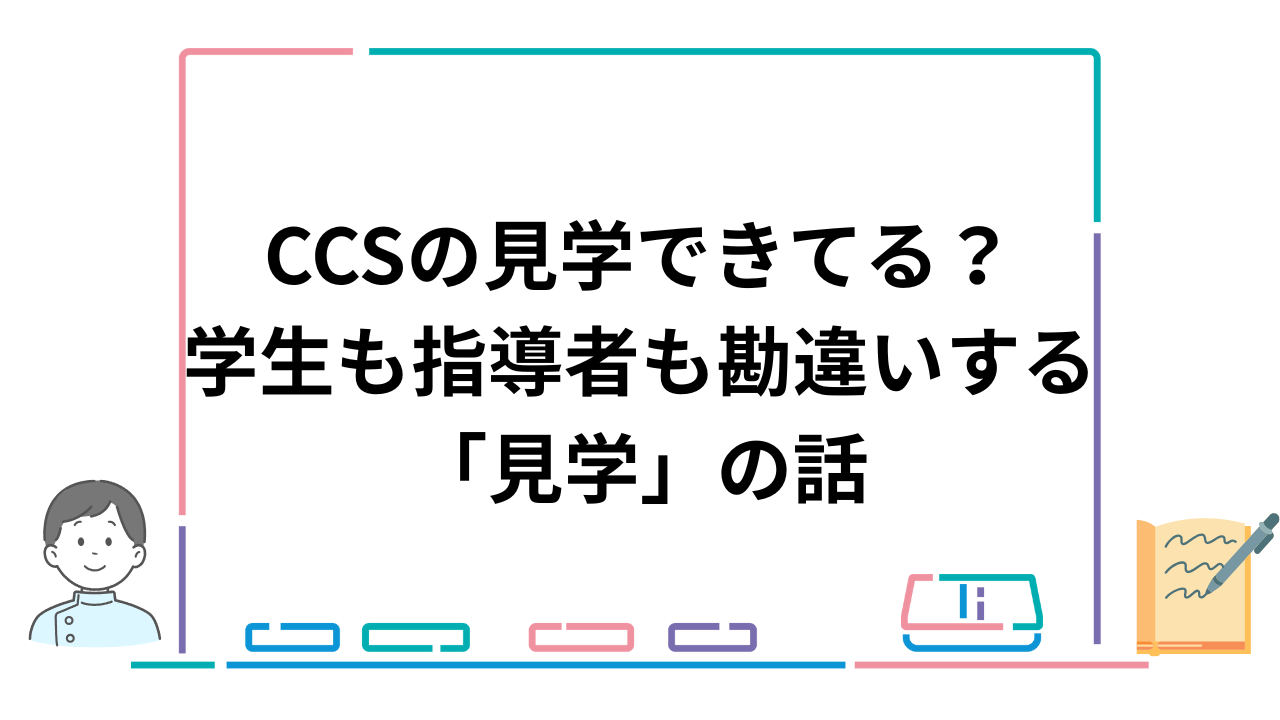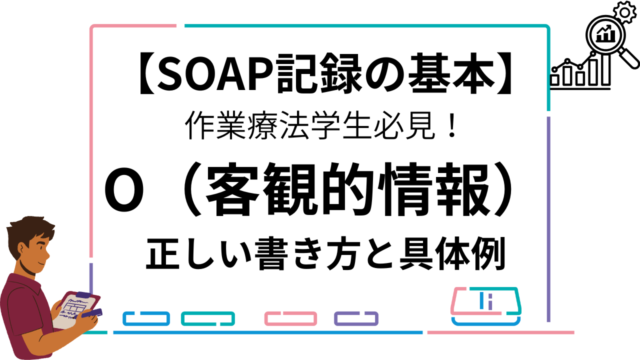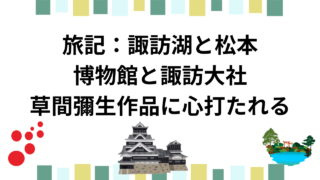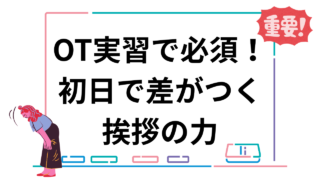クリニカルクラークシップ(Clinical Clerk Ship、以下CCS)は、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士を目指す学生にとって、臨床の現場で学ぶ大切なステップです。
その最初の段階にある「見学」は、ただ現場を見て過ごす時間ではありません。
しかし、多くの学生や一部の指導者は、この見学を「ただ一緒について行って眺めること」と誤解してしまうことがあります。
結果として、学校に提出する評価表では「見学」ができているように見えても、実際には学びが浅くなっているケースも少なくありません。
本来の見学とは、バイザー(指導者)と事前に「何を目的として」「どの視点で」「どの手順を意識して」見るのかを共有した上で行うもの。
この事前すり合わせがあることで、現場を観察しながら深く理解でき、質問やフィードバックによって知識と技術が定着します。
この記事では、CCSにおける見学の正しい意味と、学びを最大化するための具体的な行動方法を解説します。
見学=ただ見る?その誤解が学びを浅くする
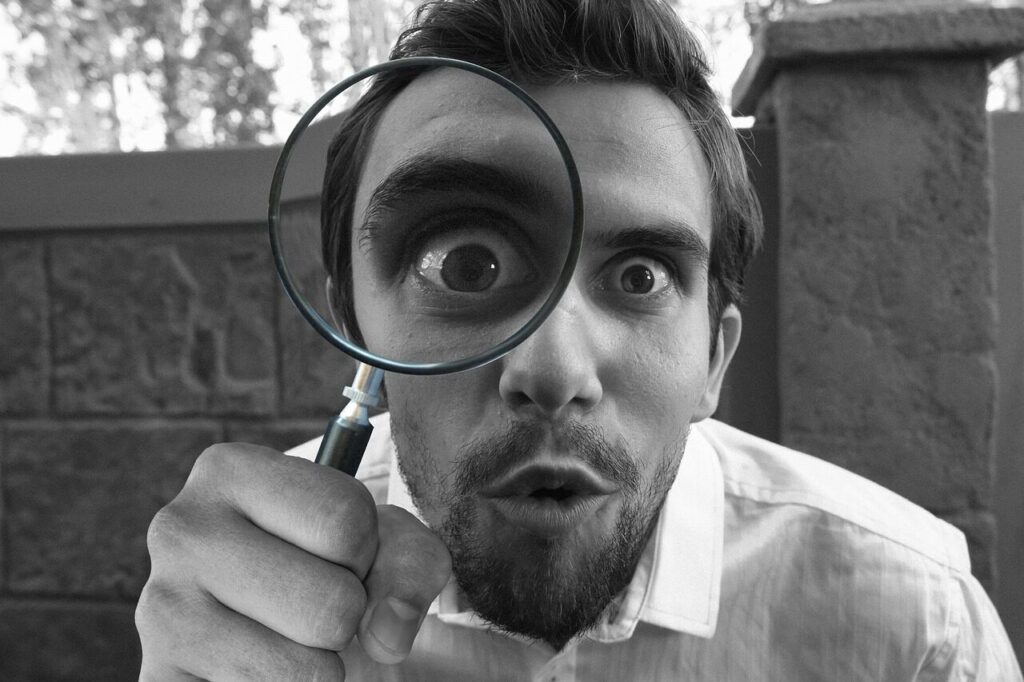
CCSは、作業療法・理学療法・言語聴覚療法の実習における重要な学習形態。
なかでも「見学」は最初のステップとして位置づけられていますが、現場では「ただ患者さんの様子や治療を眺めること」と誤解されがちです。
実際、学校の評価表では見学項目に○が並んでいても、学びが深まっていないケースが多くあります。
よくある誤解は、
「一緒について行って、関節可動域測定や治療プログラムを見た=見学が終わった」
という考え方です。
しかし、事前すり合わせのない見学は、表面的な情報しか得られず、質問も具体性を欠きます。
結果として、臨床推論や評価スキルが身につかないまま時間だけが過ぎてしまいます。
CCSにおける「見学」の正しい定義と意義
CCSにおける「見学」は、ただ現場で作業療法士や医療スタッフの行動を“目で追うだけ”の行為ではありません。
本来の見学は、「準備」→「観察」→「理解」→「学びの定着」 という流れを持った、能動的な学習活動です。
- 事前オリエンテーション:目的を明確にする
- 教わる:観察ポイントと注意点を押さえる
- 理解:知識を点と点から線へ繋げる
- 学びに変える:振り返りで学びを定着させる
このステップを意識することが、CCSでの成長を大きく加速させます。
CCSの正しい見学の流れ:見学前のオリエンテーション

- 事前オリエンテーション
当日の目的・対象者の状況・観察の焦点をバイザーと確認 - 観察中の意識
バイザーの動作・声かけ・評価ポイントを意図と結びつけて見る - 質問とフィードバック
見学後すぐに疑問点を共有し、実践的な回答をもらうことで理解を深める
CCSの見学は絶対的に事前に担当セラピストから
・何の目的で
・どういう意図で
・何に注意して
治療に当たっているのかを「教わる」ようにしてください。
そうすることで何に注目して見学するかが明確になり、学びも深まると同時に自然と「何であれをやったんだろう?」と疑問や質問が浮かんできます。
つまり、事前オリエンテーション(事前に教わる姿勢)は学びのスタート地点に立つための重要なポイントであることがわかると思います。
1. 事前準備がすべての土台
見学に入る前に、必ずバイザー(指導者)と目的、注意点、実施のポイントを共有します。
たとえば、
- 今日は患者さんの関節可動域訓練の仕方に注目したい
- ベッドやトイレ、椅子といった移乗介助の注意点を学ぶ
- 検査のやり方に加えて、声掛けや表情といったコミュニケーション方法をみる
など、観察する焦点を明確にします。
繰り返しになりますが重要なので…
目的があいまいなまま見学をすると、ただ“何となく眺めている時間”になってしまい、学びの質が大きく下がります。
2. 観察すべき視点や注意点を理解する
目的が決まったら、どの場面を重点的に見るべきか、学生側から確認します。アウトプットをすることで自分が本当に整理できているか、学ぶ準備ができているかがわかります。
たとえば、
- 可動域訓練は最初から最大可動域まで挙げず、声掛けしつつ表情をみて挙げていく
- 移乗動作は移乗先と車椅子の設置位置が安全配慮で最も大切
- 検査は「私もわからなくなることありますよ」などの共感を意識して声掛けする
こうした学びのアウトプットを自ら意識して行うことが大切です。
バイザーからの話をただ聞くのではなく、すぐに確認する目的意識を持っていると聞き方も意識も大きく変わるはずです。
そうやって 「何を見るか」を明確にできると同じ見学場面でも得られる情報量が格段に増えます。
3. 実施手順の背景や意図を知る
見学では、単に“何をしているか”を見るだけでなく、なぜその方法を選んだのかという背景や理由を理解することが重要です。
たとえば、評価手順の順番や道具を使うタイミング、声かけの仕方には必ず意図があります。
事前にバイザーから
「この患者さんの場合は○○だから、この順番で行う」
と説明を受けておくと、観察内容がより深く理解できます。
4. 見学の効果を最大化するために
- 質問をためらわない:わからないことはその場で聞くか、メモして後で質問する
- 記録を残す:観察したことや気づきをノートにまとめる
- 振り返りを行う:見学後に目的と照らし合わせて学びを整理する
このプロセスを踏むことで、見学は“受け身の時間”ではなく、自分の臨床力を伸ばすための実践的な学習時間になります。
学生とバイザーの良好なコミュニケーションの築き方

多くの作業療法士やリハビリセラピストは、学生が積極的に学ぶ姿勢に好意的です。たとえば、見学前に「今日の学びのポイントを教えていただけますか?」と一言伝えるだけで、指導内容がより具体的になり、学びの質が格段に向上します。
現場は多忙なため、時には返答が得られないこともありますが、それは個人の対応やその時の状況によるものであり、学生の姿勢や意欲が間違っているわけではありません。大切なのは、常に前向きな態度でコミュニケーションを重ね、信頼関係を築くことです。
まとめ
CCSの見学は「ただ見る時間」ではなく、「目的を持って学ぶ時間」です。
- バイザーとの事前すり合わせ
- 観察中の意識
- 見学後のフィードバック
というステップを勇気を持って行動し、実践することで、実習での学びは格段に深まります。
この習慣は、将来の臨床現場でも必ず役立ちます。
立ち止まらずに行動して、より良い未来に向かって学びを深めてください
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。