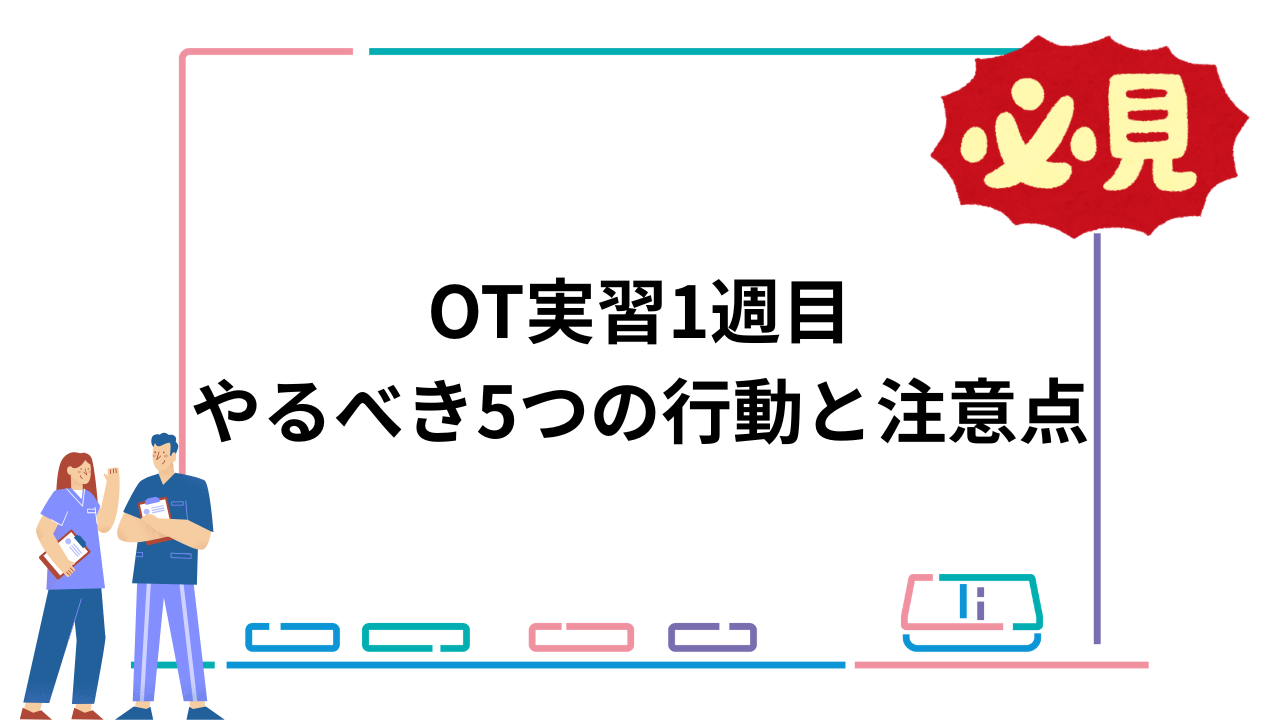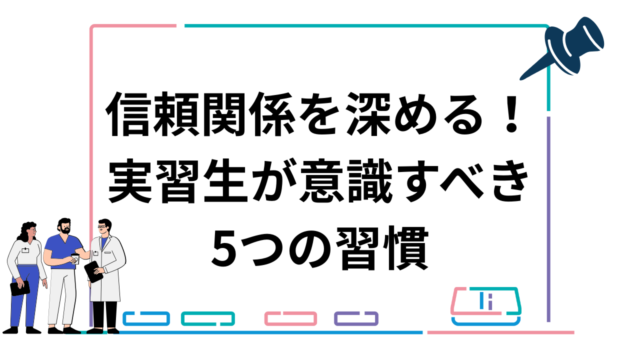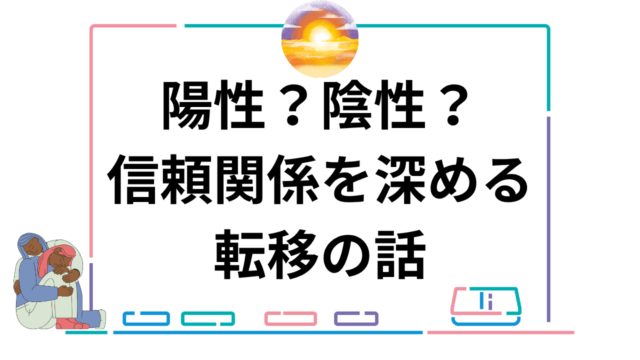作業療法実習の1週間目は、単なる導入期間ではなく、その後の実習全体の評価や学びの深さを左右する極めて重要な時間
最初の印象や行動パターンは、指導者やスタッフからの信頼感に直結し、臨床での学びの質を大きく変えます。
この時期に意識すべきは、
- 現場とクライアントの情報収集
- スタッフや患者さんの名前を覚える
- 他職種との関わり
- 現状の治療プログラムとその経緯
- ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)
の5つです。
情報収集は単なる事実把握ではなく、患者さんの生活背景や施設の特徴を理解することにつながります。
名前を覚えることは信頼関係の第一歩であり、患者さんの靴や持ち物に書かれた名前など小さな手がかりも活用できます。
他職種との関わりはチーム医療の理解を深め、ADL観察は評価力と介入の精度を高めます。
「作業療法 実習 1週間目」「ADL観察」「作業療法 実習 名前 覚える」といったテーマに悩む学生に向け、本記事では初動で差をつけるための具体的行動と実践のコツを紹介します。
① 情報収集 — 実習最初の1週間の最重要タスク

作業療法実習の1週間目は、まず現場の全体像を把握することから始まります。
見学に入る患者さん一人ひとりの診療情報はもちろん「担当指導者や病院や施設の1日の流れ」を押さえることが大切です。
さらに見学を通して病院や施設で使用している評価用紙や検査道具を一通り知っている状態にすることも身体機能、高次脳機能を評価、検査するOT実習では必須。
クライアントの情報収集は、カルテや申し送りノート、担当スタッフ間の会話など多様な情報源を活用しましょう。
- 「クライアントのカルテ情報がみたい」
- 「他部門の理学療法士や言語聴覚士の見学をしたい」
- 「カンファレンス(クライアントの会議)に参加したいがいつに開催か知りたい」
こんな声掛けを指導者にできたら、具体的で翌週の実習スケジュールもある程度見通しがたってスムーズな実習2週目になりそうですね。
また、患者さんの生活歴や趣味、退院後の生活環境といった医学的情報だけでなく、生活背景にも注目することが作業療法士としての視点を養います。
ここは次の信頼関係の項目も参照にして自分でも情報収集していきましょう。
それらを把握した上で単に「知る」だけでなく、指導者の日々の介入で「なぜこの治療プランになっているのか」という理由を考えながら情報を整理、時には直接質問することで、学びが深まります。
② スタッフや患者さんの名前を覚える — 信頼関係の第一歩

名前を覚えることは、良好なコミュニケーションの土台です。
患者さんやスタッフの名前を早い段階で覚えると、現場での会話がスムーズになり、指導者やチームからの信頼感も高まります。
人間自分の名前を一番大事にしているものですから。
具体的には、名札や靴、持ち物、カルテの表紙などを観察して記憶の手がかりにします。
また、挨拶のたびに名前を口に出すことで、記憶の定着が早まります。
- 「○○さん、おはようございます」
- 「初めて知りました。○○さん、詳しいですね」
- 「○○さんにお聞きしたいことがあるんですが…」
と繰り返す習慣は、相手にも好印象を与えます。
名前を覚える努力は「私はあなたを大切に思っています」というメッセージにもなり、人間関係を円滑にします。
③ 他職種との関わり — チーム医療を学ぶ絶好の機会

作業療法士は、医師、看護師、介護士、ソーシャルワーカー理学療法士、言語聴覚士など、多くの専門職と連携して患者さんを支援します。
実習1週目から積極的に他職種の動きに目を向けることで、チーム医療の全体像を把握できます。
他職種カンファレンスや申し送りに参加する際は、ただ聞くだけでなく「この情報は作業療法にどう関わるか」を意識しましょう。
退院が近い患者さんの場合はケアマネさんとの情報も入ってくるのでよく聞いておくといいです。クライアントも同様に同じ流れで退院になる可能性があるためです。
また、他職種の方に質問する際は、専門性を尊重しながら簡潔に聞くことが大切。
看護師や介護士(夜間の様子は重要)
- 昼と夜では課題や話題が全く異なることも多々あります。
- 入浴やトイレ、食事といった日常生活の様子も詳しく知っています。
ソーシャルワーカー(MSW)
- 家族背景や地域相談員(ケアマネ)
- 施設入所先について医師と共有していること(薬剤の関係で調整中など)
- 退院に向けた見通し
を情報として持っていることが多いです。
ここで築いた人間関係は、実習後半の学びやすさにも直結します。
④ 現状の治療プログラムとその経緯を理解する

患者さんが受けている治療プログラムは、その方の評価結果や生活背景、ゴール設定に基づいて作られています。
実習1週目は、この「なぜ今のプログラムなのか」という経緯を理解することが重要です。
といっても1週目で過去も含めて把握できるはずがないので、指導者に質問をしましょう。
- 「ROMと促通訓練を時間をかけて実施しているように感じたのですが、発症から1ヶ月で回復の予後予測をしてでしょうか」
- 「立位訓練と方向転換のステップ練習を重点的にやっていましたが移乗動作に課題がある状況でしょうか」
担当患者さんの評価内容や経過記録も確認し、治療の目的・方法・頻度・難易度を整理しましょう。
また、治療プランが変更された場合、その背景や判断理由を指導者に尋ねることで、臨床推論力(クリニカルリーズニング)が磨かれます。
これらは将来作業療法士になった際に役立つ力です。
⑤ ADL観察 — 評価力を磨く最初のステップ

ADL(Activities of Daily Living:日常生活動作)の観察は、作業療法士の基礎スキルです。
1週目から、食事・更衣・移動・排泄・入浴などの場面を意識的に観察しましょう。
観察のポイントは「できている/できていない」だけでなく
- 「どういう工夫をしているか」:自助具や姿勢、環境設定
- 「どこで困難があるか」:動作・作業分析
- 「安全面でのリスクはないか」:転倒転落、打撲や擦過傷
を見極めることです。
さらに、患者さんの表情や動作の速度、補助具の使い方にも注目すると、より質の高い評価ができます。
ADL観察で得た情報は、治療プランの修正やゴール設定の根拠にもなります。
まとめ

作業療法実習の1週間目は、単なるウォーミングアップではなく、その後の学びや評価を大きく左右する重要な期間です。
- 情報収集によって現場理解を深め
- 名前を覚えることで信頼関係を築き
- 他職種との関わりからチーム医療の本質を学び
- 現状の治療内容の経緯を知りつつ、
- ADL観察によって評価力を高める。
この5つの行動は、実習を成功させるための土台となります。
1週目の初動で積極的に動き、細やかな観察と記録を心がけることで、実習中の成長スピードは格段に上がります。
今日からできる小さな一歩を積み重ね、臨床現場で自信を持って行動できる作業療法士を目指しましょう。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。