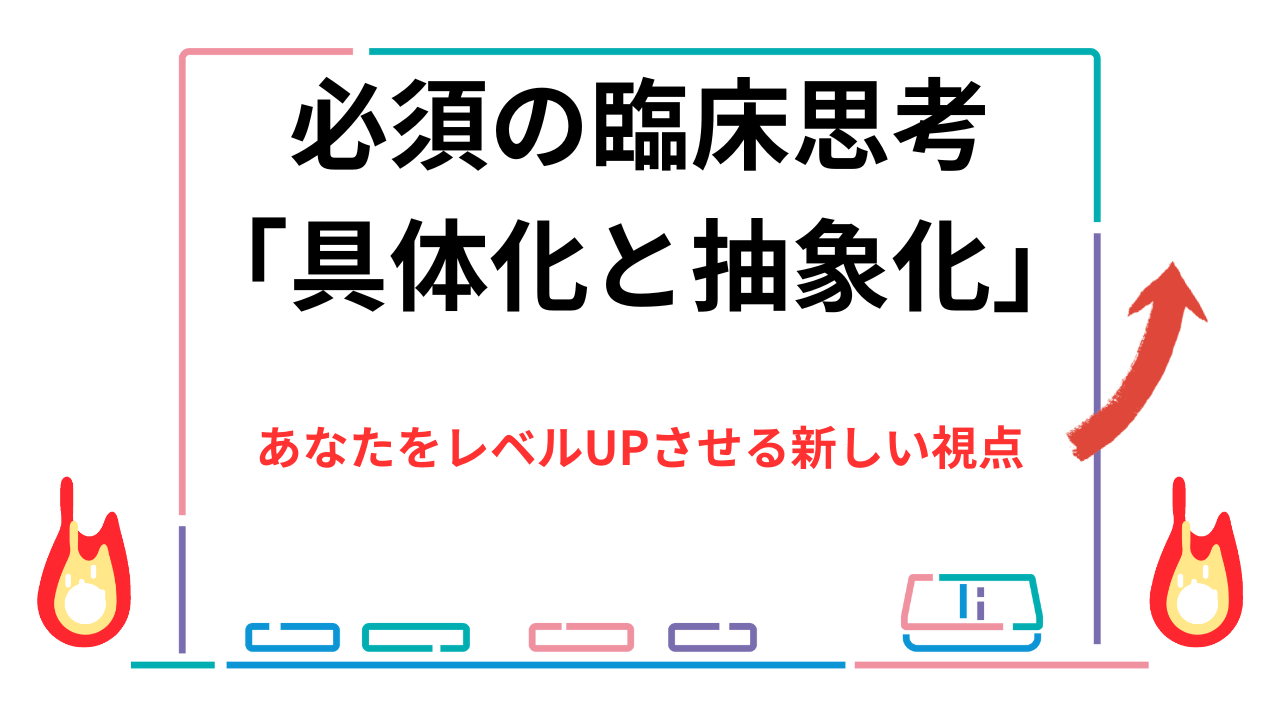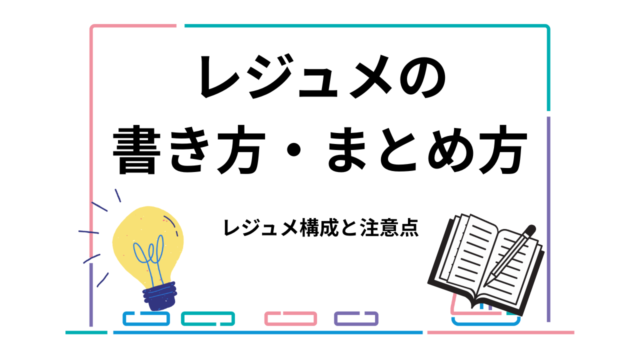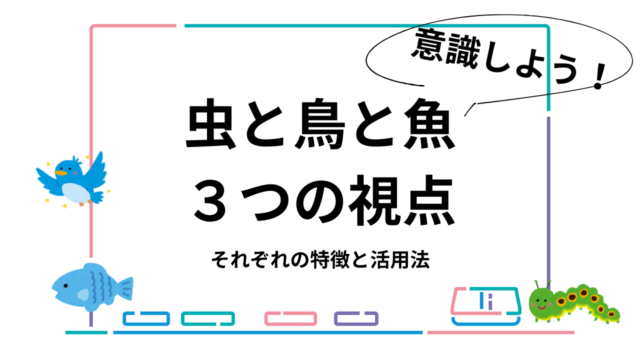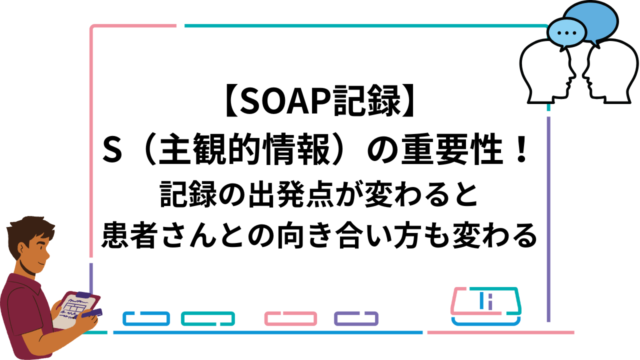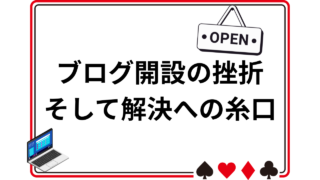🔰 作業療法における「具体化」と「抽象化」はなぜ重要なのか?

作業療法の臨床現場では、「評価や観察はしているけど、支援にうまくつながらない」「実習での学びが、点のままで終わってしまう」といった悩みを抱える方が少なくありません。
実はその原因の多くが、「具体化」と「抽象化」という思考のプロセスが不十分であることにあります。
作業療法士は、目の前のクライアントの行動や症状を細かく観察して言語化(=具体化)し、そこから意味や本質を導き出す(=抽象化)力が求められます。
この記事では、作業療法士が身につけるべき「具体化と抽象化の思考法」について、実際の臨床場面や記録の例を交えながら、わかりやすく解説します。
臨床での思考力を高めたい方、実習や記録に悩む方、支援の質を高めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
■ 作業療法における「具体化」と「抽象化」とは?

― 臨床に欠かせない2つの思考スキル ―
作業療法士(Occupational Therapist:OT)は、ただ患者の行動を記録するだけの職種ではありません。また、理論や知識を一方的に語ることが専門性を示すわけでもありません。
むしろ、作業療法の本質は、「一人ひとり異なるクライアントの生活に深く入り込み、その人らしい生き方を再構築すること」にあります。
このような実践的かつ人間中心の支援を行うために、作業療法士にとって極めて重要になるのが、「具体化」と「抽象化」という2つの思考スキルです。
✅ 具体化とは?
「具体化」とは、クライアントの行動や状況を細かく観察し、言語化・数値化して問題の構造を明らかにする力です。
たとえば、
- 「腕が上がらない」という表現を「ROM(関節可動域)で肩関節90°以降はブルンストロームステージⅣのため随意性が乏しく、上肢挙上困難になる」と具体的に数値で表す
- 「更衣が難しい」という訴えを「Tシャツを着る際に肩関節の可動域制限に加えて、座位保持が難しくバランスが取れず作業遂行できない」と動作レベルに落とし込む
といった具合に、曖昧な現象を明確にする技術が「具体化」です。
このスキルは、作業療法の評価場面やSOAP記録の作成時に特に重要であり、課題の本質を捉え、支援の的を絞るための基盤となります。
臨床場面では「どこに課題があるのか」「何をどう支援すればいいのか」を明らかにすることで、より効果的で個別性の高い介入が可能になります。
✅ 抽象化とは?
「抽象化」とは、観察や体験から得られた情報の背後にある意味を見抜き、共通点や本質を導き出す力です。
たとえば、
- 「更衣動作の自立がゴール」だった事例で、「実は本人にとって“朝の身支度”は一日のリズムを整える大切な儀式だった」と気づく
- 複数の事例から、「作業療法支援では身体機能の改善以上に、生活文脈の理解がカギになる」ことを導き出す
といった思考が、まさに抽象化です。
このスキルは、臨床での経験を深い学びに変換する力でもあります。
症例報告の整理や学会発表、実習後の振り返りにおいて、抽象化によって導き出された知見は、「点」の経験を「線」や「面」に広げていく力となります。
■ なぜ「具体化」と「抽象化」の両方が必要なのか?

作業療法の臨床では、「この人にとって最適な支援は何か?」という問いに対して、個別性と普遍性の両立が求められます。
具体化ができないと、支援の焦点が曖昧になり、表面的な対応に終始してしまいます。
一方、抽象化ができないと、経験が蓄積されず、似たような場面で応用が利かないままになります。
両方のスキルを使いこなすことで、
- 目の前の対象者を深く理解できる(具体化)
- その経験から新たな知見を導き、他に活かせる(抽象化)
という思考の循環が生まれ、作業療法士としての臨床力・支援力・説明力が格段に高まります。
■ 作業療法における「個別性」と「普遍性」― 現場で求められる柔軟な思考

作業療法の現場では、「同じ病名の人には同じ支援をすればよい」という単純な考え方は通用しません。
なぜなら、人はそれぞれ異なる背景を持って生活しているからです。
たとえば、脳卒中を経験した高齢者が二人いたとします。AさんとBさんは、診断名も、片麻痺の程度も似ているかもしれません。しかし実際には、
- 住んでいる環境(バリアフリーの有無)
- 家族との関係性(同居・独居・介護者の有無)
- 大切にしている価値観や生活習慣(仕事や趣味、人生観)
- 社会的な役割(地域活動や家庭内での役割)
など、多くの要素がまったく異なっていることがほとんどです。
このように、同じ「病気」でも、その人が置かれている状況や求める支援の形は一人ひとり異なります。これが作業療法における「個別性」の原則です。
● 「具体化」で“その人らしさ”に迫る
こうした個別性に丁寧に向き合うために必要となるのが、「具体化」という思考プロセスです。
具体化とは、対象者の行動や反応、生活場面での困りごとを、表面的な印象ではなく、具体的な言葉やデータとして捉える力を意味します。
具体化の力があることで、何が課題で、どこをどう支援すればよいかが見えてくるのです。これは評価・記録・介入すべてに関わる重要なスキルです。
● 「抽象化」で“学び”を広げる
一方で、具体的な事例に対応するだけでは、経験が「その場限り」で終わってしまいます。
支援経験を積み重ねるなかで、複数の事例に共通する特徴や、背景にある課題の構造に気づいていくことが求められます。これが「抽象化」です。
抽象化とは、一つひとつの臨床経験から意味を見出し、本質的な教訓を導き出す力です。
複数の支援経験から「支援は身体機能だけではなく、生活の文脈に寄り添うことが重要だ」といった普遍的な視点を持てるようになるのも、抽象化による思考の成果です。
● 「具体化」と「抽象化」を行き来することが臨床力を育てる
作業療法士に求められるのは、「具体化」と「抽象化」の両方の視点を自在に行き来できる思考力です。
- 具体化によって、その人固有の課題や生活の現実を正確に把握し
- 抽象化によって、経験から学びを引き出し、他の事例にも応用可能な知見へと昇華する
この思考の往復運動こそが、作業療法士としての臨床的判断力や対応力を高めていくための土台になります。
どちらか一方に偏っても、質の高い支援は実現しません。
**「この人の支援にどう活かせるか?」「この経験を今後にどうつなげるか?」**という問いを常に持ち続けることが、専門職としての成長を支える鍵となります。
■ 作業療法における「具体化」と「抽象化」の実践例
| 思考プロセス | 実践の場面 | 内容・効果 |
| 🔍 具体化 | 評価・観察時 | 「腕が上がらない」 →肩屈曲90°以上はB r.StⅣで随意性が乏しく上肢挙上困難 |
| 📋 具体化 | SOAP記録 | 「更衣に困難あり」 →「Tシャツを着るときに右手が届かない」「3分かかる」など、具体的に記述 |
| 🧠 抽象化 | 学びの整理 | 「更衣の自立が目標だったが、本人にとっては“朝の身支度”が一日を始める大切な儀式だった」など、意味づけを行う |
| 📚 抽象化 | 振り返り・発表 | 事例から「支援とは身体機能だけでなく、生活の文脈を理解すること」など、普遍的な教訓を引き出す |
このように、「具体化」と「抽象化」は、作業療法の評価・介入・振り返りのすべてのフェーズで必要不可欠な思考法です。
■ 【まとめ】作業療法士は「見て、考えて、伝える」専門職

| ポイント | 解説 |
| ✅ 具体化は支援の“的を絞る”道具 | 問題の所在や課題の本質が明確になることで、介入の方向性が定まりやすくなる |
| ✅ 抽象化は学びを“広げる”道具 | 実習や臨床経験が「ただの経験」で終わらず、応用可能な知見として蓄積される |
| ✅ 両方を使うことで支援の質が向上 | 評価の精度が上がるだけでなく、報告や記録、説明時の説得力も高まる |
作業療法士は「ただ動作を見て記録する人」ではなく、見た事実を深く考察し、意味を見出し、相手に伝えることができるプロフェッショナルです。
🔚 最後に|「目の前」と「その先」をつなぐ思考を育てよう
臨床や実習では、「目の前のクライアントと丁寧に向き合う力」が最も重要視されます。
しかし、それだけでは一過性の経験で終わってしまいます。
そこから一歩踏み込んで――
- ✅「これはなぜ起きたのか?」「何が課題だったのか?」(具体化)
- ✅「この経験から他に活かせる学びは何か?」(抽象化)
と問い続けることで、あなたの中に“臨床力”と“成長力”が蓄積されていきます。
作業療法士として長く活躍するためには、この“見て・考えて・活かす”という思考の循環を、日々の実践の中で意識して育てていくことが大切です。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。