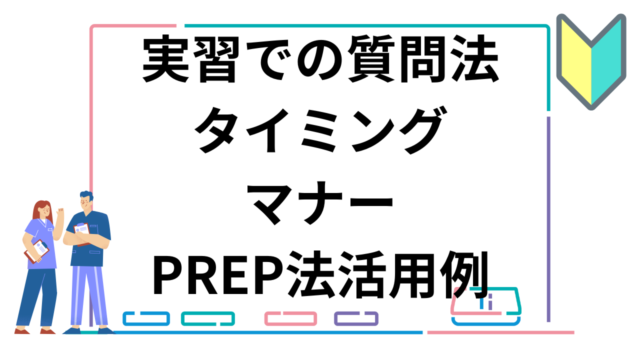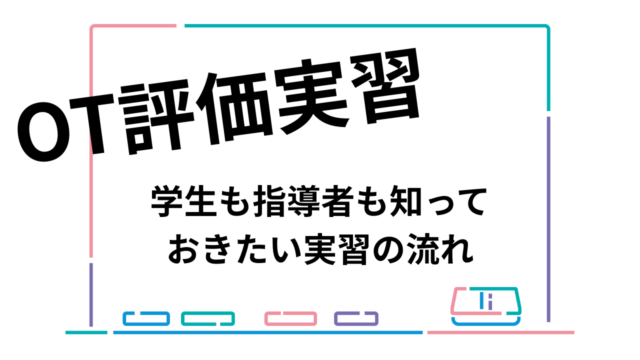作業療法実習における症例発表は、単なる発表の場ではなく、これまでの学びを整理し、臨床で得た情報を第三者にわかりやすく伝える重要な機会です。
指導者や他職種の前で行う発表は、知識や評価スキルだけでなく、情報の取捨選択、構成力、プレゼンテーション能力も問われます。
しかし多くの学生が
- 「何から準備すれば良いのか」
- 「緊張して頭が真っ白にならないか」
と悩みます。
本記事では症例発表の目的理解から資料作成、効果的な練習方法、緊張対策、そして発表後のフィードバック活用まで、成功するためのステップを詳しく解説します。
これを実践することで、発表が“試練”ではなく、自分を成長させる“チャンス”に変わります。
ステップ1:症例発表の目的と重要性

症例発表は、実習で学んだ内容を自分の言葉で整理し、他者と共有する場です。
特に作業療法実習では、単なる報告ではなく
- 「患者理解の深さ」
- 「治療方針の根拠」
- 「臨床推論の過程」
を明確に示す必要があります。
レジュメ作成の目的は以下の通りです。
- 学びの整理:情報をまとめる過程で理解が深まる
- 共有:指導者・他学生・他職種に自分の考えを伝える
- 評価:臨床推論や資料作成能力を客観的に評価してもらえる
特に、OT実習では「どの情報を残し、どの情報を削るか」の判断力が評価されます。
真剣に望んだ実習。得られた情報は全て記載したくなるのはわかります。
ただし、日記ではなくレジュメであり、目的は「実習で何をしたかを伝えること」です。
ステップ2:レジュメ作成の流れ
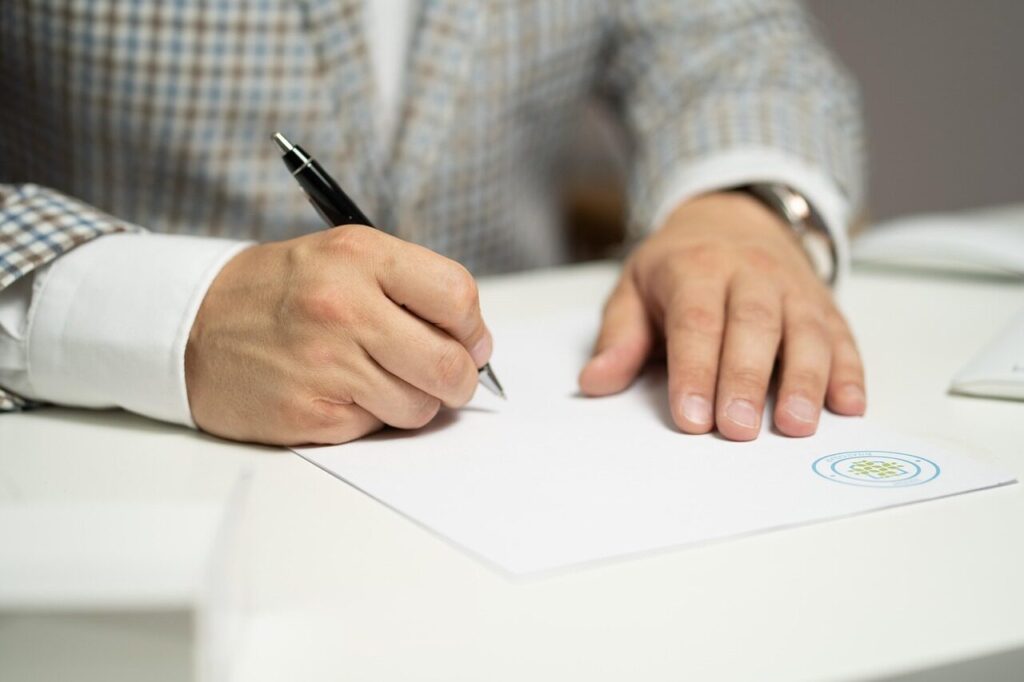
レジュメ作成は以下の順番で進めます。
- 情報収集
カルテ、面接記録、ADL評価表などから必要情報をピックアップ。 - 情報の取捨選択
発表の目的に沿わない情報は省き、重要部分に絞る。 - 構成を決める
基本は「患者概要 → 評価結果 → 問題点 → 治療方針 → 経過 → 考察→展望」。 - 下書き作成
箇条書きや短文でわかりやすく。
筆者はよく色付付箋を使います。考えを出しつつ、書き出したものを入れ替えて手を動かしながら考えを深掘りして整理します。
- 清書・体裁調整
フォント、段落、表・図の配置を整える。
レジュメ構成の例(表)
| 項目 | 内容例 | ポイント |
| 患者概要 | 年齢、性別、診断名、主訴 | 個人情報保護を徹底 |
| 評価内容 | 身体機能、高次脳機能、ADL | 表や図で見やすく |
| 問題点・利点 | 主訴と評価結果から抽出 | 評価内容とズレないように |
| 治療方針 | 介入目標と方法 | 時間・回数・道具も記載 |
| 経過 | 介入による変化 | 数値と具体例で記載 |
| 考察 | 成果と課題 | 次回の改善策も書く |
ステップ3:声に出して読む練習の効果(最低3回)
レジュメが完成したら、必ず声に出して読む練習を行いましょう。
- 最低3回は通して練習
- ストップウォッチで時間を計測
- スマホで録音・動画撮影を行い、自分の癖を確認
- 読み間違いや詰まりやすい箇所を修正
これにより、内容の定着と時間配分の感覚が身につきます。
実際の発表で「なんか読みにくい」「ちょっと詰まってしまった」「時間がない」と焦っているとレジュメを読み上げるのが目的になってしまいます。
結果、よくわからない=頑張ったのに実習評価が得られない
となってしまいます。
事前に繰り返し声に出して読むことで伝わる発表に変えることができます。
ステップ4:発表当日の緊張対策

緊張は誰でもしますが、対策次第で大きく軽減できます。
- 呼吸法:腹式呼吸で落ち着く
- 姿勢:背筋を伸ばし、足を肩幅に開く
- 視線:全体を見渡すように
- 声量:少し大きめを意識
ステップ5:フィードバックの活用法
発表後は必ずフィードバックを受けましょう。
- 指導者や同僚からの指摘をメモ
- 改善点は次の発表やレポート作成に活かす
- 良かった点も把握し、自信につなげる
大抵、発表した際に配ったレジュメに書き込みをしてくれているので、名前を書いてもらって回収するといいでしょう。
そうすることで気になった書き込みについて自分から質問することができます。
そこまでする学生を無視したり、適当に対応する人はいないので、ぜひやってみてください
まとめ(箇条書き)
- レジュメ作成は情報整理力と伝達力を鍛える場
- 構成は「概要 → 評価 → 問題点 → 方針 → 経過 → 考察」が基本
- 声に出す練習は最低3回
- 緊張対策は呼吸・姿勢・視線・声量でカバー
- フィードバックは改善と成長の鍵
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。