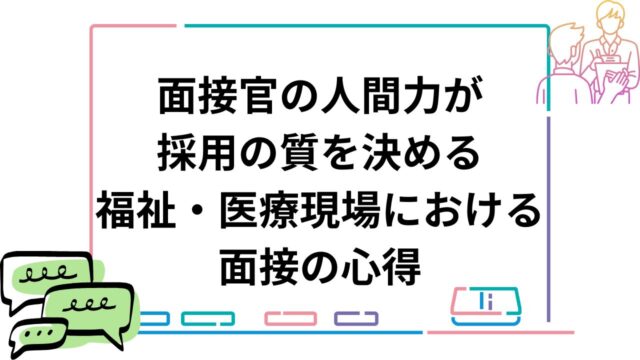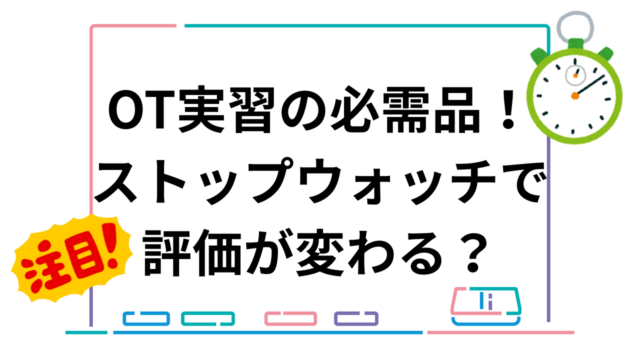作業療法実習では、知識や技術の習得だけでなく、指導者やチームメンバーとのコミュニケーション力も評価の対象になります。
その中でも「質問の仕方」は、あなたの学びへの姿勢や社会人としてのマナーを直接反映する重要なスキルです。
適切なタイミングで、わかりやすく整理された質問ができる学生は、指導者から「この学生は伸びる」と感じてもらいやすくなります。
逆に、唐突で曖昧な質問は「準備不足」「配慮が足りない」という印象を与えてしまうこともあります。
本記事では、作業療法実習で好印象を与える質問の方法を、
- タイミングの見極め方
- 声の掛け方のマナー
- PREP法による質問整理術
の3つの視点から解説します。
さらに、良い質問と悪い質問の実例も比較し、実習中にすぐ実践できる具体的なコツを紹介します。実習評価アップにつながる質問力を身につけましょう。
質問の重要性と好印象の条件
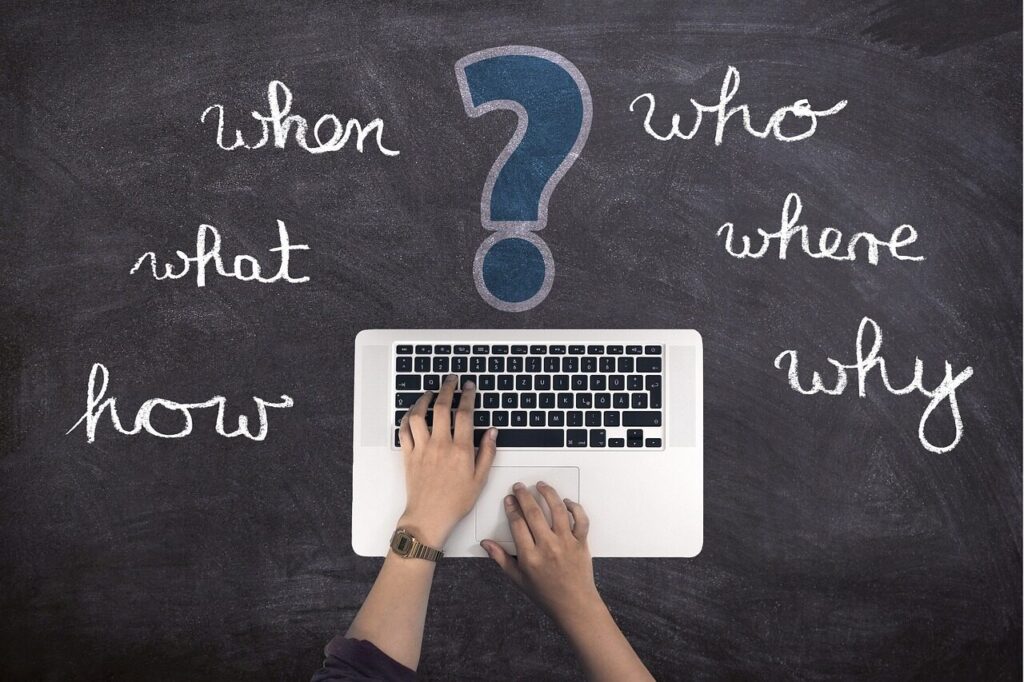
作業療法実習において、質問は単なる情報収集ではなく、指導者との信頼関係構築や学習効率の向上につながる重要な行為です。
質問を上手に行える学生は、「理解しようとする姿勢がある」「主体的に学んでいる」という好印象を与えます。
反対に、準備不足やタイミングの悪い質問は、信頼を損なう場合があります。
好印象を与えるためには、以下の3つが重要です。
- 事前準備:自分で調べたうえで質問する
- 簡潔さ:要点をまとめて短時間で伝える
- 目的の明確化:なぜその質問をするのかを示す
ポイント1: 適切なタイミングの見極め方

質問のタイミングは、相手の状況を観察して見極める必要があります。
以下は、実習現場で質問しても良いタイミングの例です。
- 患者さん対応後の記録時間や休憩時間
- カンファレンス後の振り返り時間
- 移動中や準備中など、指導者が余裕を持っている時
逆に、以下のような状況では質問を避けた方が無難です。
- 患者さん対応中や治療中
- 他職種との重要な打ち合わせ中
- 指導者が明らかに急いでいる時(カンファ前など)
タイミングを間違えると、内容が良くても印象は下がります。
ポイント2:声の掛け方のマナー

質問を始める前に、まずは声の掛け方から意識することが大切です。
作業療法実習では、指導者も患者対応や記録業務で忙しいため、いきなり質問をすると業務の流れを妨げてしまうことがあります。
そこで、質問前のひと言が印象を大きく左右します。
ポイントは以下の通りです。
- 名前を呼ぶ:「〇〇先生、少しお時間よろしいでしょうか」
名前を呼ぶことで、相手に対して敬意と注意を向けていることが伝わります。 - 相手の状況を確認する:「今お忙しいですか?」
「〇〇について3分ほど質問したいのです」
この一言があると、相手は自分の作業を中断するタイミングを判断しやすくなります。
- 感謝を添える:「ありがとうございます、助かります」
「お忙しいのに丁寧にありがとうございました」
質問後に感謝を伝えることで、相手は「協力してよかった」と感じやすくなります。
これらを習慣化すると、質問のたびに相手に配慮した好印象を与えられ、実習全体の人間関係も良好に保ちやすくなります。
ポイント3: PREP法で質問を整理する方法
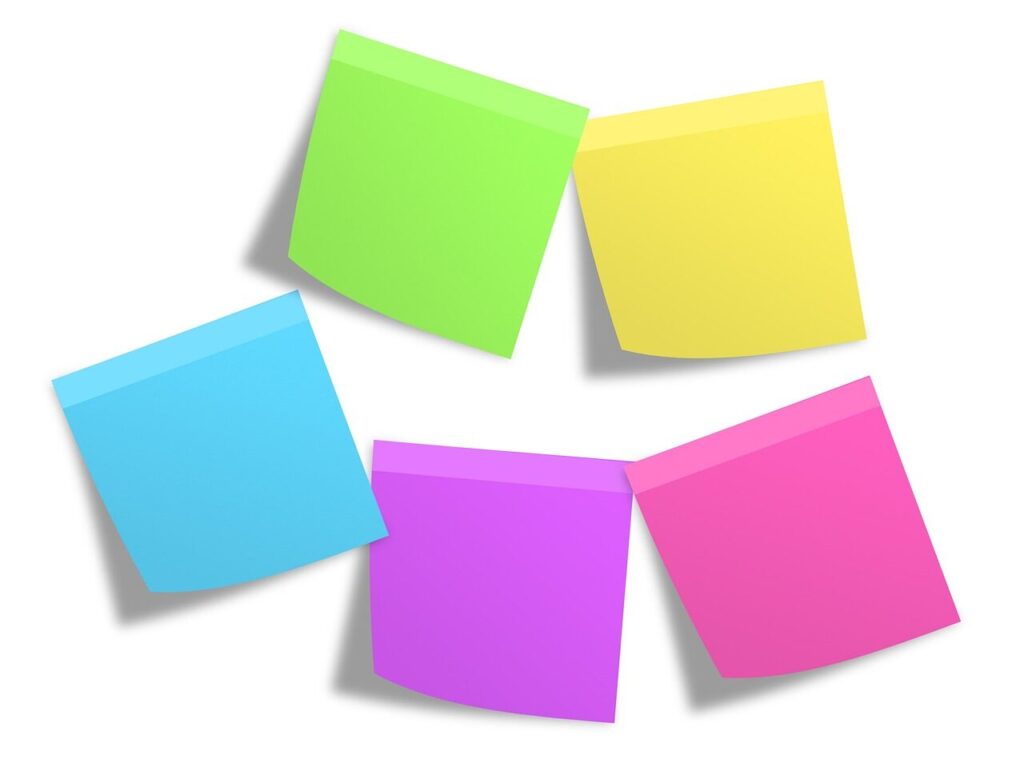
質問の内容は、PREP法を使うと整理しやすくなります。
PREP法とは、以下の順序で話を組み立てる方法です。
| 項目 | 内容 | 例 |
| P(Point) | 結論を先に述べる | 「〇〇について確認したいです」 |
| R(Reason) | 理由を伝える | 「治療計画を立てる際に必要だからです」 |
| E(Example) | 具体例を挙げる | 「患者さんの〇〇場面で…」 |
| P(Point) | 再度結論で締める | 「この場合、どう対応すべきか知りたいです」 |
PREP法を使うことで、質問が冗長にならず、相手が理解しやすくなります。
NGな質問例と改善例
質問の質を高めるために、悪い例と良い例を比較してみましょう。
悪い質問例
- 「これってどうしたらいいですか?」(漠然としている)
- 「昨日のことなんですが…」で話が長く続く(要点不明)
改善例(PREP法)
- Point(結論)
「〇〇さんの食事動作の評価で、〇〇の方法を使っても良いでしょうか?」 - Reason(理由)
「現在の評価方法では、細かい動作の観察が難しく、より正確な把握が必要だと感じています。」 - Example(具体例)
「例えば、スプーン操作や嚥下のタイミングを評価する際に、〇〇の方法を用いると詳細なデータが得られやすいと考えています。」 - Point(再結論)
「そのため、この評価に〇〇の方法を導入してもよいかご相談したいです。」
この形にすると、質問の意図・背景・具体例・結論が明確になり、事前に要点を整理し、相手が答えやすい形なので指導者も回答しやすくなります。
PREP法での質問例

①作業活動の選択
P: 「編み物を作業活動として導入してもよいでしょうか?」
R: 「手指巧緻性と集中力の向上に効果があると考えたためです。」
E: 「〇〇さんは手作業が好きで、既往歴的にも無理のない範囲で実施可能です。」
P: 「導入の適否を教えていただけますか?」
②ADL観察項目の追加
P: 「本日のADL観察に排泄動作を追加してもよろしいでしょうか?」
R: 「現行の評価項目だけでは自立度の把握が不十分なためです。」
E: 「昨夕の移乗時にズボンの上げ下げで一部介助が必要でした。」
P: 「実態把握のため排泄動作も評価対象に含めたいです。」
③歩行訓練の環境変更
P: 「室内歩行から屋外の段差練習へ切り替えてもよろしいでしょうか?」
R: 「環境変化への適応と安全確認が必要だからです。」
E: 「廊下歩行は自立に近い状態で、転倒リスクも低下しています。」
P: 「退院前評価として屋外練習の実施可否を確認したいです。」
④更衣訓練の衣服調整
P: 「更衣訓練でボタンの大きいシャツに変更してもよろしいでしょうか?」
R: 「巧緻性の負担を軽減し、成功体験を積むためです。」
E: 「昨日の訓練では細いボタンで時間超過し、疲労が強く出ました。」
P: 「段階付けの一環として衣服の難易度を下げたいです。」
⑤家庭復帰に向けたIADL評価
P: 「調理動作評価を追加してもよろしいでしょうか?」
R: 「自宅復帰後の生活に直結し、本人の希望にも合致するためです。」
E: 「面談で『退院後は簡単な料理をしたい』と意欲を示されました。」
P: 「退院支援計画に反映するため評価追加の可否を伺います。」
実際の実習場面でもPREP法を意識して指導者に質問をしてみましょう。
まとめ
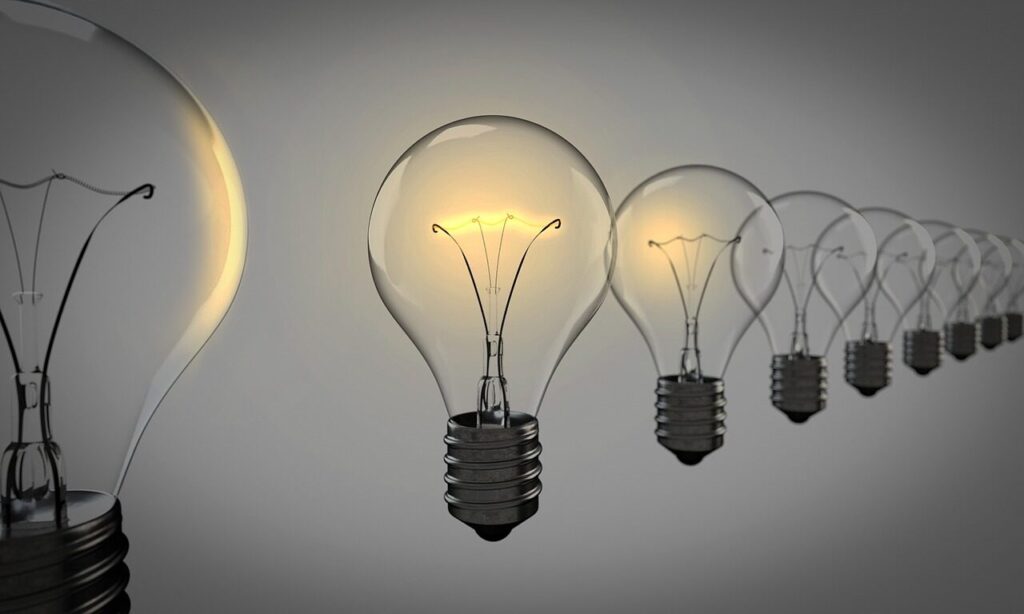
実習中の質問は、ただ答えを得るためではなく、自分の成長の加速装置として活用すべきです。
そのためには以下のポイントを意識しましょう。
- 適切なタイミングで行う
- 声の掛け方や礼儀を守る
- PREP法で簡潔にまとめる(具体的かつ目的のある質問にする)
指導者の方が医師に声をかけるタイミングや治療の考えを話す時の様子もみていて勉強になるかもしれません。
これらを実践することで、指導者からの信頼を得られ、実習の学びが深まります。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。