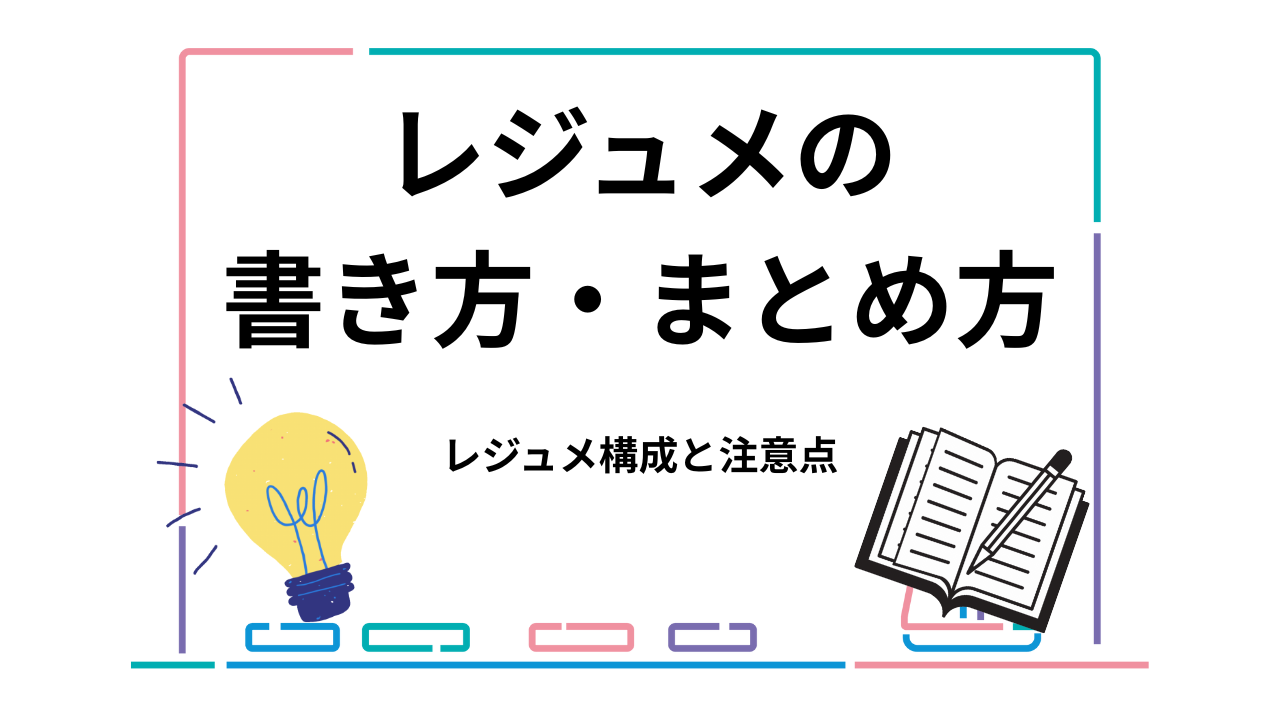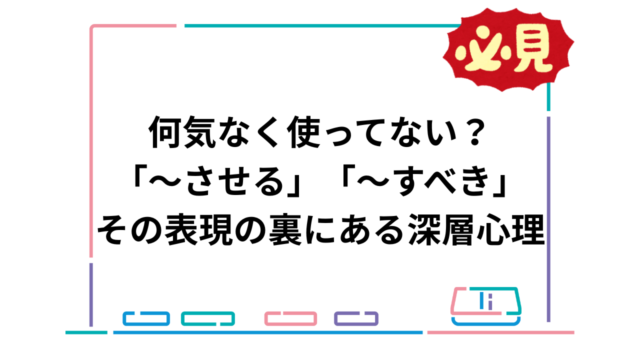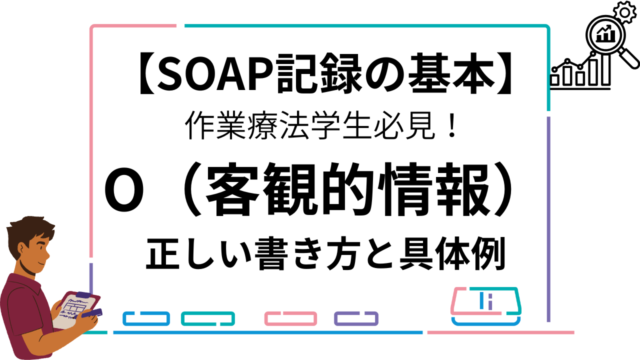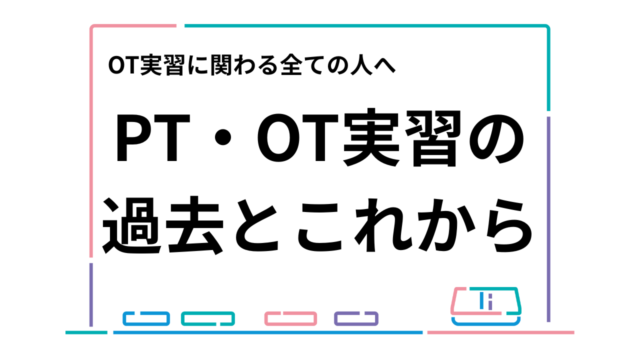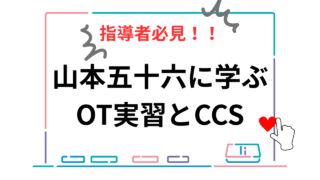🎯 作業療法実習レジュメの役割とは?

作業療法(OT)実習において、実習レジュメは単なる報告書ではなく、「学びと成長を見える化」するための重要なツールです。評価から介入、振り返りまでのプロセスを一貫して記録・整理することで、自身の臨床思考を深め、実習の成果を最大化できます。
このレジュメをしっかりと書き込むことで、以下のような作業療法士として必要な力が自然と養われていきます
- 臨床推論力:患者の状態を的確に分析し、根拠ある介入を考える力
- 記録力:変化や根拠を明確に言語化し、伝える力
- 表現力:自分の考えを論理的かつ分かりやすくまとめる力
作業療法実習レジュメは、学生自身が「どのように考え、行動し、学んだか」を形にすることで、将来の臨床力の土台となる貴重な記録となります。本記事では、効果的なレジュメの書き方や構成、活用のポイントを詳しく解説します。
🧩 実習レジュメが大切な理由とは?
作業療法の臨床実習は、「評価→目標設定→介入→振り返り」のサイクルを繰り返す学びの場です。
このプロセスをきちんと整理・記録し、思考の軌跡を見える形にすることで、実習経験が「点」ではなく「線」としてつながり、深い学びにつながります。
また、レジュメは自分のためだけでなく、指導者とのフィードバックや他の学生との情報共有の場で活用されます。見やすく、筋道立てて記述されたレジュメは、信頼される学生の証ともいえるでしょう。
📘【作業療法実習レジュメ】構成と書き方のポイント

| 項目 | 内容 | 書き方のポイント |
| 1. タイトル | レジュメの表紙部分(氏名、学籍番号、実習先など) | 読みやすく整え、提出書類としての形式を意識 |
| 2. はじめに(実習目的) | レジュメで伝えたい思い実習を通して達成したい目標 | 実習でクライアントと出会い、ともに体験した「大切な作業」をどういったプロセスで考え、進めたかを具体的かつ簡潔に記述 |
| 3. クライアントの概要 | ・基本的情報・医学的情報・社会的情報・他部門情報 | 左記の「情報」だけでなく、クライアントの生活背景、本人の希望も重視することでクライアントの人物像が読み手に思い浮かぶように意識。 |
| 4. 評価内容 | ・身体機能(ROMなど)・高次脳機能(MMSEなど)・日常生活動作(FIMなど) | 実施した評価をレジュメで必要なものに厳選することを意識し、この後の考察やプログラム立案に根拠と具体性を持たせる |
| 5. 介入計画 | ・短期・長期目標・作業活動の選定理由や環境設定など | 作業療法士らしく“作業中心”の視点を忘れずに |
| 6. 統合と解釈(考察) | ・どういったクライアントにどんな目的で何をしたか・その結果、どんな効果や変化があったか・なぜ、そうなったと考えるのか | 単なる出来事の羅列でなく、「なぜそうなったか」の深掘りを意識する。うまくいかなかったとしても「それはなぜか」「どうするとよかったか」「何がわかったか」を分析すると良い |
| 7. 今後の展望 | 実習後の「クライアントの人生」がどのように変化していくと良いか | 実習後のクライアントの人生がどのように変化していくと良いか。感謝の気持ちで書いていく |
| 8. 参考文献(余白があるならばで構わない) | 使用した教科書や論文など | 信頼性のある文献を明記し、根拠を示す |
✨ 書き方のコツと注意点

作業療法実習レジュメを書くときに意識したいのは、「誰が読んでも伝わる内容になっているかどうか」です。特に学生や実習初心者の方は、以下のポイントを押さえることで、より質の高いレジュメが作成できます。
1.一貫性を意識する
評価 → 介入計画 → 実施 → 振り返りという一連の流れが、論理的につながっているかを確認しましょう。内容が飛んでいたり、関係のない情報が混ざっていたりすると、読み手は混乱しやすくなります。一貫性のあるレジュメは、「なぜこの介入を選んだのか」「どう考えて行動したのか」が伝わりやすく、評価にも好影響を与えます。文章をつなぐ言葉(例:「その結果」「このため」「一方で」など)をうまく使うと、流れがスムーズになります。
2.専門用語は正しく、簡潔に使う
専門用語を無理に使おうとすると、誤用や曖昧な表現になってしまうことがあります。用語の意味や使い方をきちんと理解した上で、適切に使うよう心がけましょう。また、相手に伝わるようにするために、必要であれば用語の後に簡単な説明を加えるのも有効です。たとえば「ADL(日常生活動作)」といったように略語と意味を併記することで、読む人の理解を助けます。
3.「作業療法士の視点」を忘れない
レジュメは単なるリハビリの記録ではありません。作業療法の本質は「作業を通じて、対象者の生活と人生に寄り添うこと」です。つまり、単に関節可動域が広がった、歩行距離が伸びたといった身体的な変化だけではなく、その人が「やりたいこと」や「大切にしていること」が実現できるよう支援しているか、という視点が大切です。評価や介入計画の中で、その人らしさや生活背景に目を向けた内容を含めるようにしましょう。
4.指導者や第三者の目線で見直す
自分では完璧に書けたつもりでも、第三者が読んだときに意味が通じない場合があります。書き終えたレジュメは、客観的な目線で見直すことが重要です。「この文章は誰が読んでも伝わるか?」「略語や専門用語の説明は必要か?」といった視点で再チェックし、可能であれば指導者や仲間にフィードバックをもらいましょう。
5.過程を重視し、失敗も記録する
成功したことだけでなく、失敗したことやうまくいかなかった場面も大切な学びの材料です。「なぜ失敗したのか」「何が不足していたのか」を振り返ることで、次の実践に活かせます。レジュメは成果だけを書くものではなく、「どのように考え、どう行動したか」を記録することが目的です。結果以上に、そこに至るプロセスに価値があるという意識で書いてみましょう。
6.簡潔でわかりやすい文章を心がける
難しい表現や長すぎる文章は、読む人を疲れさせてしまいます。1文が長くなりすぎないように注意し、文の区切りや言い回しにも気を配りましょう。とくに実習レジュメは、指導者や他の学生が読むこともあるため、「伝わる文章」を意識して書くことが大切です。「誰にとっても読みやすい文章」を目指すことが、結果的に自分の理解の深まりにもつながります。
📝 まとめ|レジュメは“成長の記録”
作業療法実習のレジュメは、「自分の成長を可視化するツール」であり、「伝える力を育てる訓練」でもあります。
患者理解の深まり、自分の思考の整理、他者との共有といった多くの目的が込められているこのレジュメを、単なる“義務”で終わらせてはいけません。
✅ レジュメ作成で身につくこと:
- 臨床での観察力・判断力
- 論理的思考と記述力
- チーム医療に必要な伝達力
🔚 最後に|伝える・伝わるレジュメで成長を加速させよう

良いレジュメは、単なる「まとめ」ではなく、「臨床家としての成長記録」です。あなた自身が臨床家としてどんなことを考え、どんなふうに悩み、どんな工夫をしながら目の前の患者さんと向き合ってきたか。その歩みを言葉にした「成長の記録」です。
「自分のやっていることが正しいのか」
「うまくいっているのか」
不安になることもあるでしょう。
それでも、あなたが毎日考えたこと、感じたこと、悩んだこと、工夫したことを丁寧にレジュメに書き留めることで、その一つひとつが自分の“軸”になっていきます。
レジュメは提出するための“書類”ではなく、自分の内側を見つめ、次の一歩を見つけるための“ツール”です。
また、上手に書こうとしすぎる必要はありません。大切なのは、「あなたが何を感じ、何を考え、どう動いたのか」を自分の言葉で伝えること。
あなたのレジュメは、いずれ未来のあなた自身が読み返し、「この頃の自分もがんばっていたな」と思えるような、かけがえのない記録になります。
あなたのレジュメが、未来のあなたを支える“地図”になるように。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。