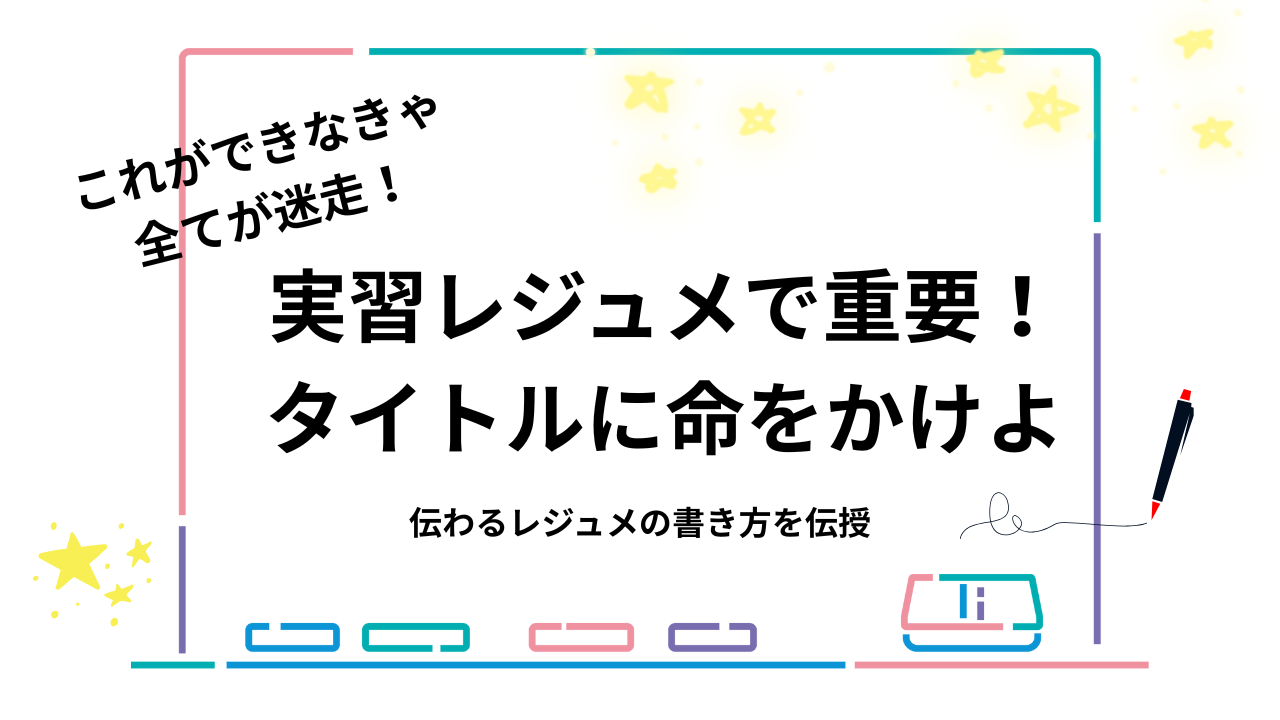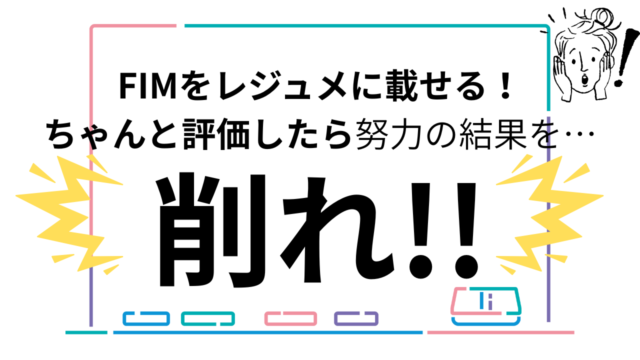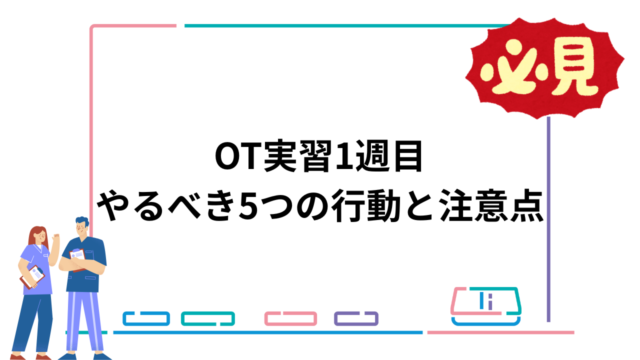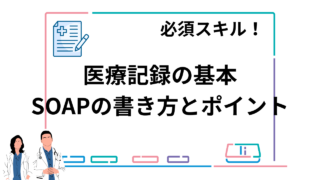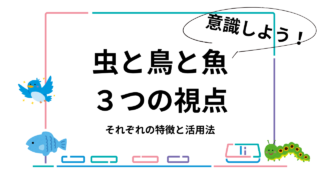レジュメの書き方、間違っていませんか?“タイトル”が与える第一印象の力とは
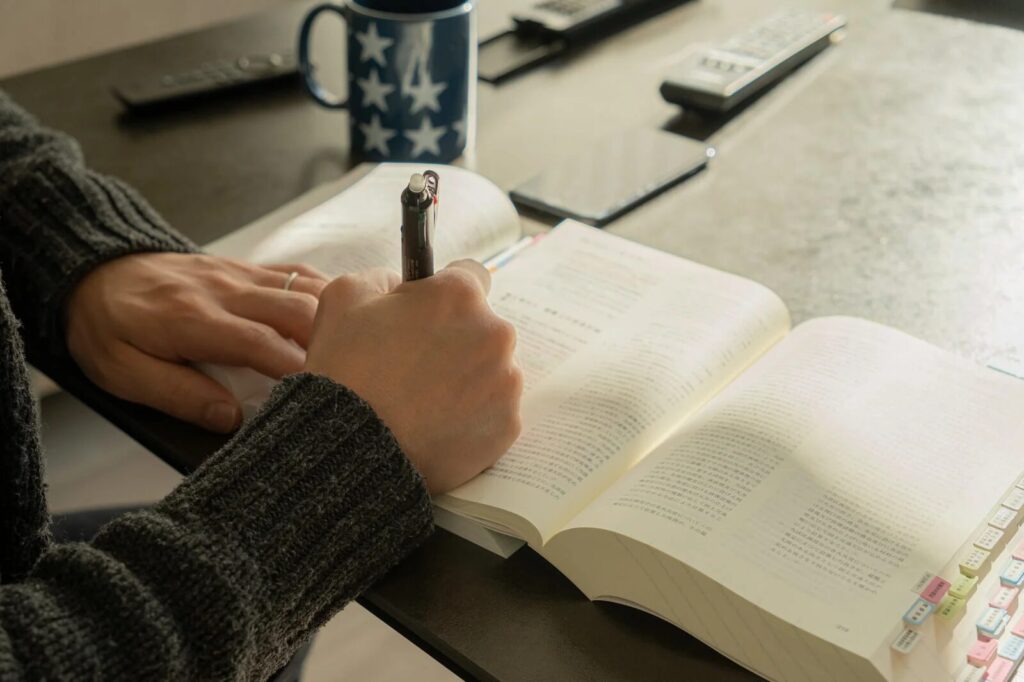
「実習でレジュメを書いたけれど、指導者から“もっと伝わるように書こう”とフィードバックを受けた」
「頑張って内容をまとめたのに、読んでもらえていないような気がする…」
そんな経験はありませんか?
作業療法士や理学療法士をはじめとする医療・福祉系の学生が避けて通れないのが実習の集大成として作成する“実習記録(レジュメ)”。
レジュメを書く際、多くの学生が最初に見落としがちなのが「タイトル(表題)」。
実は、この“たった一行”が、実習記録全体の印象や、読まれるかどうかを左右する非常に重要な要素で読み手の心を動かす力があります。タイトルは、単なる記録の名前ではなく、“読むきっかけ”であり、“内容の本質”を凝縮したメッセージなのです。
読み手である教員や実習指導者、時には多職種連携の医療スタッフ、学生ならば友人たちに、「この事例は読んでみたい」と思わせることができるかどうか。それは、タイトルの一文にかかっていると言っても過言ではありません。
表題は、いわばキャッチコピーのようなものであり、直感的に興味を引くトリガーでもあります。読まれる実習記録を作るためには、「読み手の目線に立つこと」が重要です。どんなに丁寧に記録しても、タイトルが魅力的でなければ最初の1行でスルーされてしまうこともあるのです。
タイトルは“読まれるレポート”の鍵!キャッチコピー的役割を果たす
レジュメのタイトルは、ただの見出しではありません。
- 読者(指導者・教員・他職種)に「この記録、面白そう」「気になるな」と思わせる力
- レポート全体の核となるテーマを伝えるシグナル
- 読む前から“期待”を生む導入部分
つまり、タイトルとは「読みたくなる直感のトリガー」であり、キャッチコピーのような存在なのです。
良いタイトルは、読む人の注意を引きつけ、内容を自然に読み進めさせてくれる“扉”になります。
【比較実例】タイトルだけで印象がここまで変わる!

✴️ 事実をそのまま表したタイトル(よくあるパターン)
- 80代男性、脳梗塞後の左片麻痺における更衣動作の支援
- 脳性麻痺による歩行不安定な児童への買物自立支援の取り組み
このようなタイトルは、情報としての正確性はあるものの、読み手の関心を惹く力は弱く、少し味気なく感じられることも多いです。
✴️ 物語性・感情訴求を取り入れたタイトル(印象に残るパターン)
- 「自分で着替えて良い一日を迎えたい」朝の身支度を通じて自分らしい生活を取り戻した“ダンディなおじいさん”との出会い
- 「歩けなくてもいい」買い物を楽しむ体験から希望を見つけた“オシャレ女子”の物語
いかがでしょうか?
前者の事実型は、客観的な事実を淡々と述べているだけで、あまり読み手の心には響きません。
一方で後者は、対象者の気持ちや背景、その体験の意味づけまでが感じ取れる表現になっており、読者の感情に訴えかけてきます。
「物語性」や「感情の訴求」は、単に美辞麗句で飾るためのものではなく、「その人らしさ」や「作業の意味」を浮き彫りにするための大切な表現なのです。
このように、ストーリー性や感情に訴えかける言葉を使うと、記録が“人の人生”として伝わりやすくなります。
読まれるレポートに共通するのは、単なる事実ではなく「心が動く表現」があることです。
なぜ“タイトル”が重要なのか?レジュメの本質を考える
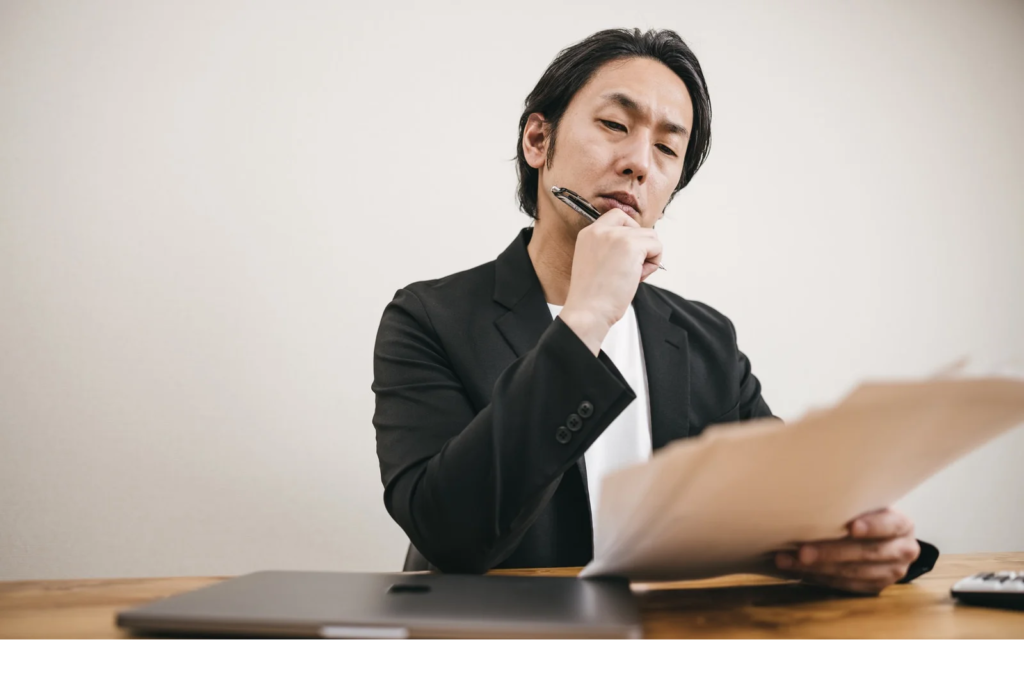
実習とは、クライアントの人生に触れ、支援を通じて自らの成長を深める場。クライアントとの真摯な関わりの中で、自分自身が得た気づきや学びを形にする経験です。そして、そのレジュメは、協力してくれたクライアントへの恩返しの意味も込められています。
- 感じたこと:その人に接する中で、自分が心を動かされた瞬間や気づいた点
- 学んだこと:評価や介入を通じて、専門職としてどんな知識や態度が身についたか
- 実施したこと:具体的な支援内容、観察、記録、計画、実践など
- 成長したこと:この経験を通じて、自分自身の専門性や人間性がどう深まったか
これらをこれらのすべてを、「伝わるように」言葉にするには、まずタイトルから始める必要があります。タイトルが明確になれば、自ずと何をどう伝えるべきかも整理されてくるのです。
タイトルが果たす役割は決して小さくありません。タイトルとは、「学びを恩返しするための第一歩」でもあるのです。
タイトルが記録全体の“焦点”を明確にする|情報整理のツールにも
印象的なタイトルは、単に読みたくさせるだけでなく、レポート全体の構成を整えるヒントにもなります。
たとえば…
✅ 例1:『「自分で着替えて良い一日を迎えたい」朝の身支度を通じて自分らしい生活を取り戻した“ダンディなおじいさん”との出会い』

タイトルから、「朝の身支度=更衣動作」が中心課題であることが明確になります。
<評価すべきポイント>
- 身体領域:上肢や下肢の随意運動、麻痺の程度、バランス能力
- 高次脳機能:注意障害、失行、構成障害など
- ADL:更衣・整容の自立度、習慣形成、生活リズムの再構築
- 不要な情報:入浴や食事動作など、中心課題に直結しない内容は省いてもOK
✅ 例2:『「歩けなくてもいい」買い物を楽しむ体験から希望を見つけた“オシャレ女子”の物語』

「買い物を通した自立支援」が中心テーマと読み取れます。
<評価すべきポイント>
- 身体領域:歩行能力、上肢機能、スタミナ(耐久性)
- 高次脳機能:金銭管理、意思決定、遂行機能
- ADL:外出、買い物、公共交通の利用など
- 不要な情報:排泄や就寝など、課題と関係ない情報は省略可能
このように、タイトルを決めることで「必要な観察項目」「記述すべき内容」が明確になり、
結果的に内容の質も高まり、レジュメ作成の効率も上がるのです。
【書き方のコツ】“伝わるタイトル”をつける3つの視点

魅力的なタイトルは、記録全体の設計図のような役割を果たします。
以下のポイントに注目しながら、逆算的に記録を作成していきましょう:
- 何を中心に書くか(=中心作業)
- 食事、入浴、更衣、移動、買い物、学習活動など、実習で焦点を当てた「クライアントの人生で大切な作業」は何か?
- 誰にとってどんな意味があるのか(=物語性)
- その作業がクライアントの生活や人生にどんな意味を持っていたか?
- 喜びや悩み、希望や不安といった感情とつながるエピソードは何か?
- どこまでの評価・観察が必要か(=情報の絞り込み)
- 必要最低限の評価に集中することで、記録の質が高まり、時間の効率も上がります。
タイトルを磨くことは、伝える力・対話力を磨くこと

レジュメ作成は、「伝える力」「共感力」「観察力」を同時に鍛えるトレーニングでもあるのです。
実習を通じて得た経験は、自分だけの財産であると同時に、その体験を提供してくれたクライアントの“人生の一部”でもあります。だからこそ、その物語を尊重し、心を込めて「伝える」ことが、医療専門職を目指す私たちに求められる重要なスキルなのです。
タイトルに込める想いは、単なる表現の工夫ではなく、「この人の経験を多くの人に伝えたい」「この出来事が、学びのきっかけになってほしい」という姿勢の表れです。医療・福祉分野で働くということは、「情報を適切に伝える力」が求められる場面が非常に多くあります。
クライアント・家族・他職種との連携においても、“伝わる言葉”は必須スキルです。読み手に伝わる表現力、共感を呼ぶ文章力、そして“読む価値のあるレジュメ”をつくるためのスタートラインとして、タイトルにもう一度しっかり向き合ってみましょう。
まとめ|“タイトル”でレジュメの質は変わる!あなたの実習経験にタイトルをつけよう
| 項目 | 意義 |
| タイトルの目的 | 読みたくさせる、レジュメの意図を明示する |
| 良い表題の効果 | 読者を惹きつけ、レジュメの焦点を明確にする |
| 書き方のポイント | 感情・物語性・意味づけを簡潔に |
| タイトルが与える影響 | 必要な情報を選択しやすくなる(評価・観察・治療プログラム) |
📣 最後に|“物語のタイトル”をつけるつもりで
あなたの実習経験には、唯一無二の物語があります。
その経験をどう表現するかによって、読み手の印象も、自分自身の理解も、大きく変わります。
さあ、ただの報告書をやめて、“伝わる物語”を綴りましょう。
「この人の経験をもっと知りたい!」と思われる表題を、あなた自身の言葉で考えてみてください。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。