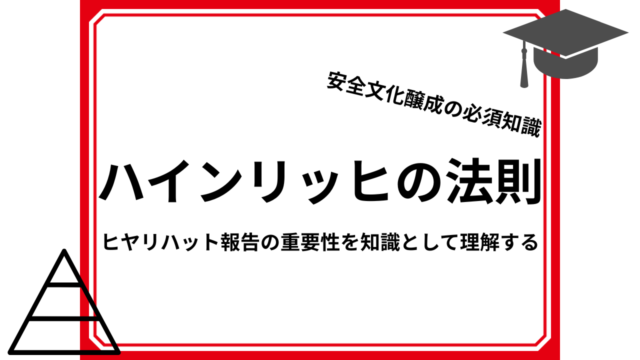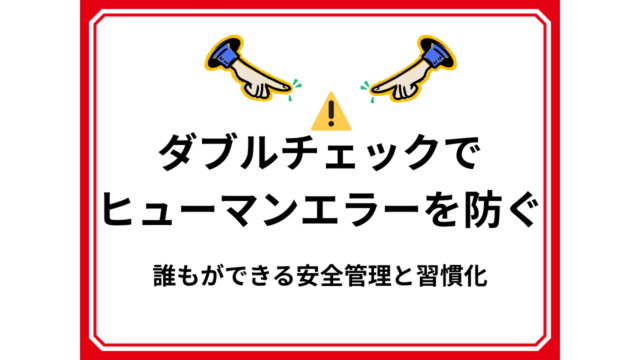医療安全におけるヒヤリハットやインシデント、事故報告書の質は、再発防止と組織学習のレベルを左右します。
中でも重要なのが、「事実」と「対策(考え・意見・感想)」を明確に分けて記述すること。
事実に推測や感情が混じると、誤解が生まれ、原因分析や是正措置がぶれてしまいます。
本記事では、現場で誰でもすぐに使える「事実・対策分類シート」を使った練習法と、ヒヤリハット・事故報告の書き方を、良い例・悪い例を交えてわかりやすく解説。
新人教育や多職種連携の標準化、医療・介護・福祉の現場改善に役立つ情報を発信します。
報告書の「読みやすさ」と「再発防止効果」を同時に高め、今日から使える安全文化づくりを後押しします。
医療安全と「事実・対策」を分ける意味
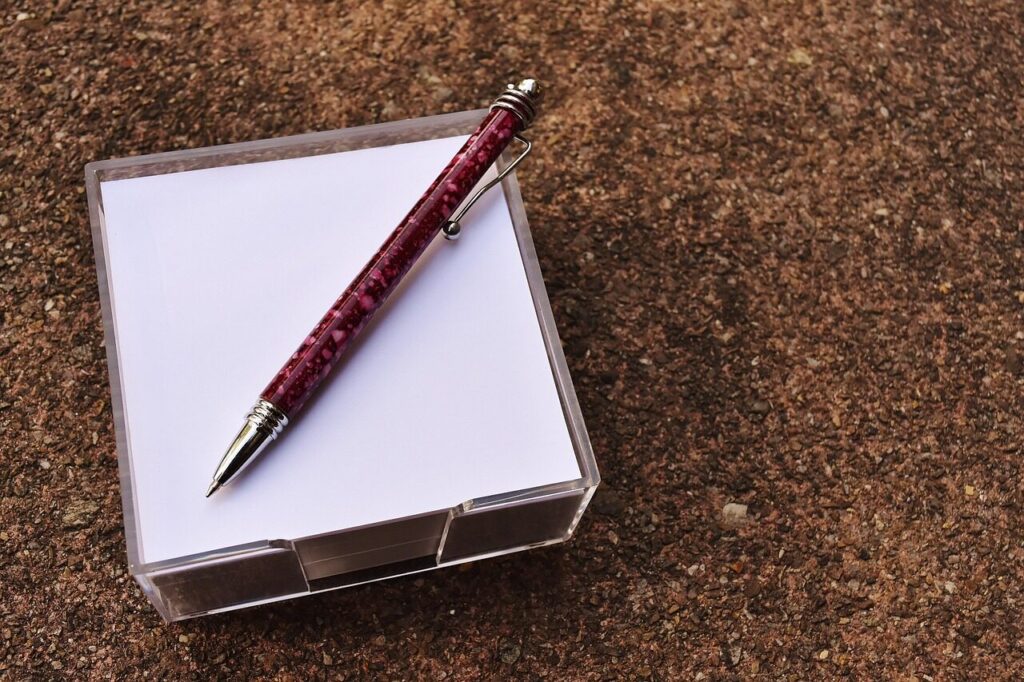
医療安全の現場では、ヒヤリハットやインシデントを正確に記録・共有し、再発防止へつなげることが最重要です。
そこで鍵となるのが次の2つを切り分けて記述することです。
- 事実(誰もが否定できない出来事)
- 対策(意見・判断・改善案)
事実と対策を混在させると、原因分析が曖昧になり、効果の弱い対策が採用されがちです。
逆に、事実を時系列で正確に並べ、原因と影響を見える化すれば、多職種でも同じ議論ができ、標準化と再発防止が加速します。
基礎練習:例文で事実と考えを見分ける
問題集のルール
「事実=誰もが疑いようのないこと」
「対策=考え・意見・感想」
- Q1. 猫は可愛い → 多くの場合考え(主観)
- Q2. 1日は24時間 → 事実(一般的な定義)
- Q3. 日本は島国 → 事実(地理的定義)
- Q4. カレーは美味しい → 考え(嗜好)
- Q5. コーヒーは苦い飲み物 → 考え
以下、例題を多数挙げます。
- 東京は日本の首都である(事実)
- 東京は住みやすい都市である(考え)
- 犬は哺乳類である(事実)
- 海水は塩分を含む(事実)
- 火は酸素がないと燃えない(事実)
- 牛乳は体にいい(考え)
- 北海道は寒すぎる(考え)
- 雨は水滴が空から落ちる現象である(事実)
- 映画館は楽しい場所(考え)
- 和食は世界一おいしい料理(考え)
- 北極には氷がある(事実)
- クジラは哺乳類(事実)
- 地球は太陽系に属している(事実)
- 夏はアイスが一番美味しい(考え)
- 血液は赤い(事実)
- 朝は早く起きた方が得(考え)
- 魚はエラで呼吸する(事実)
- ハワイは太平洋にある(事実)
- 植物は光合成を行う(事実)
- 朝はパンよりご飯が良い(考え)
やってみると「なんてことないな」と感じるかもしれませんが、何百ものヒヤリハットや事故報告をみてきた経験からすると、文章になった瞬間に事実と考えが入り混じってしまうのが人間のクセのようです。
事故の例で学ぶ:事実と対策を分けて書く実践

例文(インシデント)
「車椅子車両の固定操作研修を受けていない状態で指導も受けずに帰りの送迎で、車椅子利用者の車両固定を担当したスタッフAは、指差し呼称・ダブルチェックを行わず会話しながら作業。走行後、利用者から『揺れている』との訴えがあり、添乗スタッフCが確認したところ固定ボタンが未押下で、フックのみ掛かった状態だった。」
事実(赤)
- 帰りの送迎で車椅子固定をAが担当
- 指差し呼称・ダブルチェックを実施せず
- 会話しながら作業
- 走行後、利用者が「揺れている」と訴え
- Cが確認 → 固定ボタン未押下、フックのみ掛かっていた
対策(青)
- 固定前の指差し呼称の必須化
- ダブルチェックの標準手順化(担当・タイミング明記)
- 会話禁止の作業区域設定
- 固定前・発進前チェックリスト導入
- 新人向け再教育・監査の実施
良いヒヤリハット事例(完成イメージ)
- 事実:2025年8月10日 16:05、事業所前にて送迎車両出発直後、利用者より「揺れている」と訴え。停車後に固定具を確認したところ、左後輪側の固定ボタン未押下、フックのみ掛かりを確認。担当Aが固定作業、Cが添乗。
- 影響:転倒などの健康被害は認めず。
- 対策:固定前の指差し呼称徹底、Cによる発進前ダブルチェックを標準手順化。チェックリストを8/15から運用開始。A・Cは8/12に再教育受講。責任者:安全管理担当B。
→ 事実と対策が分離され、日時・場所・人・機器・行為が明確。第三者が読んでも同じ理解に到達できます。
悪いヒヤリハット事例(どこが良くない?)
- 事実:忙しくてみんな焦っていたため、車椅子の固定が甘くなった。Aさんも注意力が散漫で、Cさんもちゃんと見ていなかった。
- 影響:特に問題はなかったが、ヒヤッとした。
- 対策:今後は気をつける。
問題点
- 主観・推測・評価語が多く、事実が不明
- 日時・場所・機器状態・確認手順が抜けている
- 再発防止に結びつかない
改善ポイント
- 事実を時系列で具体化
- 対策は責任者・期限・手順化まで落とし込む
共有と振り返り:多職種で活用する運用ポイント
- テンプレート化:報告書の章立てを「①事実(時系列)②影響③対策(優先度・担当・期限)④フォロー」で統一
- 朝礼・カンファレンスでの共有:週1回、3分で読める要約を共有し、関連部署のToDoへ反映
- 学習ループ:実施した対策の効果測定(監査、指標、監視表)を1か月後に確認。効果が弱ければ対策を更新
- 新人教育:オリエンテーションで分類シートを使ったロールプレイを導入。採用後1か月で再評価
まとめ:自己分析→標準化→再発防止へ

事実と考えを見分ける力は、情報を正しく理解し、判断力を高めるための基礎です。
私たちは日々、多くの情報に触れていますが、その中には事実と意見が入り混じっています。
見分ける力があれば、情報に流されず、自分の頭で判断できるようになります。
今回の問題集を活用し、普段から「これは事実か、意見か」を意識して訓練することで、思考が整理され、事故やヒヤリハットに対して必要な情報収集や論理的な議論の第一歩を踏み出せます。
この練習は医療福祉の業界で必須スキルであり、その知識と技術を確実に身につけることが重要です
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。