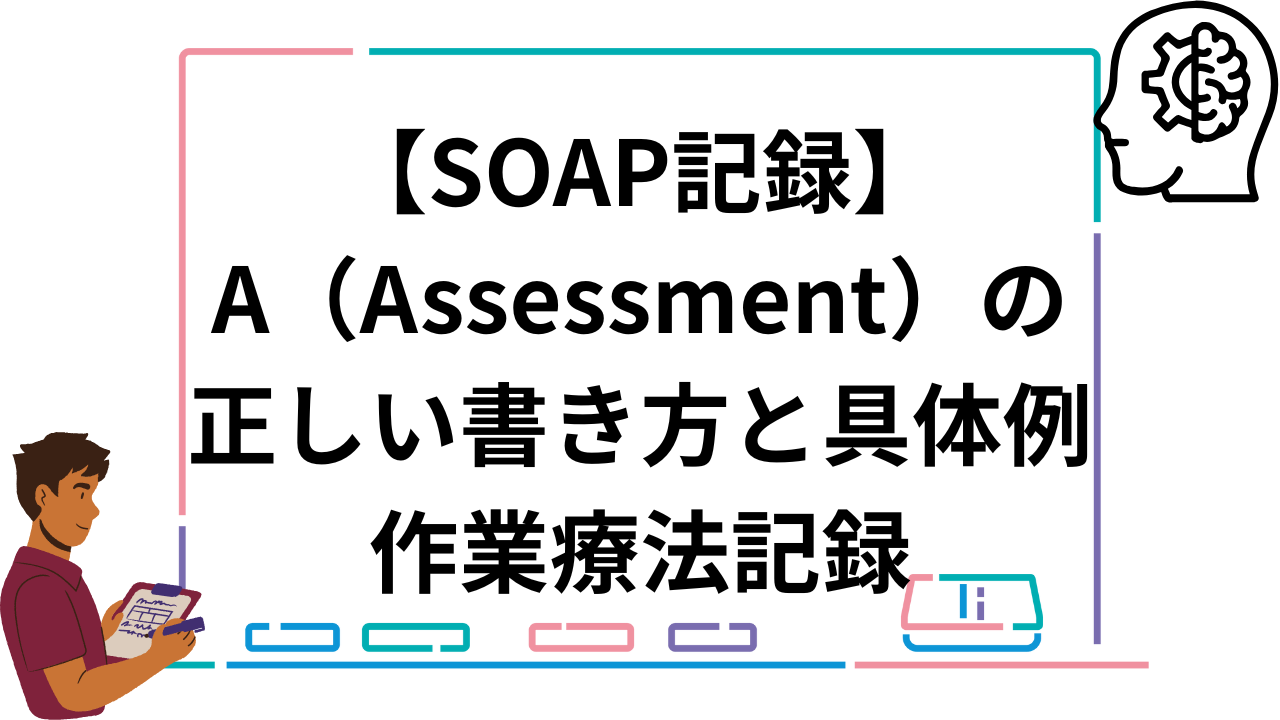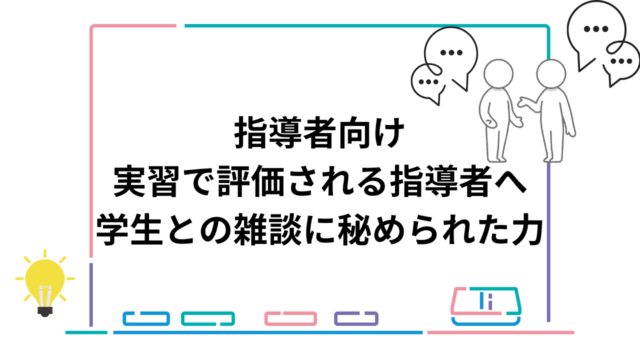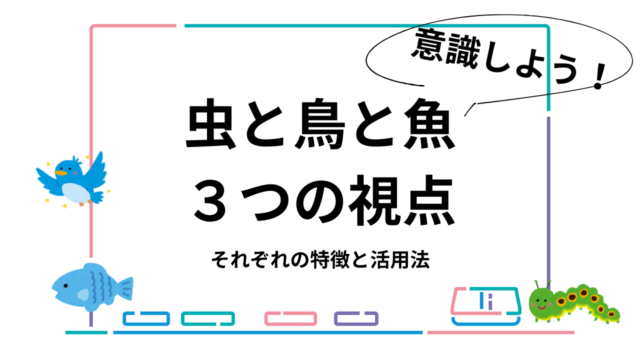作業療法実習で使われる記録形式が SOAP 。
その中でも「A(Assessment:評価)」は、学生が最も戸惑いやすい部分です。
なぜなら「事実を記録するSやO」と違い、Aは「そこからどう考えるか」を書く必要があるからです。
つまり、A(Assessment:評価)は単なるまとめではなく、患者さんの状態を踏まえて臨床的に解釈する力が求められます。
具体的にAに含まれる内容は以下の通りです。
- SやOから得られた情報の意味づけ
(例:歩行距離が100m延びた → 体力が改善している可能性) - 患者の強みや課題の整理
(例:右手の巧緻性は保たれているが、持久力が低下している) - 治療や訓練の方向性の示唆
(例:移動手段や方法は自立レベルだが金銭管理など自己管理能力の強化が必要)
Aは「次のP(Plan)」に直結するため、単なる観察の羅列では不十分です。
重要なのは、SやOをもとに「作業療法士としての臨床的な見方」を示すこと。
学生のうちは「評価=正解を書くこと」と思いがちですが、実際は「考えた過程を示すこと」が大切で指導者はそういったプロセスが文章として記載できているかを見ています。
教科書や参考書から導き出されるテストの答えではなく、自分の考えを相手に伝える情報処理の訓練の場にしたいのです。
この記事を通して、あなたの考えを伝わるように伝えてみましょう
SOAP記録とは?まずはおさらい: 4つの基本要素
ここからは一般的なSOAP記録について記事にしていきます。
臨床現場で患者さんの状態を整理・共有するための記録方法がSOAP。
以下の4つの要素から構成されます。
- S(Subjective):主観的情報
患者さんが感じている症状や思い、訴えなど。 - O(Objective):客観的情報
バイタルサインや検査結果、観察所見など、測定可能で客観的に確認できる情報。 - A(Assessment):評価
SとOを踏まえて、臨床家が状況をどう解釈するか。 - P(Plan):計画
今後の治療方針、介入内容、指導計画など。
この中でもAはその前に見出された患者さんからの情報(S:主観的情報)と実施して得られた医療・リハビリの根拠(O:客観的情報)を分析、考察、解釈する作業療法士の知識量が試される場所です。
どんなことを記載すればいいのか?概要
SOAPのAは Assessment の略で SとOを材料にして作業療法士として下す評価や解釈を言語化する部分。
事実の写し取りではなく 事実に意味を与える工程です。
患者さんの訴え(S)や測定値(O)を統合し、
- 何が起きているのか
- なぜ起きているのか
- 生活にどう影響しているのか
を推論します。
ここで示した見立てがPの方向性や優先順位の根拠になります。
< 例 >
S:早くトイレに一人で行ける様になりたい
O:トイレ動作は自立レベルだが、トイレ移乗は麻痺側のステップがうまくできず2回に1回は方向転換に触れる程度の介助を要する
上記の記録があればトイレへの意欲はあり、立位保持もある程度安定しているが「方向転換」という内乱を伴うバランス保持に困難さがあり、転倒リスクから自立に至っていないことが明示されますね。
なので…
A:立位保持は安定しているが方向転換に伴う不安定さで介助を要す状況。そのため、手すりやテーブルでの横移動やステップ練習による動作に伴う立位安定性の改善がトイレ移乗自立には必要。
のようなA(Assessment:評価)になるでしょうか?
純粋に
A:トイレへの意欲はあり、立位保持もある程度安定しているが「方向転換」という内乱を伴うバランス保持に困難さがあり、転倒リスクから自立に至っていない
でもいいかもしれませんね。
ただAは目標設定にも直結していて変化の判定軸になり、それまでの改善や悪化の要因を振り返り、介入の妥当性を検証する役割も持ちます。
そのため、後に続くP(Plan:計画)につながる内容も加えておくと、SOAP全体の妥当性がUPします。
カルテ記載例:筆者だったらカルテにこう書く!事例集
< 検査結果の場合 >
なぜ、その結果になったと考えるかを記載しよう!
- O:Br.stage:上肢Ⅳ 肘伸展位保持での挙上不可、手指Ⅲ 離す動作や指伸展不可
- A:上肢挙上を全身過緊張による代償動作で行うため、抹消(手指)の痙性が高まる結果、物品操作に必要な指伸展動作が行えない。上肢代償動作の抑制を図ながら促通訓練進めつつ、手指伸展出力UPに向けたワイピングでの伸展保持なども取り入れる必要あり
ここでは純粋な麻痺のステージ評価を例にしました。
「麻痺だからこのステージです!」
ではなく、そうなってしまう原因も記載したいですね。
この例の場合は麻痺側を頑張って動かそうする分、全身が踏ん張ってこわばってしまう全身過緊張や代償動作を問題点と分析しています。
なぜ、その検査結果に至り、どうしてそうなっているのかを記載していきましょう。
< 評価バッテリー >
結果からどんな症状と判断でき、日常生活への影響が予測されるか
O:半側空間無視:BIT通常検査58/146(カットオフ131)
A:机上検査でカットオフ値を大きく下回り、左半側空間無視の症状あり。日常生活場面で机上で行われる食事への影響はないか観察評価が必要。また、身体外空間の左無視が生じていないか手すりの探索や更衣動作で評価が必要と考える
作業療法士の場合、高次脳機能検査を扱うことが多いのでBITを例に挙げてみました。
半側空間無視の直接の原因は脳血管疾患による右半球損傷であろうことはわかっているので、その原因をここで述べる必要はないと判断します。
その分、評価バッテリーの結果から「何が予測されるか」が重要。
この例の数値だと日常生活にかなりの影響を及ぼしているでしょうから、実際の生活場面(食事、整容、更衣など)でどのように症状が阻害因子になっているか追加評価する必要が出てきますね。
そうすると、自ずとSOAPのP(Plan:計画)も続けてかけるような気分になってきませんか?
< 日常生活動作:ADL >
観察内容からどのように改善できるか?
O:食事で左側に置かれた小鉢や汁物に手をつけずに3分ほど座っている
A:半側空間無視により机上に置かれた左側の物品に意識が向かず、認識されていない可能性が高い。食事を食べ進めながら左側に意識が向くような盛り付け(ワンプレートタイプ)も検討してみる価値はある印象。
こちらも引き続き、半側空間無視で書いてみました。
前日にBITで高次脳機能検査を行っていて、翌日に観察評価したのであればカルテとして患者さんの半側空間無視における情報が蓄積されてきています。
なので、ここではBITの結果は載せず、食事場面で観察された内容に対してのA(Assessment:評価)を記載します。
こちらもP(Plan:計画)が明白ですね。
ワンプレート皿の導入で再評価です。
まとめ:SOAPのAとは何か?
SOAPの「A」は Assessment(評価・判断) を表し、実習生にとっては「自分が観察した事実や患者さんの発言をどう理解し、どう解釈するか」をまとめる部分。
- 「S(主観)」と「O(客観)」に基づき、学生なりの考えを整理することがポイント
- 正解・不正解を求める場所ではなく、臨床推論のプロセスを言葉にする練習の場だと思うと取り組みやすくなります。
- 「なぜそう考えるのか?」という根拠を添えると、指導者とのディスカッションが深まり、学びも大きくなります。
- 学生の段階では「推測」や「仮説」でも構いません。大切なのは、患者さんの状態を「自分の言葉で理解しようとする姿勢」です
👉 つまりAは、観察や情報をもとに“自分の考えを言葉にする場所”。ここを丁寧に書けると、P(Plan=計画)にもつながり、臨床的な思考力が磨かれていきます。
教科書の内容も参考にしつつ、「自分だったらどう考えるか」「自分は今、こう考える」というアウトプットを積極的に行ってください。
出力(アウトプット)がないと指導や助言をしようと思ってもできないですから。
個人的には文字にできなくても、言葉にして指導者に伝えられるだけでもOKです
言葉にできるってことは、ちゃんと患者さんのことを真剣に考えてるんだぞ
そうそう。
学生が精一杯、言葉にしたことをどうしたら文章にできるかを一緒に考え、導くのも指導者の役割です
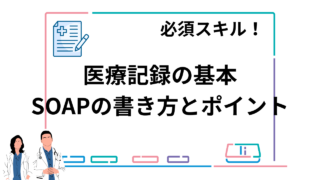
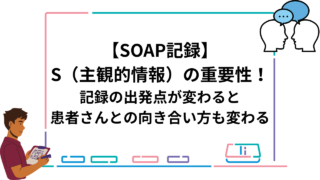
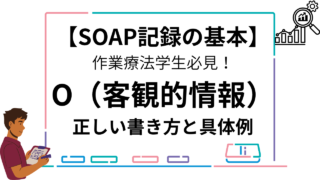
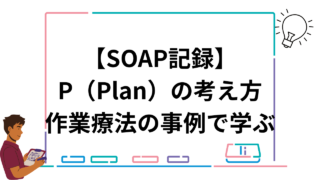
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。