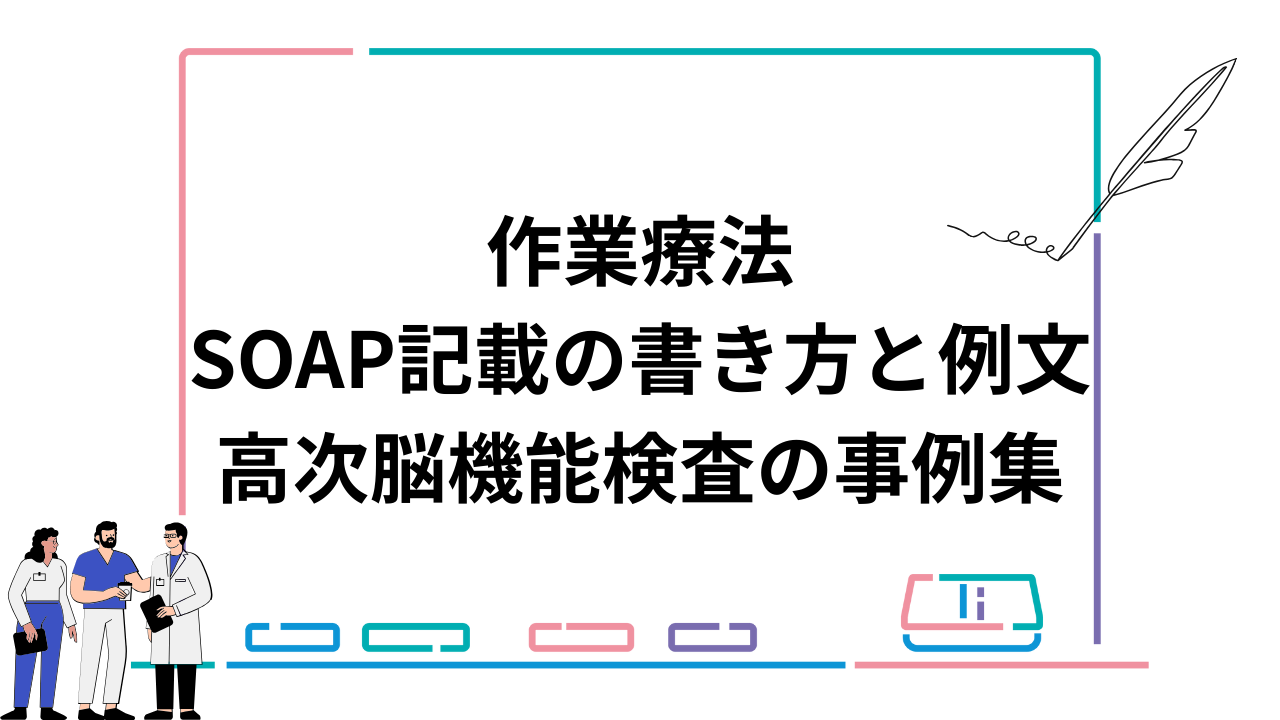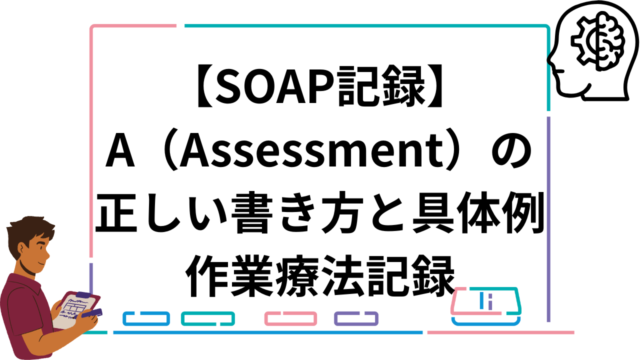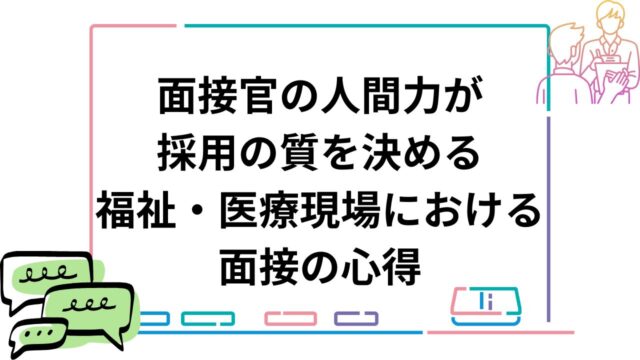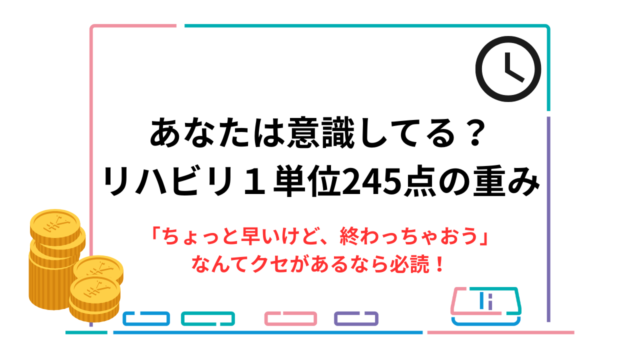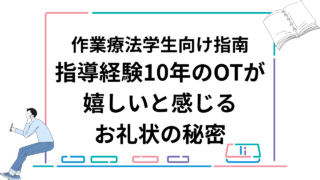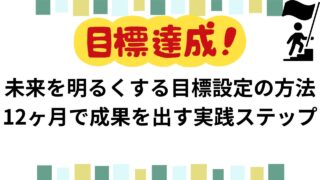作業療法の実習や現場で「SOAPを書こうとしてもPが浮かばない」「検査結果は書けるけど評価や次の行動に繋がらない」と悩んだ経験はありませんか?
特に高次脳機能検査では、点数や所要時間といった数字に目が行きがちで、「結果を並べるだけ」の記録になってしまうことも少なくありません。
ですが、それでは臨床心理士の記録と大差がなく、作業療法士としての視点が活かされないのです。
SOAP記録の本質は、検査の数値から生活にどんな影響が及ぶのかを考え(A)、その上でどのように評価・介入していくのか(P)を具体的に示すこと。
つまり、SOAPは単なる記録ではなく、日々の臨床推論【クリニカルリーズニング】を形に残すトレーニングツールなのです。
この記事では、以下のフィクション事例でBIT・MMSE・三宅式記銘力検査・TMT・FABといった代表的な高次脳機能検査を取り上げ、良い例・悪い例を比較しながら、OTならではのSOAP記載の書き方を事例集としてまとめました。
読み進めることで「検査結果を生活に還元する思考法」が身につき、実習や臨床で自信をもってSOAPを書けるようになるはずです。
SOAPとは?(簡単な定義+作業療法での重要性)
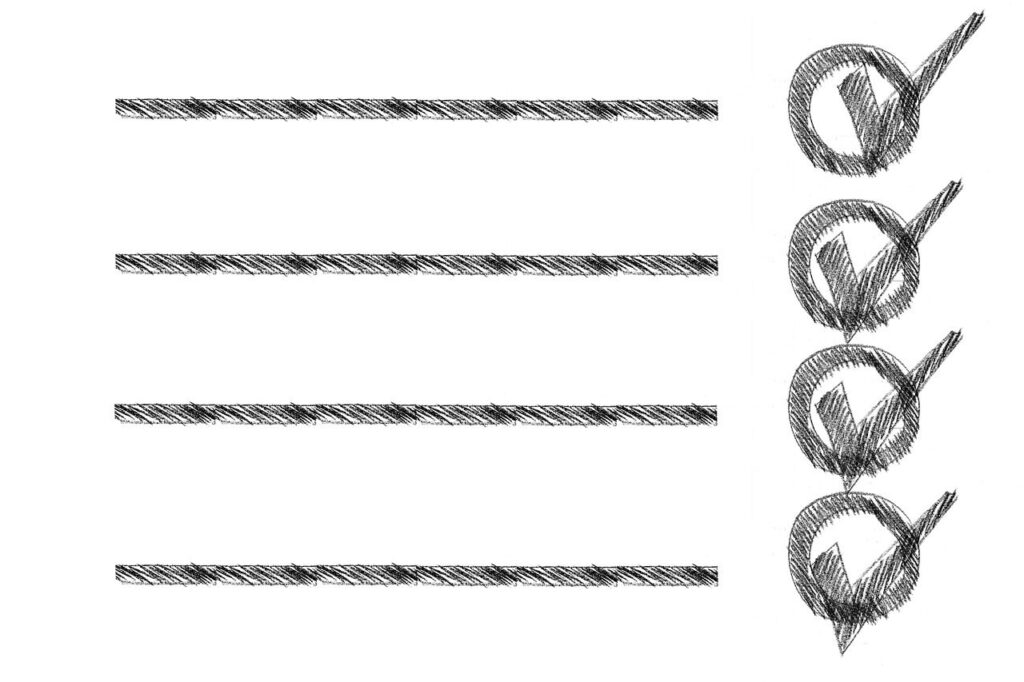
臨床現場で患者さんの状態を整理・共有するための記録方法がSOAP。
以下の4つの要素から構成されます。
- S(Subjective):主観的情報
患者さんが感じている症状や思い、訴えなど。 - O(Objective):客観的情報
バイタルサインや検査結果、観察所見など、測定可能で客観的に確認できる情報。 - A(Assessment):評価
SとOを踏まえて、臨床家が状況をどう解釈するか。 - P(Plan):計画
今後の治療方針、介入内容、指導計画など。
今回はフィクション事例で高次脳機能検査に対するSOAP記録の書き方を一緒に学んでいきましょう
高次脳検査のSOAP記録:良い例・悪い例(比較で理解を深める)
BITを実施した際のSOAP記載例
S:これで全部だよ
O:半側空間無視:BIT通常検査58/146(カットオフ131)
A:BIT通常検査でカットオフ値を大きく下回り、左半側空間無視の症状あり。日常生活場面で机上で行われる食事への影響はないか観察評価が必要。また、他の場面(更衣や清容)で左無視が生じていないか情報収集含め評価必要
P:ADL評価(食事、清容、更衣、移乗関連など)での動作観察と夜間含む病棟でのADL状況の情報収集。また、必要に応じてBIT行動検査も追加実施検討。
S:これで全部だよ
O:半側空間無視:BIT通常検査58/146(カットオフ131)
A:カットオフ値以下で左半側空間無視あり。ADL評価も進める
P:ADL評価の実施
解説
良い例は少し長めですが原因やこれからの行動も明確
悪い例は簡潔ですが「なぜそう考えるのか」が不明瞭
ただ、悪い例もSOAPとしての流れはいいね
簡潔さは大事。ただ考えたプロセスも欲しい。少なくとも聞かれた時に答えられるようにしておいて
高次脳機能検査後のSOAP記載で頻回にみられるのが検査結果だけを載せて満足するパターン。
それなら誰でもできますし、検査によっては臨床心理士さんの方が正確です(WAISⅢは特に)。
SOAP記載で必要なのは「作業療法士だからこそのあなたの視点」
検査結果(O)から何が予測されて日常にどんな影響が生じ(A)、どのような解決方法(P)があるのか
それを具体的にしていくためにSOAPの段階的な記載方法で「繋がり」を示すのです。
発見された要素(S)→検査結果(O)→予測しうる予後予測(A)→何が必要か(P)
この流れが一般的にいう臨床推論【クリニカルリーズニング】です。
日々の記録で自分自身を高め、磨き、患者さんに還元できるよう、忙しいを言い訳にせずに真剣に取り組んでみましょう
・S→O→A→Pの流れ、繋がりを意識する
・SOAPで臨床推論能力を日々高める
作業療法ならではの事例集(高次脳機能検査編)
ここからは作業療法士が活用する高次脳機能検査をいくつか例に挙げながら、SOAPの書き方を一緒に学んでいけたらと思います。
事例:MMSEを実施した際のSOAP記載例
S:検査中「最近物忘れが増えてきて心配」と本人から発言あり。
O:MMSE 21/30点。見当識(時間・場所)で複数の誤答、遅延再生は3語中0語。計算課題で途中誤りあり。
A:中等度の認知機能低下が示唆される。特に記銘・再生に困難を認め、日常生活では服薬忘れや金銭管理エラーが生じる可能性が高い。生活上の安全性確保と補助手段の導入(服薬カレンダー、金銭管理の家族サポート)が必要。
P:服薬管理状況を病棟で観察。
買い物動作や金銭管理場面の評価を行う。
必要に応じて家族への助言や支援体制構築を検討する。
AとPの文量がえげつないな。。。
私見ですが、高次脳検査を分析して計画立案の根拠を記録するってなると、これくらい必要になってきます。
解説
MMSEは認知症スクリーニングとして広く使われていますが、作業療法士の役割は「点数が低い=認知症」と記録することではないです。
また、MMSEはスクリーニング(症状の有無にかかわらず、多くの人の中から病気や疾患の疑いがある人を早期に「ふるい分け」して見つけるための検査)ですので、追加検査項目をあげるパターンも多いです。
今回でいうと三宅式記銘力検査やレイ複雑図形検査が上がるかと思います。
加えて、点数の内訳(見当識・記銘・計算・再生など)から、その人の生活で起こりうる困難を予測し、評価や支援につなげることが重要。
事例:三宅式記銘力検査を実施した際のSOAP記載例
S:〇〇さん(院内にいない人の名前)は難しいことばっかりする
O:三宅式記名力検査
・有関係:2-2-3
・無関係:0-0-0
担当セラピストの名前も記名不可
A:検査上、有関係で10個記名できず、無関係も0で記名力低下著明(対連合記憶も低下)。介入6週目になるセラピスト名の記銘も困難。
P:レイ複雑図形検査も追加実施
内服管理など時間把握して実施する必要がある作業への影響を情報収集
解説
高次脳機能検査の場合、関連する機能の追加検査判断ができるかどうかは作業療法士の知識の幅が試されます。今の時代、教科書やネットでいくらでも関連検査は調べられるし、そういった努力は惜しまず実行してください
よし!ガンガン検査するぞ
毎日検査を受ける患者さんの気持ちも考慮して、必要のあるもの、その方にあったものだけにしてください
確かに。検査することが目的になってたな
大事なのは検査から根拠を得て、その人の人生に還元すること。検査は手段の一つです
事例:TMTを実施した際のSOAP記載例
S:(TMT-B実施中)頭がこんがらがって時間かかる
O:・TMT-A 75秒
・TMT-B 263秒
・所要時間の差 188秒(3.5)
TMT-Bの文字と数字の切り替えには促しを3回必要とした
A:セットの転換困難さから注意機能障害よりも遂行機能障害が疑われる。退院後は家事動作を役割として担うことから買い物や調理で作業工程に非効率なプロセスがないかを評価する必要あり
P:買い物訓練を通じた問題解決能力の評価と観察
調理訓練に伴う遂行機能障害の影響の評価
解説
検査から予測される高次脳機能障害の特徴から、対象の患者さんの今後の人生に影響を与えうる作業を抽出しましょう。
検査実施=結果記載
そういった思考回路ではなく、検査結果=予測される作業への影響を分析・抽出して、どうやってより良い生活に繋げるかを導き出すように習慣化してください。
毎日書く記録だからこそ、毎日より良い作業提供(治療介入)ができるように考えるクセを身につけよう
TMTはAとBの所要時間の差(B-A、B➗A)を出してください。
セットの転換(概念の切り替え:文字と数字を交互に切り替えて順番に結ぶ)を含まないAと含むBを比較しないと意味ないです
FAB(Frontal Assessment Battery:前頭葉機能検査)を実施した際のSOAP記載例
S:検査中に「考えがまとまらない」「頭が混乱する」と訴えあり。
O:FAB合計9/18点(基準値≧12点)。
概念的把握課題・系列動作課題で著明な失点を認めた。保続が強く、課題切り替えに複数回の促しを要した。
A:遂行機能障害および注意機能の低下が示唆される。退院後に予定している自宅生活では、調理・買い物・金銭管理など、複数工程を要する作業に非効率さやエラーが生じる可能性が高い。生活動作への影響を多面的に把握する必要あり
P:調理や買い物を通じた実生活課題で遂行機能の影響を評価する。
金銭管理や服薬管理についても実施状況を確認し、必要に応じて家族指導や補助具導入を検討する。
解説
ここまでくると検査結果から作業への影響の分析、そして介入の流れはイメージしやすくなっているかと思います。
SOAPのA(評価)で「どの作業にリスクがあるのか」を具体化し、P(計画)で「どの場面を観察・介入するか」を明確にすることが重要。
検査はあくまで手段であり、そこから生活にどう還元するかを記録に落とし込む姿勢が、作業療法士としての臨床推論力を高めます
まとめ
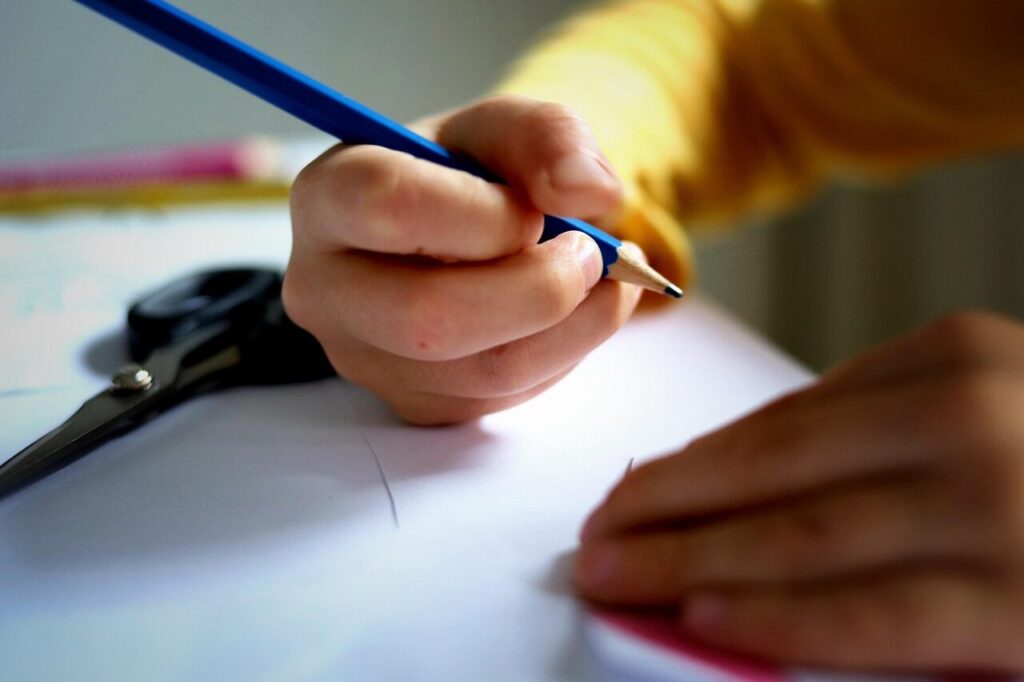
・S→O→A→Pの流れ、繋がりを意識する
・SOAPで臨床推論能力を日々高める
SOAP記載は「ただ検査結果を並べる作業」ではなく、対象者の生活にどう影響するかを考え、次の一歩へつなげる臨床推論のプロセス。
特に高次脳機能検査では、結果(O)から予測される問題(A)を分析し、解決のための具体的な行動(P)を立てることが重要になります。
学生や新人のうちは「Pが書けない」と悩むことが多いですが、それは臨床推論を言語化する練習の不足が原因。
本記事で紹介した「良い例・悪い例」の比較、検査別のSOAP事例を参考に、自分自身で書いてみることを繰り返すことで、確実に力がついていきます。
毎日の記録は単なる義務ではなく、患者さんの生活を支えるための大切な積み重ね。
今日から少しずつ、臨床推論力を意識したSOAP記載に取り組んでみましょう。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。