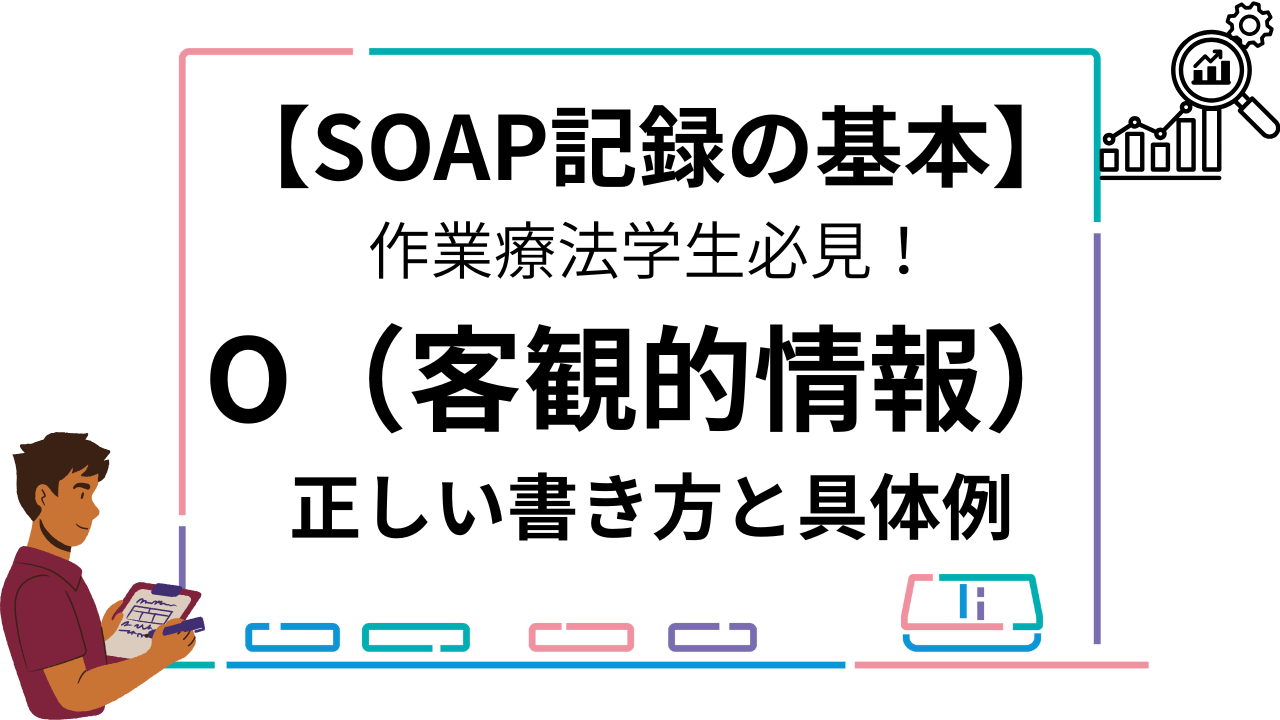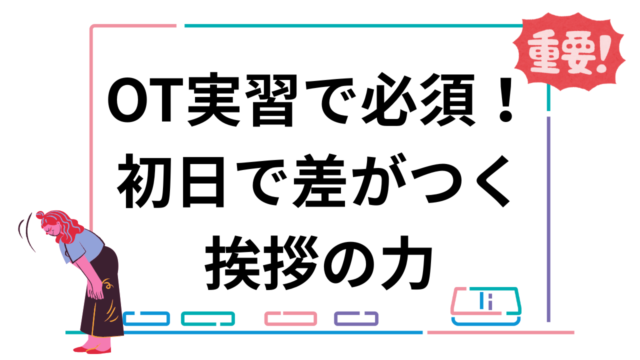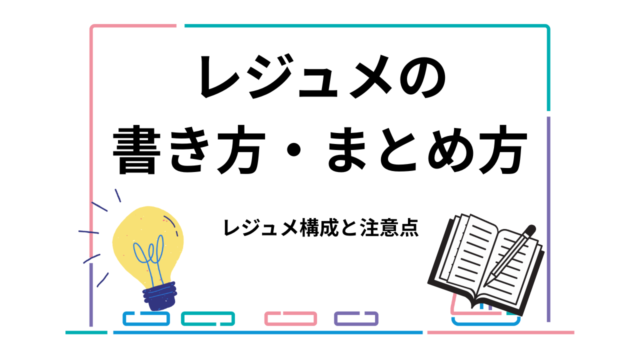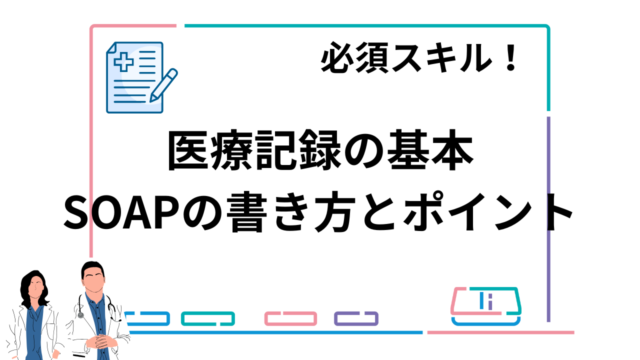一晩かけて作ったデイリーノートやケースノートを提出したら
「OとAがごちゃ混ぜだね」
なんて言われて意気消沈したこと、ありますよね?
作業療法の実習において、SOAP記録は学生が必ず向き合う課題のひとつです。
さらには現場の作業療法士もカルテを記載する時には曖昧になっていることも散見されます。
「O(Objective)」は、患者さんの状態を客観的に記録する重要な要素
Oでは、学生の主観や推測を交えるのではなく、実際に観察できた事実や測定した数値、評価スケールに基づいた情報を記載することが求められます。
例えば「手の動きがぎこちない」という表現ではなく「右手MP関節の屈曲角度は40度」と具体的に示すことが評価につながります。
ポイントは
- 数字:数値化
- 具体化
- 条件の明示
- 事実の記載
本記事では、実習指導を実際に10年近く行っている現役の作業療法士がSOAP記録におけるOの役割を整理し、書き方の基本から実際の記載例までをわかりやすく解説します。
これから作業療法実習に臨む学生や、SOAP記録の書き方を見直したい方に役立つ内容となっています。
SOAP記録とは?まずはおさらい: 4つの基本要素
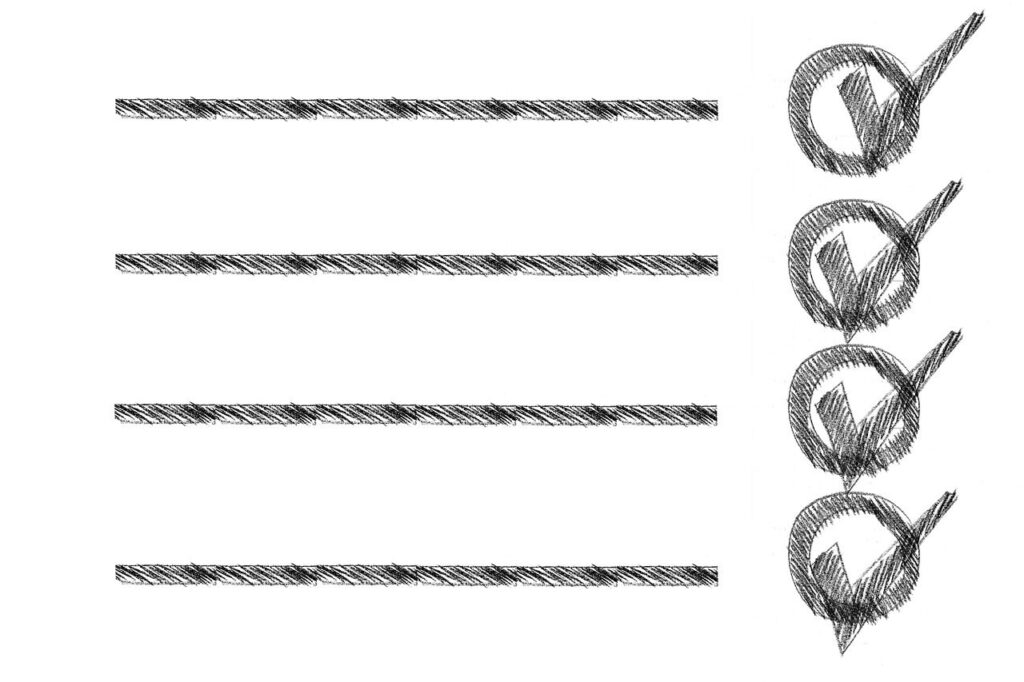
臨床現場で患者さんの状態を整理・共有するための記録方法がSOAP。
以下の4つの要素から構成されます。
- S(Subjective):主観的情報
患者さんが感じている症状や思い、訴えなど。 - O(Objective):客観的情報
バイタルサインや検査結果、観察所見など、測定可能で客観的に確認できる情報。 - A(Assessment):評価
SとOを踏まえて、臨床家が状況をどう解釈するか。 - P(Plan):計画
今後の治療方針、介入内容、指導計画など。
この中でもOは患者さんの発言や思いと医療・リハビリの根拠を繋げる重要な要素です。
Oの基本的な考え方:何を記載すればいいか?
SOAP記録の「O」は 客観的情報(Objective data) 。
ここでは学生自身の主観や解釈を交えず、観察や測定など「事実」として確認できる情報を記録することが求められます。
例えば、
- バイタルサイン(体温、血圧、脈拍など)
- 身体機能面(関節可動域:ROM、筋力:MMT、Br.Stなど)
- 高次脳機能面(MMSE、かなひろいテスト、三宅式記名力検査、TMTなど)
- 日常生活面(FIM、実際の生活場面など)
- 家事動作などIADLの様子
などが含まれます。
重要なのは「誰が読んでも同じ状況をイメージできる」ように記録すること。
たとえば
トイレ移乗が不安定
と書くよりも、
トイレ移乗で車椅子に戻る際、2回バランスを崩し、
脈も100以上となって休憩を要した
と具体的に表現する方が、より正確に患者さんの状態を伝えることができます。
また、Oには評価の過程で得られる測定結果だけでなく、リハビリ場面での行動や動作、表情や姿勢といった「目に見える変化」も含まれます(作業療法ではADLやIADLが該当)。
その場合も日記のようにせずに、数字を用いて具体的に記載することを意識してください
それによって、S(主観的情報)やA(評価)とのつながりを持たせ、P(計画)を立案するための基盤となります。
Oの具体的な記載例(Objective:客観的情報)
繰り返しになりますが大事なこと。
O(Objective)は、観察や測定によって得られる 客観的なデータ を記録する部分。
学生が陥りやすいのは「患者の主観(S)」と混同してしまうことや、抽象的な表現にとどまってしまうこと。
数値・動作・行動・検査所見など 事実ベースで表現すること が求められます。
身体所見の例
- 体温 37.2℃、脈拍 88回/分、血圧 128/74 mmHg。
- 上肢可動域:右肩外転 120°、左肩外転 160°。疼痛の訴えは右肩90°以上で出現。
- Br.stage:上肢Ⅳ 肘伸展位保持での挙上不可、手指Ⅲ 離す動作や指伸展不可
高次脳機能検査の例
- MMSE:27/30点(日時の見当識で減点)
- 記憶機能:三宅式記銘力検査、有関係6-8-10,無関係0-0-1
- 遂行機能:Trail Making Test A 65秒、B 210秒、差145秒
- 半側空間無視:BIT通常検査58/146(カットオフ131)
※ここで結果から考えられることを書いてしまうことが多いので要注意
それはA(Assessment)です。
ちょっとくらい考え書いてもいいでしょ?
SOAPは事実と考察は分けて記載しないと意味ないからダメです!
日常生活場面(ADL)の例
- 食事:自立(箸操作良好)
- 更衣:上衣着脱に要する時間は約3分。袖を通す動作で右手が遅延。
- 移乗:ベッド⇔車椅子は監視レベル(1分程を要する)で、L字柵必須。
- 排泄:トイレ動作は自立、下衣の上げ下ろし(臀部引っ掛かり)に軽度介助必要
IADL場面の例
- 買い物
- スーパーで必要物品の選択は可能だが、現金支払いで小銭で支払えず。10000円札で支払う(前回も同様で財布は小銭で溢れている状態)
- スーパーで必要物品の選択は可能だが、現金支払いで小銭で支払えず。10000円札で支払う(前回も同様で財布は小銭で溢れている状態)
- 調理
- 簡単な炒め物は可能。しかし、一食分の食事(汁物とサラダ、メイン)同時遂行が必要になると1時間で1品も完成することができなかった。
- 簡単な炒め物は可能。しかし、一食分の食事(汁物とサラダ、メイン)同時遂行が必要になると1時間で1品も完成することができなかった。
- 公共交通機関の利用
- 単独でバス亭までいき支払いもSuicaで可能だが、バスの番号確認せず乗り込もうとするため、声かけとチェックの促しを要した
O(客観的情報)の書き方の注意点
O(Objective)は、SOAP記録の中でも「観察・測定・検査に基づく客観的事実」を示す部分。
臨床実習や日々の臨床記録において信頼性を高めるためには、以下の点に注意して記載することが重要です。
1. 他のSOAP項目と混同しない
Oはあくまで「客観的に確認できる事実」のみを記載。
患者さんの発言や訴えはS(Subjective)に書くべきであり、Oには入れません。
同様に検査結果の分析はA(Assessment)です。
「カットオフ値以下だから高次脳機能障害が疑われ、日常生活でも影響している様子が観察されている」などは全てAです。
(Assessment)の直訳が評価だから惑わされないようにしてください。
私も病院勤務している時に「Assessmentは評価なんだから評価結果はAに書くべきです!」と間違った解釈が病棟で伝染した経験があります。
外部の人から見られた時に恥ずかしい思いをしないように気をつけて
2. 数値化・定量化を意識する
「反復動作による痙性UPあり」「浴槽移乗が不安定」といった表現は抽象的で、評価の再現性が低くなります。
可能な限り具体化しましょう!
- 反復動作による痙性UPありは…
お手玉を前方10cmの高さのカゴに移動する作業で3個以上で肘伸展困難となり、上半身前傾の代償動作が著明になる様子が3セット中3回観察された
- 浴槽移乗が不安定は…
立位での浴槽移乗は出入りともに麻痺側下肢管理不十分で2回実施しても2分以上かかり重介助。
など、測定可能な数値を用いることで誰が見ても同じ判断ができるようにします。
ストップウォッチがあるとADL動作の数値化がしやすくなります。
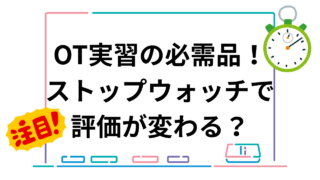
3. 観察した事実を具体的に書く
「リハビリに積極的である」といった解釈的な表現は避け、「リハビリ開始時、自ら椅子に移動し練習を始めた」といった行動事実を記載します。
事実に基づく記録は、後の評価や治療方針の根拠になります。
4. 測定条件を明確にする
バイタルサインや可動域測定は、測定環境や条件によって数値が変化します。
例えば「安静座位にて測定」「ベッド上背臥位にてROM測定」といった条件を付記することで、信頼性と再現性を高められます。
5. 略語・専門用語の使用に注意
医療現場では略語が多用されますが、誤解を招く可能性があります。記録はチーム全体が共有するものなので、必要に応じて正式名称を併記することが望ましいです。
まとめ:SOAP記録のOを正しく書く力は実習成功の鍵

作業療法実習におけるSOAP記録の中でも「O(客観的情報)」は、患者さんの状態を事実に基づいて共有するための重要な要素。
曖昧な表現や主観的な判断ではなく、観察した事実や測定値を明確に記載することが信頼性の高い記録につながります。
数値化や具体的な動作の描写を意識することで、指導者や他職種にも正しく伝わりやすくなり、評価や今後の計画を立てる際の確かな根拠となります。
SOAP記録は単なる記録ではなく、患者さんの状態を正確に捉え、次のA(Assessment)である臨床推論や計画立案へとつなげる大切なプロセス。
Oの書き方を理解し、客観的で具体的な記録を積み重ねていくことが、実習を成功に導き、臨床家としての基礎を築く第一歩となります。
これから実習に臨む学生はもちろん、記録の質を見直したい方も、Oの基本をしっかり押さえて日々の実習や臨床に活かしていきましょう。
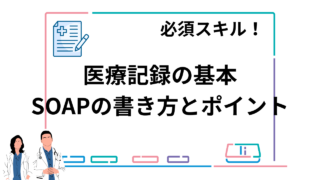
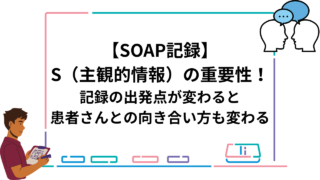
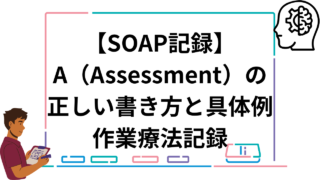
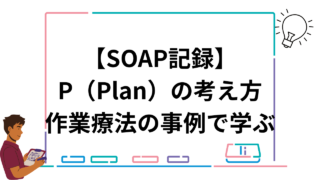
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。