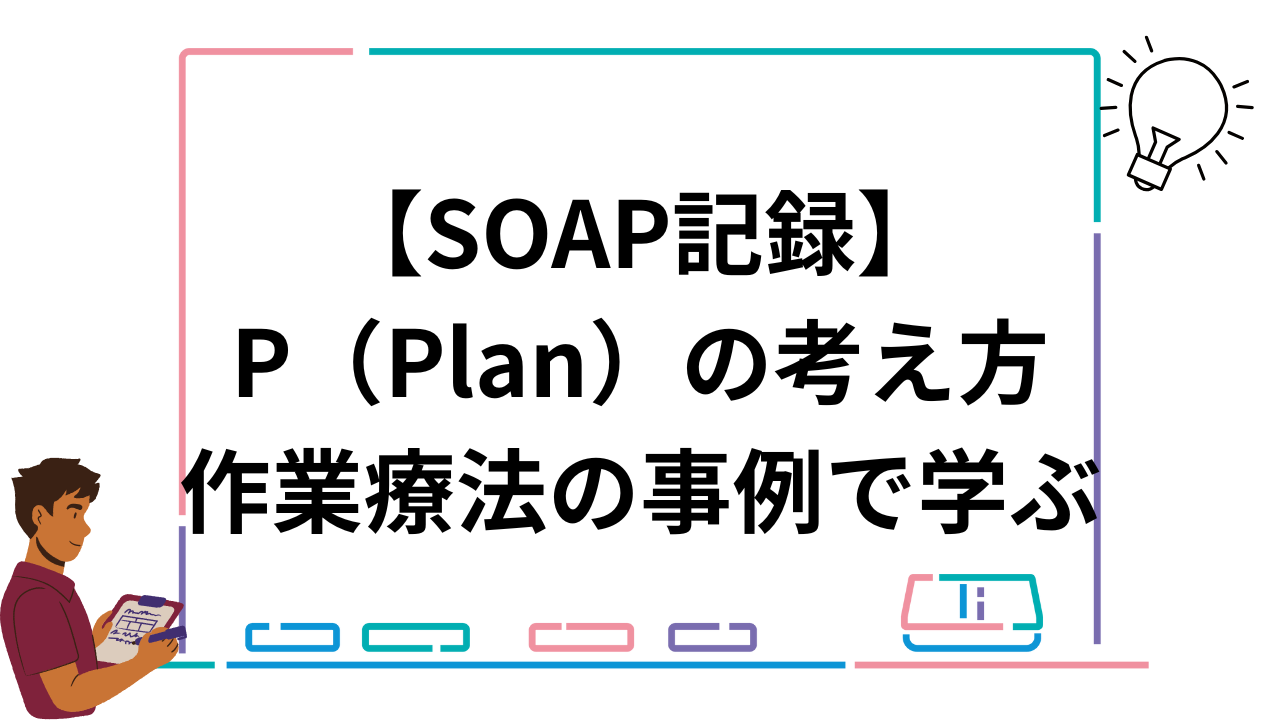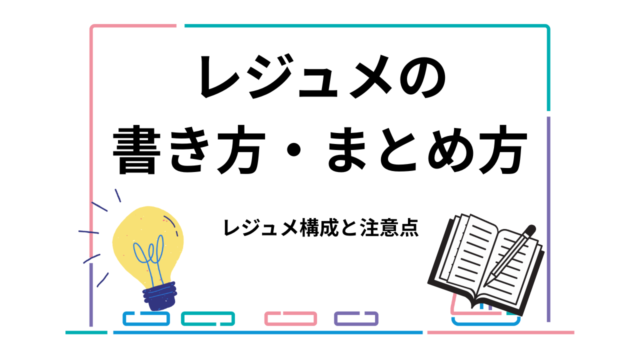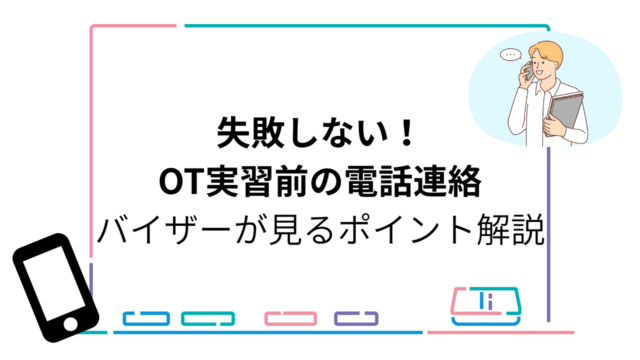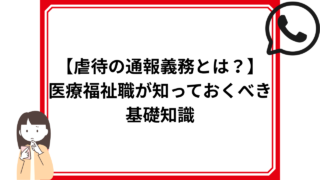SOAPの最後に位置する「P(Plan)」は、実際の臨床現場において非常に重要な部分です。
でも、記録を書いていると「Pが書けない!Doでいいや!」なんてことしてませんか?
患者さんの状態を主観的(S)・客観的(O)に捉え、そこから評価(A)を導き出したうえで、今後の介入方針を明確にするのがPの役割です。
例えば、
- 上肢機能向上のために自主トレーニング導入を実施
- 次回は移乗動作(ベッド間、トイレ、浴槽)評価を追加
- 調理訓練に向けたADL室での動作確認実施
といったように、短期的・具体的な計画を書きます。
Pがあることで、単なる観察記録に終わらず、治療や支援の方向性がチーム全体で共有できるようになります。
SOAPのPは、患者の未来を形作るための「行動の指針」といえるのです。
今回の記事はSOAPの基本の後はフィクションで事例をたくさん挙げていき、
- P:Plan(計画)はこうやって導き出すんだ。
- SOAPってこうやって書くんだ
と体感していただけるようにしてみました。
SOAP記録とは?まずはおさらい: 4つの基本要素
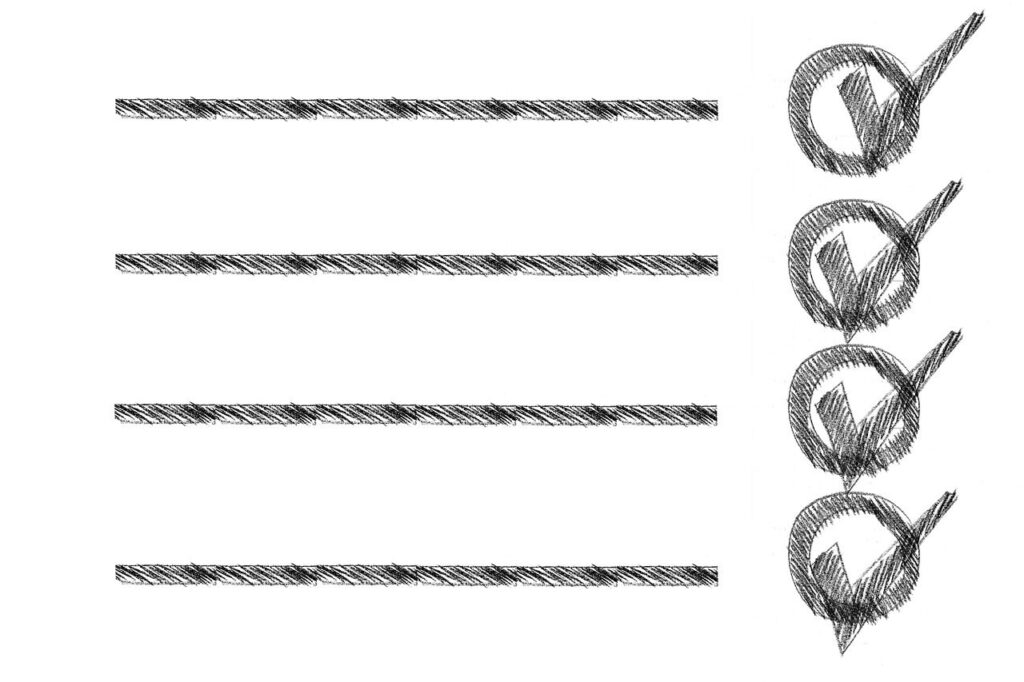
臨床現場で患者さんの状態を整理・共有するための記録方法がSOAP。
以下の4つの要素から構成されます。
- S(Subjective):主観的情報
患者さんが感じている症状や思い、訴えなど。 - O(Objective):客観的情報
バイタルサインや検査結果、観察所見など、測定可能で客観的に確認できる情報。 - A(Assessment):評価
SとOを踏まえて、臨床家が状況をどう解釈するか。 - P(Plan):計画
今後の治療方針、介入内容、指導計画など。
この中でもPはS:主観的情報とO:客観的情報から導き出されたA:評価で見えた次の作業療法での患者さんへのアプローチ方法を記載する未来のための記録です。
具体例:様々なSOAP記録からP:Plan(計画)を学びとる!
< 身体機能関連:亜脱臼のある脳出血の発症2週目の患者さん >
S:腕が重い
O:・上肢Br.StⅡ
・移乗後に手を敷いて座る様子あり(2回に1度)
・寝返り動作での上肢置き忘れあり(ほぼ毎回)
A:発症2週目で今後の改善は期待できるが、麻痺側上肢管理が不十分で肩関節痛が生じる可能性が高い。日常でのポジショニング(臥位、座位、移乗時など)に加え、夜間状況含めて介入必要
P:・車椅子座位で膝上に枕など腕置き設置
・病棟ベッドポジショニングと夜間状況の聴取
・アームスリングの活用(移乗時)
アームスリングは賛否あるのは承知ですが、個人的には移乗時の麻痺した上肢管理をスムーズにするためには有用と考えます(病棟スタッフさんは日常の介助で精一杯になりますし)。
考え方は人それぞれ。自信を持って自分の考えを明確に記録してけ!
< 高次脳機能検査:妻と二人暮らしの退院間近の70代男性 >
S:昔っから忘れっぽいけど、一人じゃもう駄目だ。妻に助けてもらわなきゃ。
O:・MMSE12/30点(カットオフ23/24)
減点項目:日時の見当識、連続減算、遅延再生、作文、図形模写
・病棟で内服自己管理が課題と相談あり(現状は病棟管理中)
・妻(心身良好)との関係良好で自宅退院予定
A:見当識および言語情報の処理に困難さが認められ、内服管理のように時間や言語情報を正確に処理することが求められる作業は難易度が高い印象。介助者となる妻へ必要含めて説明し、本人も受け入れている妻へ依頼したほうが現実的と考える。
P:・病棟スタッフとの内服に関する情報共有と提案
・妻への内服管理方法の伝達
認知機能低下があっても自宅で家族と過ごされる。そんな時に本人のできることはないかと模索し、様々な相談が病棟からあると思います。
もちろん残存能力は最大限活用していくことは大切ですが、どうしても医療者の思いが先に立ってしまうことがあるのも事実。
そういった時に検査結果やそこから見えた事実に基づいて、病棟スタッフや今後支えていくご家族と連携していきたいですね。
事実(O)に基づく分析(A)、提案(P)だと病棟も受け入れやすいね
< 高次脳機能検査:発症23日目の右半球脳梗塞の50代男性 >
S:これで全部だよ
O:半側空間無視:BIT通常検査58/146(カットオフ131)
A:机上検査でカットオフ値を大きく下回り、左半側空間無視の症状あり。日常生活場面で机上で行われる食事への影響はないか観察評価が必要。また、他の場面で左無視が生じていないか手すりの探索や更衣動作で評価が必要と考える
P:・ADL評価(食事、移乗関連、更衣)と夜間含む病棟への情報収集
・必要に応じて、行動検査も追加実施を検討
BIT58点だと日常生活に影響が大きいので、どのような時にどんな形で影響を与えているか評価したいところ。
加えて、日中だけでなく夜間の様子も含めて病棟スタッフに情報収集すると良いでしょう。半側無視により全般性注意の低下(一般的にいうと注意散漫な状態)もよく認めるので、作業療法士側から病棟に聞くと多くの課題が見えてきます。
半側空間無視は方向性注意の障害。一般的な注意障害は全般性注意の障害なんて言ったりするよ。
急に専門知識語るなよ!
< 日常生活動作:回復期病棟で1ヶ月経過した脳梗塞の方 >
S:トイレに行きたくても行けなくて毎日つらい
O:トイレ動作は自立レベルだが、トイレ移乗は麻痺側のステップがうまくできず2回に1回は方向転換に触れる程度の介助を要する
A:立位保持は安定しているが方向転換に伴う不安定さで介助を要す状況。そのため、手すりやテーブルでの横移動やステップ練習による動作に伴う立位安定性の改善がトイレ移乗自立には必要。
P:・ステップ練習の実施(実際に使用するトイレ)
・トイレ以外での移乗動作場面の増加
・担当PTへの情報共有
こちらもよくありますね。
今回のポイントは環境設定もPに含めていること。実施する場所や方法も記載できていると代診で介入する作業療法士もわかりやすいです。
加えて、身体機能面も関わることであれば理学療法士への相談と共有も欠かせません。チーム連携は必須です。
一人でやれるとことは限られてます。チームで解決して患者さんのより良い生活に向けたサポートをしていきましょう
<IADL関連:脳出血(麻痺軽度)の独身30代の調理訓練 >
S:(時間がかかりましたか?の問いに)一人身だし、自分の分ができれば十分。惣菜だってあるし。
O:・1食分の朝食調理(炊飯、汁物、卵焼き)を1時間で準備〜片付けまで実施
・鍋取り出しのしゃがみ込みなど身体機能は問題なし
・先に時間のかかる炊飯(米研ぎなど)から行わず、声掛け要する
・両手で持ち運び可能も1品ずつ出すため、冷蔵庫とキッチンを10回以上往復
・惣菜活用を自ら提案
A:・作業遂行可能だが繰り返し動作が多くなり、加えて複数作業を同時遂行する際に組み立て(時間のかかるものから先にやる等)が非効率となり時間を要する。
・声掛けで修正可能で受け入れも可能。惣菜活用など問題解決方法も自ら考えること可能
P:・同時作業課題の実施(ながら作業など)
・再度、調理訓練を実施して反復による学習効果有無の評価
調理訓練は観察方法や課題設定で大きく変化する作業療法士の腕の見せ所。
AMPSライセンスも取得したことのある筆者からすると「運動」「プロセス」の2つの視点で原則声掛けせずに患者さんだけで実施してもらうスタンスで介入します。
私たちは退院した後はいないので、その前提で介入するとリアルな退院後の姿がイメージできると思います。
ちょっとぐらい手伝ってやれよ!優しくないな!
それは優しさではなく、セラピストの自己満足。
患者さん自身が自分の人生を歩めるように見守る姿勢も大切です。
まとめ:SOAPのP(Plan)は作業療法の要

SOAP記録のP(Plan)は、単なる「次にやることのメモ」ではありません。
S(主観的情報)とO(客観的情報)をもとにA(評価)で整理した内容を、実際の介入にどうつなげるのかを示す 未来への指針 です。
- 患者さんの状態に即した短期・長期目標を明確にする
- 具体的なリハビリ内容や評価計画を書き込む
- 医療チーム全体で共有できる形にする
- 介入後には振り返り、柔軟に修正する
この4点を意識するだけで、Pは「形だけの記録」から「臨床で役立つ実践的な計画」に変わります。
実習生にとって、SOAPのPを書くことは難しく感じるかもしれません。しかし、事例を通して「評価から計画へとつなげる流れ」を体験的に学ぶことで、自然と臨床思考力が身についていきます。
SOAP記録は、患者さんの未来を支えるための大切なツールです。
ぜひPの部分を丁寧に書き、チームで共有し、次の一歩につなげてください。
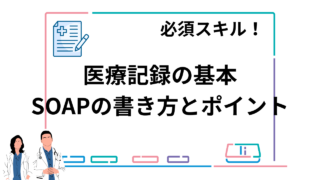
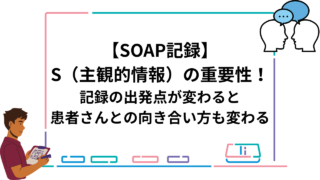
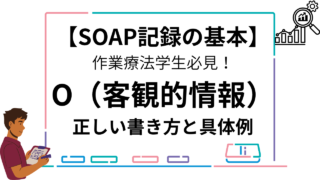
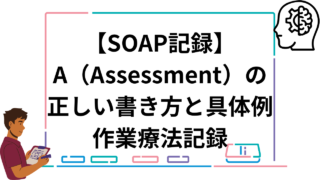
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。