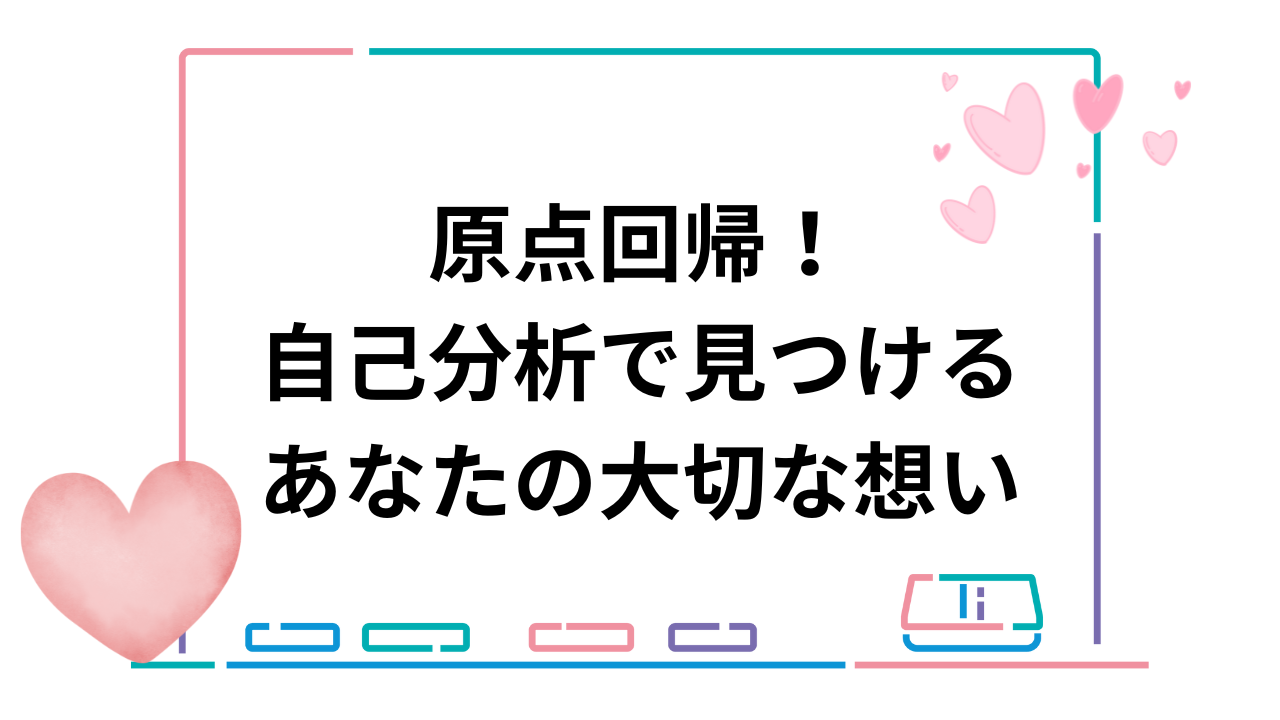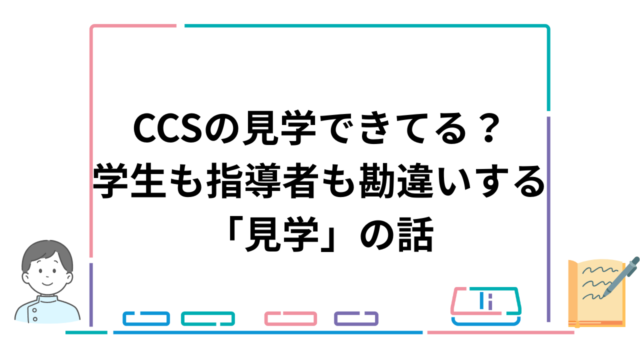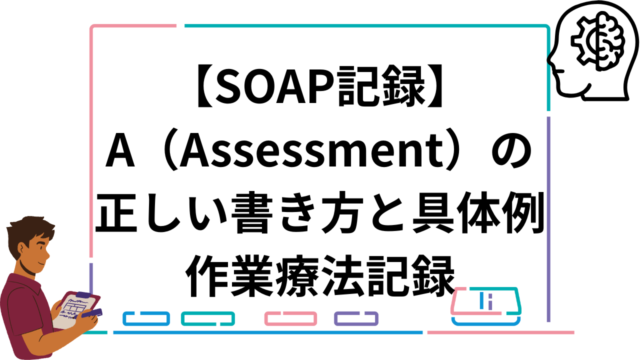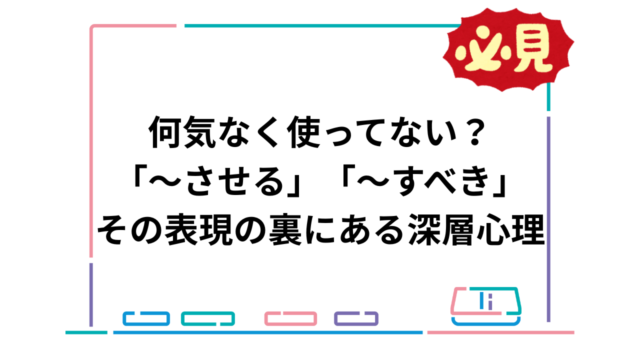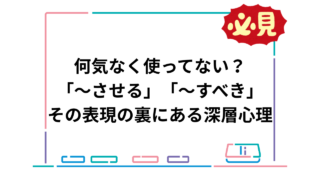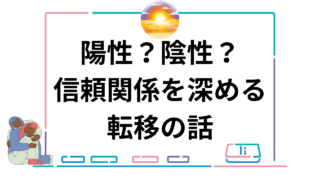作業療法士として働く中で、「治療の正しさ」と「クライアントの幸せ」の間で迷った経験はありませんか?
日々のリハビリ現場では、成果や計画に追われるあまり、作業療法士を志した頃の純粋な想いが薄れてしまうことも少なくありません。
そんな時こそ、自分自身を深く理解し、同時にクライアントの価値観や背景を理解することが、支援の質を大きく高めます。
本記事では、自己分析とクライアント理解を同時に進めるための簡単で効果的な方法「付箋ワーク」をご紹介。
付箋を使って「好きなこと・得意なこと」「できること」「苦手なこと」を可視化し、そこから共通点を見つけ出すことで、障害者と治療者という枠を超えた人と人としてのつながりが生まれます。
そして、その気づきを基に「支援計画(治療プラン)」へ落とし込み、より温かく意味のある支援へと変えていくプロセスを作業療法士や学生、そして障害福祉やリハビリに携わるすべての人に向けて解説します。
1. 自己理解から始める支援の質向上

なぜ自己理解が大切なのか
作業療法士としての専門知識や技術はもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、「自分はどんな支援者なのか」を知ることです。
自己理解が進むと、自分の強みを最大限に活かし、弱みをカバーする方法を見つけられます。結果として、クライアントへの関わり方や言葉選びも変わってきます。
< 自己理解の3つの項目 >

付箋ワークでは、まず以下の3項目について付箋に書き出していきます。
- 自分の好きなこと・得意なこと
例:人の話を聞くのが好き、工作が得意、創意工夫することが好き
※あなたの「大切な作業」はなんですか? - 自分のできること
例:評価スキル、関係機関との連携、利用者に合わせた運動メニュー作成
※歩ける、喋れる、パソコンが打てるも「できること」ですね - 自分が嫌いなこと・苦手なこと
例:長時間の事務作業、大人数の前での発表、細かい数値管理
※あなたの価値観に合わないものはなんでしょう?
ポイントは深く考えすぎず、頭に浮かんだことをどんどん書き出すこと。
1〜3をそれぞれA4用紙に貼り付けていくといいでしょう。
これにより、自分の価値観や行動パターンが自然と浮かび上がります。
2. クライアント理解への応用
自己理解を終えたら、同じ手順でクライアントについても整理します。
- クライアントの好きなこと・得意なこと
- クライアントのできること
- クライアントの嫌いなこと・苦手なこと
例えば、高齢のクライアントが
・「庭いじりが好きだった」
・「手先が器用だった」
という情報を持っていれば、それはリハビリプログラムを作るうえでの重要なヒントになります。
家族や本人との会話、生活歴のヒアリングから得られた情報を付箋にまとめ、視覚化すると、見えにくかった特徴や強みがはっきりします。
3. 共通点を見つけることで生まれる「人と人」としての関係

自己理解とクライアント理解を並べてみると、予想もしていなかった共通点が浮かび上がります。
- 昔好きだった遊びが一緒
- 好きな色が同じ
- 苦手なことまで似ている
そんな瞬間、胸の奥がふっと温かくなるような感覚が訪れます。
「何だ、障害者と治療者じゃなくて、そもそも同じ人間じゃないか」
この気づきは、支援の在り方を根本から変えてしまうほどの力を持っています。
それまで「支える側」と「支えられる側」という固定された構図の中にいた私たちは、互いに向き合う【ただの人】として同じテーブルに座ることができます。
そこには上下関係も、「教える・される」という一方通行の流れもありません。
代わりにあるのは、互いの価値観や人生を尊重し合う、温かいパートナーシップです。
この関係性の変化は、支援者自身のモチベーションにも大きな影響を与えます。
「ちゃんとした治療・支援を提供しなければ」という義務感から、「この人の人生を少しでも豊かにしたい」という純粋な願いへと、心の方向が変わっていきます。
その瞬間、支援は単なる職務ではなく、自分の人生の一部となります。
そして、その思いは必ずクライアントにも伝わり、互いの関係をより深く、強い絆へと変えていくのです。
4. 支援計画(治療プラン)への落とし込み
共通点や相互理解が深まったら、それを支援計画に活かします。
- 好きなことを活かした訓練メニュー
- 苦手なことを避けつつ段階的に挑戦できる課題設定
- 本人の価値観を尊重した生活目標の設定
ここで忘れてはいけないのは、一人で抱え込まないこと。
理学療法士、言語聴覚士、看護師、介護職、地域ボランティアなど、多職種や地域の力を借りることで支援の幅は大きく広がります。
5. 「正しい治療」よりも大切なこと

医学的根拠に基づいた正しい治療は、作業療法士としての責任で欠かすことのできない基盤。評価や計画、エビデンスに沿った介入は、確かに私たちの仕事の柱です。
しかし、現場で本当にクライアントの心を動かし、人生を変えるほどの力を持つのは、教科書やマニュアルには書ききれない「目の前の人のために」という純粋な気持ちと、それを行動に移す勇気です。
たとえば、ある日は予定していた訓練を中断してでも、クライアントの不安や悲しみに寄り添う必要があるかもしれません。
そうした小さな行動の積み重ねこそが、信頼関係を深め、支援の効果を何倍にも高めるのです(もちろん、治療と思いを叶えるバランスは大事)
思い出してください。
あなたが作業療法士を志した頃、「資格を取ること」や「正しい手技を身につけること」だけが目的ではなかったはず。
きっと、「誰かの役に立ちたい」「困っている人の力になりたい」という真っ直ぐな願いがあったはずです。
その想いを、今の現場で生きた形にすること。
それが、技術や理論を超えて支援を本質的に変え、クライアントとあなた自身の人生をも豊かにしていくのです。
まとめ|原点回帰が支援を変える
付箋ワークによる自己理解とクライアント理解は、障害者と治療者という立場を超えて「人と人」としてのつながりを作ります。
そのつながりこそが、作業療法士としてのモチベーションを高め、支援の質を向上させる原動力になります。
今日から机の上に付箋とペンを置き、まずは自分を知ることから始めてみませんか?
あなたの支援は、きっとより温かく、より意味のあるものへと変わっていくはずです。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。