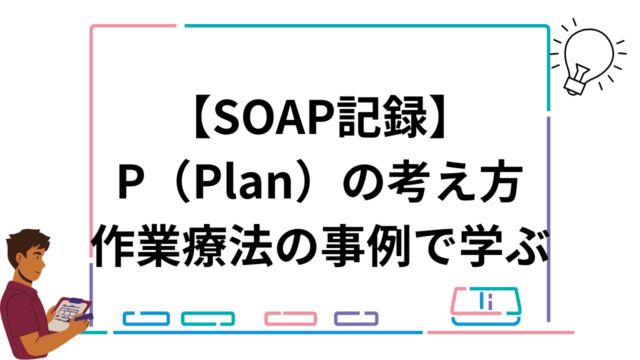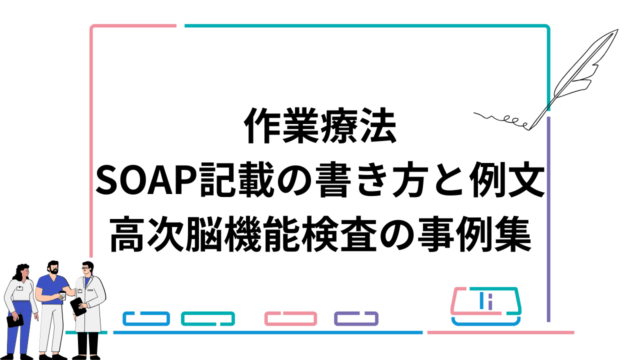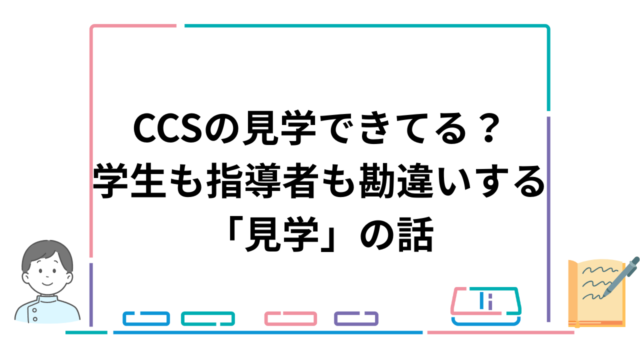作業療法(OT)の実習といえば、メモ帳やペンを持参するのは当たり前。
ですが、実はあまり知られていない“持っていると評価が上がる便利アイテム”があります。
それが**「ストップウォッチ」**。
時計で代用できると思われがちですが、臨床現場では時計を身に着けないセラピストが多く、特に金属部分がクライアントの肌に触れて傷をつけてしまうリスクを避けるためです。
実習中にも同じ配慮が求められるため、ストップウォッチがあると非常に便利。
評価検査や訓練で「時間を正確に測る」場面は多く、三宅式記銘力検査やTMTなど時間計測が必須の検査では特に重宝します。
いざという時に「私、持っています」と差し出せれば、バイザーからの印象もアップ。
この記事では、作業療法実習でのストップウォッチ活用法や使用場面、準備のポイントをわかりやすく解説します。
ストップウォッチが作業療法実習で役立つ理由
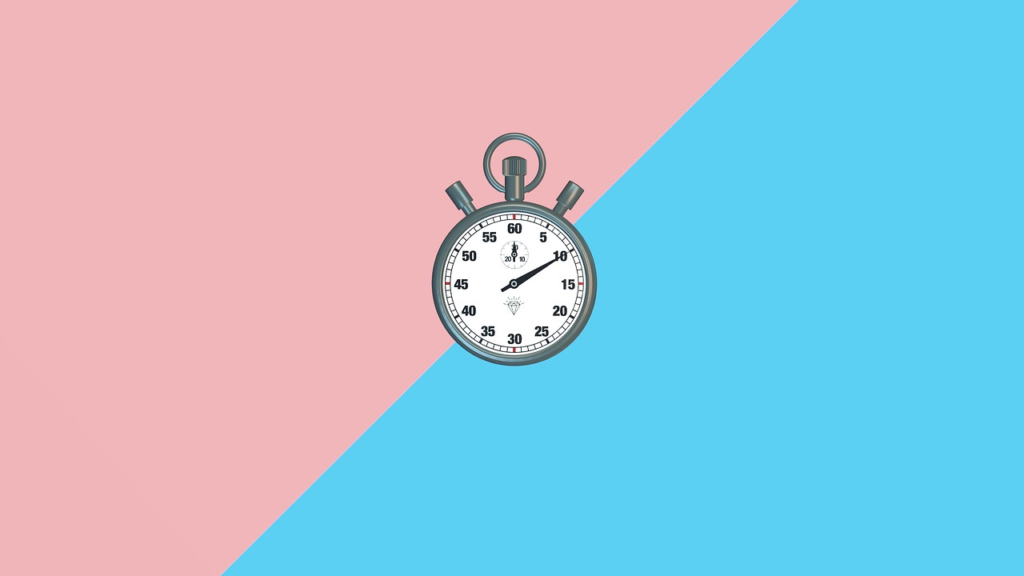
作業療法の実習では、時間を正確に計測する場面が非常に多くあります。
作業療法実習では、時間管理は単なる作業効率ではなく、臨床的な根拠を持つ重要なスキル。
動作分析や評価記録、プログラム管理など、正確な時間計測が成果を左右する場面は数多くあります。
しかし、現場ではスマートフォンや腕時計の使用が制限されることもあり、衛生面・安全面を考慮するとストップウォッチの有用性が際立ちます。
持ち運びがしやすく、片手操作でスタート・ストップができるストップウォッチ。
実習中に自然に取り出して使えると、現場での信頼度がグッと上がります。
作業療法実習での主な使用場面
ストップウォッチが必要になる主な場面を挙げてみます。
- 評価検査:特定の課題をどれだけの時間で行えるか測定するために使用
- 訓練場面:動作訓練や作業課題を「○分間やりましょう」という形で実施する際に使用
- リハビリ効果の確認:経過観察や改善度合いを比較するために時間を測定
こうした場面で、サッとストップウォッチを出せる学生は、バイザーから見ても「現場感覚がある」と評価されやすくなります。
ストップウォッチを使う主な評価検査一覧

作業療法の評価検査の中で、ストップウォッチを使う代表例を挙げます。
- 三宅式記銘力検査
- TMT(Trail Making Test)
- BIT
- コース立方体組み合わせテスト
- かなひろいテスト
- BADS
これらの検査では「正確な計測」が必須であり、誤差が出ると評価結果にも影響します。
持っていると印象アップする理由
実習生がストップウォッチを持っていると、バイザーからの評価は確実に変わります。理由は2つ。
- 準備力の高さ:「必要になる場面を予測して道具を用意している」と評価される
- 臨機応変な対応:急に必要になった場面でもスムーズに対応できる
こうした姿勢は、臨床現場では非常に重要視されます。
実習前の準備と選び方のポイント

- サイズ:ポケットに入るコンパクトなタイプが便利
- 機能:ストップ・ラップ・タイマーがあると汎用性が高い
- 防水性:医療現場では手洗いの機会が多いため必須
- 静音操作:ビープ音を消せるタイプが望ましい
静音操作は臨床では結構大事です。
患者さんや利用者さんに「ちゃんとやらなきゃ」と思わせなくていいし、そもそも検査されるという事自体に嫌悪感を示す方も少なからずいらっしゃいます(症状として表出されることもあるため)。
そんな時に「ピッ!」って鳴ったら…
だからこそ、静音操作できるストップウォッチはさらにポイント高いです。
まとめ:ストップウォッチで差をつける実習準備
作業療法実習では、知識や技術だけでなく「準備力」も評価されます。
ストップウォッチは、評価・訓練・経過観察など多くの場面で活躍し、持っているだけで信頼度が高まる道具です。
ぜひ実習前に準備し、現場でスマートに活用しましょう。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。