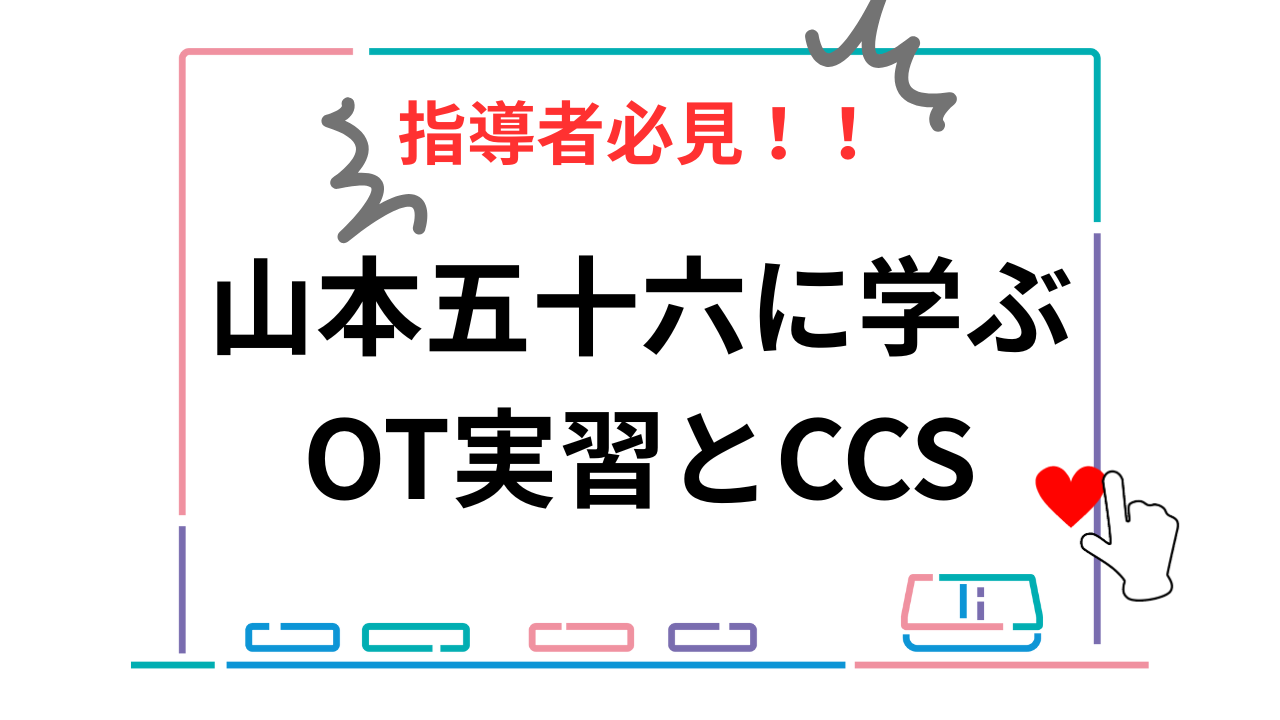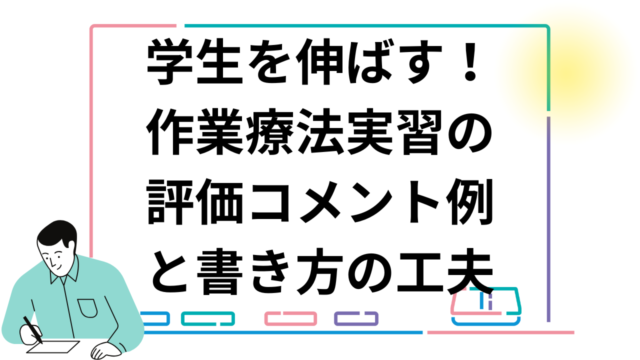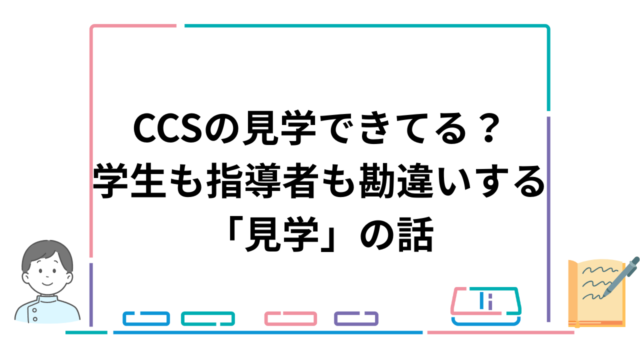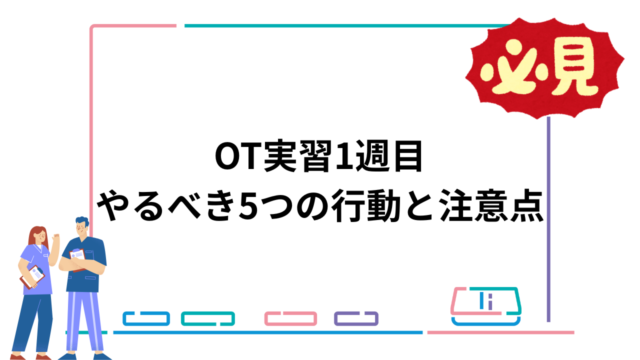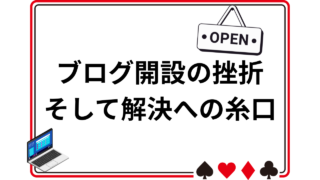― 山本五十六の言葉に学ぶ、信頼と成長のプロセス ―
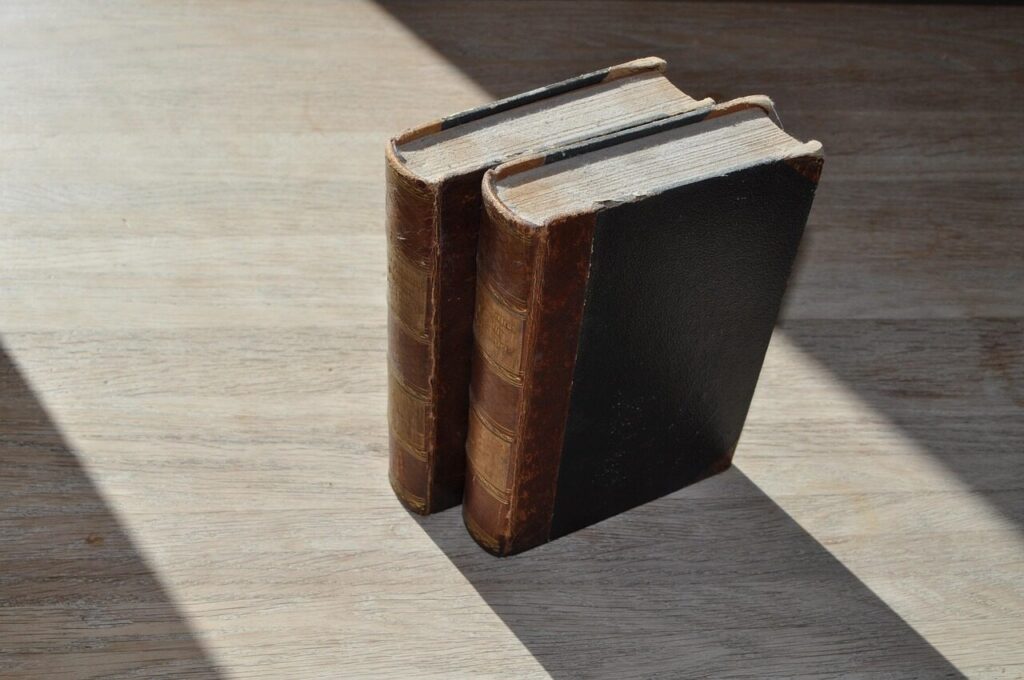
作業療法の臨床実習指導において、学生の成長をどう支えるか。
これは、実習指導者にとって非常に重要なテーマです。特に、近年導入が進む「クリニカル・クラークシップ(CCS)」では、学生が実際の医療現場に参加し、患者と関わりながら“主体的に学ぶ”ことが求められます。
しかし、学生が自ら考え、行動し、成長していくためには、指導者の関わり方がカギを握ります。単に“任せる”だけではなく、信頼関係を築きながら育てる姿勢が必要です。
この記事では、CCSにおける実習指導の考え方を、山本五十六の教育的名言をもとに解説します。作業療法の実習現場で、学生をどう支え、どのように育てていけばよいのか。教育と信頼の本質を、そして何よりも「信頼関係を築きながら人を育てる方法」について臨床現場の視点から紐解きます。
✅ CCSとは? ―「育てること」そのもの

「CCS(クリニカル・クラークシップ)」は、医療系教育において取り入れられている臨床参加型の実習形態です。学生は単なる見学者ではなく、医療チームの一員として患者と向き合い、評価・介入を体験していきます。
つまり、CCSとは「知識を詰め込む場」ではなく、「現場で実践的に育てる場」。教える側にとっても、従来の“指示を与える”指導ではなく、「ともに成長する」意識が必要となります。
❓ なぜ「任せるだけ」では学生は育たないのか?
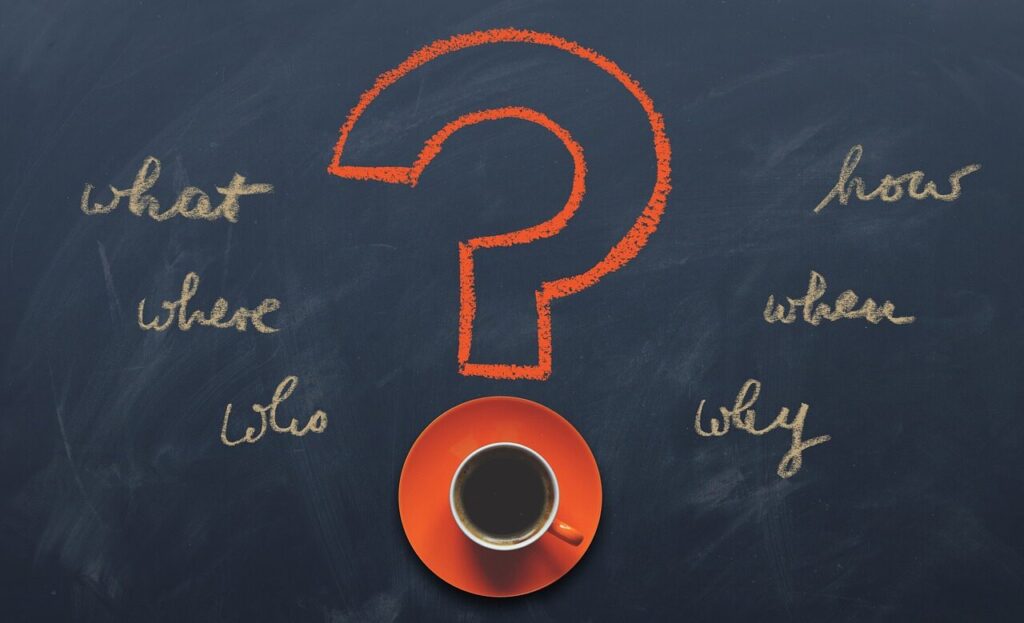
「任せれば育つ」というのは、実習現場では通用しません。
ここで引用したいのが、山本五十六の有名な言葉です
やってみせ
言って聞かせて
させてみせ
褒めてやらねば、人は動かじ。
話し合い
耳を傾け、承認し
任せてやらねば、人は育たじ。
やっている
姿を感謝で見守って
信頼せねば
人は実らず。
この言葉に、教育・育成のすべての本質が詰まっているといっても過言ではありません。特にCCS実習では、学生の緊張や不安も大きく、「ただ任せる」では委縮し、失敗体験だけが残ってしまう可能性があります。
📚 CCS実習における“山本五十六メソッド”とは?
以下に、山本五十六の名言に基づく育成プロセスと、それをCCSでどう実践するかを表にまとめました:
| 山本五十六の言葉 | CCS指導の具体行動 | 意義とねらい |
| やってみせ | 指導者が実際に評価や介入を行う | 学生は模倣を通じて学ぶ。「こうすればいいのか」というモデル提示 |
| 言って聞かせて | 理由や目的を丁寧に説明する | 表面的な知識でなく、背景理解を促す |
| させてみせ | 学生に実践の機会を与える | 経験を通して自ら考え、行動できる力を養う |
| 褒めてやらねば | 成果や努力に具体的に声をかける | 自信を育て、次のチャレンジへの原動力に |
| 話し合い・耳を傾け | ディスカッションやリフレクションを行う | 自己理解を深め、他者からの学びも引き出す |
| 承認し、任せてやらねば | 段階的に責任ある役割を与える | 信頼される経験が自己効力感を育てる |
| 感謝で見守り、信頼せねば | 見守りながら過度に介入しない | 自立を促し、最終的な「成長の実り」へと導く |
このような段階的アプローチを意識することで、CCS実習は「ただこなす」ものではなく、学生にとって“飛躍的な学びの場”になります。
🤝 CCSで重要な“信頼の関係性”とは?

作業療法の臨床実習において、学生の学びを最大化するために欠かせないのが、指導者と学生との信頼関係の構築です。とくにCCS(クリニカル・クラークシップ)は、学生が医療現場で「患者と直接関わる」ことを通して成長する実習形態。だからこそ、「指導者の支え」と「学生の挑戦」がかみ合う信頼関係が不可欠です。
● 指導者が意識すべき4つのポイント
① 初期段階では「見せる・語る・支える」
実習初期には、学生が戸惑う場面が多くあります。まずは、評価や治療場面を実際に見せながら、「なぜこのアプローチをするのか」を丁寧に言葉で説明しましょう。知識と技術だけでなく、臨床判断や患者理解のプロセスを可視化することが、学生の学びを深めます。
② 中盤からは「任せる勇気」を持つ
学生がある程度経験を積んだら、段階的に“任せる”機会を増やすことが重要です。リスクを管理しつつ、実際の評価や介入を経験させることで、学生は自信と責任感を養います。ここでの「見守る姿勢」が、信頼構築の要となります。
③ 評価は“結果”より“過程”に注目
学生が行った介入やアプローチの結果だけでなく、そのプロセス(判断理由・準備・反省点など)に目を向けましょう。失敗の中にも成長の種があります。具体的な行動や思考の変化に気づき、そこをフィードバックすることで、自己成長が促されます。
④ 「あなたならできる」と信じて伝える
学生の成長には、“言葉による信頼の伝達”が大きな力を持ちます。具体的な努力や進歩を認めた上で、「あなたならできる」といったポジティブなメッセージを伝えることで、学生は自らの可能性を信じて一歩踏み出す勇気を持てるようになります。
● 学生に伝えたい4つの大切な姿勢
① まずは「観察」から始めよう
最初は何もできなくて当然です。指導者の言動や関わり方をよく観察し、真似することが学びの第一歩です。記録を取りながら、自分なりの気づきを積み重ねましょう。
② 疑問や不安は言葉に出す
わからないことや不安なことは、そのままにせず、勇気を出して質問や相談をしましょう。コミュニケーションの積み重ねが、信頼関係の構築につながります。
③ 小さな気づき・成功体験を振り返る
日々の実習の中で得た気づきや成功体験は、どんなに小さなものでも大切な成長の証です。日報や振り返りノートなどで言語化する習慣を持つことで、自信や学びが深まります。
④ 「できたかどうか」より「挑戦したかどうか」
CCSでは、「完璧な成果よりも挑戦する姿勢」が重視されます失敗も含めて多くの経験をすることが、作業療法士としての成長につながります。自分の努力を認める視点を大切にしてください。
✍️ まとめ:CCS実習は“教える場”ではなく“育ち合う場”

作業療法の臨床実習、特にCCS(クリニカル・クラークシップ)では、学生がただ知識や技術を習得するだけでなく、主体的に思考し、行動し、振り返りながら成長していくプロセスが重視されます。
そのプロセスを支えるのが、実習指導者との信頼関係です。指導者は「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやる」ことから始まり、「話し合い、任せて、信じて見守る」ことで、学生が安心して挑戦できる環境を築いていきます。
また、CCS指導は一方通行の教育ではなく、学生と指導者が“共に育つ”関係です。教える側が育成のプロセスを意識し、段階的に任せていく姿勢を持つことで、学生は本当の意味で“医療の現場に立つ自分”を育んでいきます。
その成長を支えるのは、日々の関わりの中にある小さな対話や成功体験の積み重ねです。
🔚 最後に:未来の作業療法士を育てる“信頼のまなざし”を

「教育とは、信じて任せ、見守ること」――。この本質を体現するのが、CCSという実習のかたちです。
山本五十六の言葉が教えてくれるように、人は信じられ、任され、そして見守られることで初めて本当の力を発揮します。
作業療法実習の現場で、あなたが学生を信じ、育てようとする姿勢そのものが、次世代の医療を担う人材を形づくっていきます。
そして、それは単なる教育の枠を超え、「人を信じて育てる」という医療専門職のあり方を体現する行為です。
未来の作業療法士たちが、自らの力で患者と向き合えるように。
どうか、その第一歩を、あなたの“信頼のまなざし”で支えてください。
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。